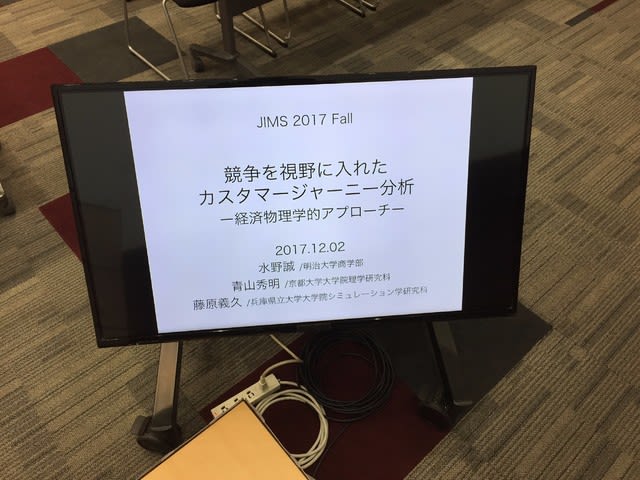JIMS「マーケティングの計算社会科学」研究部会では、NTTデータ経営研究所の高山文博さん、茨木拓也さんから、同社の最先端の実践について伺った。高山さんからは同社が構築している2万人、約1,500の変数からなる「人間情報データベース」が紹介された。その特徴は心理学や行動経済学に基づく個人特性情報を含む点にある。

すでに多くの会社が数万人規模の消費者データベースを商用化している。デモグラフィクスは基本として、購買履歴データやメディア接触データ、価値観やライフスタイルなど、各社がそれぞれの品揃えを競っている。それらに対してNTTデータ経営研究所は、人間心理の「深い」変数を、研究者の協力のもと収集することで差別化を図る。
行動履歴から観察される「相関」に基づいてデータを活用しようとするのが主流だが、行動の背景にある心理特性を把握することで Why? の問いに答えようというのが、その戦略である。その点で、ビッグデータ×機械学習だけでは満足できないという、少なからぬマーケティング研究者とも近い立場である。今後の発展を見守りたい。
後半は、同研究所で神経科学的な研究と企業へのコンサルテーションを行っている茨木さんの発表。脳情報通信技術の「恐るべき」発展の現況をまず伺い、同社が行っている実践例の紹介を受けた。たとえばテレビ広告に対する fMRI で測定される血流反応と、画像を言語化したアノテーションデータの関係が機械学習を用いて分析される。
その延長には、望ましい感情に対して最適な CM を作成することも視野に入っている。現状では測定にかなりのコストが掛かるので、個人差を扱えるような分析にはいっそうのイノベーションが必要とされる。ニューロ・マーケティングそのものは10年以上前から話題になっているが、現時点でさらに高いステージに進んでいるようだ。
今後、データを握るものが市場を支配する、ともいわれている。コンサルティング会社が広告業界に進出するだけでなく、従来にはない発想で大規模データを構築するのがひとつの潮流だろう。そこに解析手法だけでなく収集すべき情報という観点でもアカデミズムの成果が生かされる。それは研究者にとっての好機であり、試練でもある。

すでに多くの会社が数万人規模の消費者データベースを商用化している。デモグラフィクスは基本として、購買履歴データやメディア接触データ、価値観やライフスタイルなど、各社がそれぞれの品揃えを競っている。それらに対してNTTデータ経営研究所は、人間心理の「深い」変数を、研究者の協力のもと収集することで差別化を図る。
行動履歴から観察される「相関」に基づいてデータを活用しようとするのが主流だが、行動の背景にある心理特性を把握することで Why? の問いに答えようというのが、その戦略である。その点で、ビッグデータ×機械学習だけでは満足できないという、少なからぬマーケティング研究者とも近い立場である。今後の発展を見守りたい。
後半は、同研究所で神経科学的な研究と企業へのコンサルテーションを行っている茨木さんの発表。脳情報通信技術の「恐るべき」発展の現況をまず伺い、同社が行っている実践例の紹介を受けた。たとえばテレビ広告に対する fMRI で測定される血流反応と、画像を言語化したアノテーションデータの関係が機械学習を用いて分析される。
その延長には、望ましい感情に対して最適な CM を作成することも視野に入っている。現状では測定にかなりのコストが掛かるので、個人差を扱えるような分析にはいっそうのイノベーションが必要とされる。ニューロ・マーケティングそのものは10年以上前から話題になっているが、現時点でさらに高いステージに進んでいるようだ。
今後、データを握るものが市場を支配する、ともいわれている。コンサルティング会社が広告業界に進出するだけでなく、従来にはない発想で大規模データを構築するのがひとつの潮流だろう。そこに解析手法だけでなく収集すべき情報という観点でもアカデミズムの成果が生かされる。それは研究者にとっての好機であり、試練でもある。