看護学部や薬学部といったところで
未来の医療者に話をする機会が増えてきています。
テーマとしては
「外国人患者への接遇」
「外国人患者の社会的背景を知る」
「医療通訳の上手な使い方」
「医療現場におけるやさしい日本語」
学生の間にそうした基礎的な話を聞いているかいないかは
現場に出たときに違いが出てきます。
看護の場合は「国際看護」の中に1コマか2コマ組み込むことが多いです。
目的は
「外国患者人の顔を見て逃げない医療者を作る」
「外国人患者も日本人患者も配慮が必要ではあるが、接遇としては同じ」
「接遇のコツをつかむ」
もともと日本では、あまり日常的に通訳を使うことはありません。
知らないことはできないことでもあります。
また、知らない人と接するには知識が必要です。
手話通訳は毎日テレビで見ることがあり結構身近な存在かもしれませんが、
外国語のコミュニティ通訳を自分で使う機会は
日常生活の中ではあまりないと思います。
だから、私はすべての専門職の方には
現場に出る前に、こうしたトレーニングを1時間でもいいから受けて欲しいと願っています。
その際にお世話になるのが
当事者である模擬患者(SP)役をしてくださる外国人です。
先日も、神戸市看護大学で模擬患者を使った研修を行いました。
外国人患者は日本に来て日が浅く日本語でのコミュニケーションは基礎程度の設定です。
学生たちはチームで、やさしい日本語、ジェスチャー、図形、数字などを駆使して
コミュニケーションをとろうと奮闘します。
その過程が大きな学びになります。
また、英語ではない通訳を使ってコミュニケーションをとる練習もします。
上手に通訳を使えば、自分の言葉が患者に伝わり
患者の言葉が理解できるようになる不思議な体験をします。
タイムラグのある「人工衛星」からの言葉を聴いているみたいだといいます。
そして、日本に滞在する外国人患者と家族の
「言葉」「制度」「文化」の違いや背景を理解し、
特別扱いする必要はないけれど
配慮が必要であることを説明します。
でも、一番学生の心に残り、響くのは
模擬患者さんが語ってくれる医療機関で苦労した体験談です。
心細かった出産体験や言葉がわからず大変だった手術など
医療者としては想像がつきにくいことも語られます。
手話通訳の方とお話したとき
「私たちの先生はろう者」とおっしゃっていたのが印象的でした。
本来、外国人医療の先生は当事者である外国人であるべきだと思っています。
そして、学生は外国人患者から学べる機会をもつべきです。
これからは外国人模擬通訳者(SP)の育成が必要だと考えています。
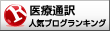
未来の医療者に話をする機会が増えてきています。
テーマとしては
「外国人患者への接遇」
「外国人患者の社会的背景を知る」
「医療通訳の上手な使い方」
「医療現場におけるやさしい日本語」
学生の間にそうした基礎的な話を聞いているかいないかは
現場に出たときに違いが出てきます。
看護の場合は「国際看護」の中に1コマか2コマ組み込むことが多いです。
目的は
「外国患者人の顔を見て逃げない医療者を作る」
「外国人患者も日本人患者も配慮が必要ではあるが、接遇としては同じ」
「接遇のコツをつかむ」
もともと日本では、あまり日常的に通訳を使うことはありません。
知らないことはできないことでもあります。
また、知らない人と接するには知識が必要です。
手話通訳は毎日テレビで見ることがあり結構身近な存在かもしれませんが、
外国語のコミュニティ通訳を自分で使う機会は
日常生活の中ではあまりないと思います。
だから、私はすべての専門職の方には
現場に出る前に、こうしたトレーニングを1時間でもいいから受けて欲しいと願っています。
その際にお世話になるのが
当事者である模擬患者(SP)役をしてくださる外国人です。
先日も、神戸市看護大学で模擬患者を使った研修を行いました。
外国人患者は日本に来て日が浅く日本語でのコミュニケーションは基礎程度の設定です。
学生たちはチームで、やさしい日本語、ジェスチャー、図形、数字などを駆使して
コミュニケーションをとろうと奮闘します。
その過程が大きな学びになります。
また、英語ではない通訳を使ってコミュニケーションをとる練習もします。
上手に通訳を使えば、自分の言葉が患者に伝わり
患者の言葉が理解できるようになる不思議な体験をします。
タイムラグのある「人工衛星」からの言葉を聴いているみたいだといいます。
そして、日本に滞在する外国人患者と家族の
「言葉」「制度」「文化」の違いや背景を理解し、
特別扱いする必要はないけれど
配慮が必要であることを説明します。
でも、一番学生の心に残り、響くのは
模擬患者さんが語ってくれる医療機関で苦労した体験談です。
心細かった出産体験や言葉がわからず大変だった手術など
医療者としては想像がつきにくいことも語られます。
手話通訳の方とお話したとき
「私たちの先生はろう者」とおっしゃっていたのが印象的でした。
本来、外国人医療の先生は当事者である外国人であるべきだと思っています。
そして、学生は外国人患者から学べる機会をもつべきです。
これからは外国人模擬通訳者(SP)の育成が必要だと考えています。









