
室堂平から、立山山頂直下に掘られた3.7キロのトンネルをトローリーバスで抜けると、大観峰という名の標高2316メートル地点に着く。確かに眺めは「大観」で、緑の壁の底に黒部湖が、深い翠色を湛えて横たわっている。前日、宇奈月からのトロッコ電車で途中まで遡った黒部川の、最上流ダム湖を見下ろしているのだ。黒部の渓谷は立山連峰と後立山連峰を裂いて南北に延び、私たちは後立山の赤沢岳や爺ヶ岳に対面していることになる。

大観峰から黒部平へ、1.7キロ間に支柱が一つもないというロープウェイで一気に下り、さらにトンネル内を下るケーブルカーで標高1455メートルの黒部湖に到着する。乗り継ぎの待ち時間を除けば室堂から22分で1000メートル下ったことになる。地中を移動している区間が多いため、登りの高原バスのような眺望は楽しめない。それにしても霊峰に、こんなに手を加えてもいいのかと、安逸な移動を享受しているくせに考えたりする。

黒部ダムは完成して今年で60年だという。完成時の世の中の興奮は、私は高校生だったから新聞などで読み、よく記憶している。ただ子供心の印象としては、その5年前の佐久間ダム完工時の方が、大人たちの興奮は凄かったように思う。それは佐久間ダムの建設が、この社会が戦後の混乱を脱し、成長経済へ離陸し始める時代に重なったからであり、その5年後の人々は、いくらか余裕を持って黒部ダム完成を迎えることができたからではないか。

ただその後の小説や映画などによって、このダムがいかに困難な工事を乗り越えて建造されたかが知れ渡り、今や「日本一のダム」と言えば誰もが黒部を上げるに違いない。巨大なだけでなく、大きなアーチを描く造形は美しくさえある。専攻に土木工学を選ぶ学生の夢は、ダム建設だと聞いたことがある。確かにダムが必要とされる場合、自然に手を加えながら膨大な貯水に耐える構造物を造ることは、技術者の夢が注ぎ込まれる壮大な仕事だろう。

黒部ダムは確かに巨大だ。186メートルの高さを堰堤から覗き込むと、ダムの下から再出発する黒部川本流が小川のせせらぎのようにか細く見える。そこを目掛けて巨大な水塊が2本、放流されて轟音を響かせている。子供のころはクロヨン・ダムと覚えたものだが、それは10キロ下流の黒部川第四発電所に水を送るダムだからだ。落差は550メートルというから、凄まじい勢いだろう。

堰堤はまるで広場のように幅がある。それだけ分厚いコンクリートとアーチ型の構造で、最大2億トンになる水圧に耐えているのだ。このダムが、計画停電に苦しむ関西の電力不足を解消したというのだから、ただの巨軀ではない。そして山の緑に打ち込まれたコンクリートを含め、堰堤の手すりのデザインにまで気を配ったというダムはどこか美しい。自然と人為の融合を楽しむ時、171人の殉職者を出した工事の過酷さを思わずにいられない。

このダム建設で最大の難工事となった赤沢岳地中の破砕帯を抜け、長野県側の扇沢に出る。駆け足ではあったものの、私の脚力でアルペンルートを越えられたことは感謝しなければならない。このルートを担うのは「立山黒部貫光」という、変わった名称の会社である。「貫」は時間を、「光」は大自然を意味し、「日本海側と太平洋側の偏差を正して地方自治の振興に寄与する」ことを企業理念にしているのだという。ルートは完全な独占事業だろうに、驕りや緩みは感じられない社員たちだった。(2023.8.25)









大観峰から黒部平へ、1.7キロ間に支柱が一つもないというロープウェイで一気に下り、さらにトンネル内を下るケーブルカーで標高1455メートルの黒部湖に到着する。乗り継ぎの待ち時間を除けば室堂から22分で1000メートル下ったことになる。地中を移動している区間が多いため、登りの高原バスのような眺望は楽しめない。それにしても霊峰に、こんなに手を加えてもいいのかと、安逸な移動を享受しているくせに考えたりする。

黒部ダムは完成して今年で60年だという。完成時の世の中の興奮は、私は高校生だったから新聞などで読み、よく記憶している。ただ子供心の印象としては、その5年前の佐久間ダム完工時の方が、大人たちの興奮は凄かったように思う。それは佐久間ダムの建設が、この社会が戦後の混乱を脱し、成長経済へ離陸し始める時代に重なったからであり、その5年後の人々は、いくらか余裕を持って黒部ダム完成を迎えることができたからではないか。

ただその後の小説や映画などによって、このダムがいかに困難な工事を乗り越えて建造されたかが知れ渡り、今や「日本一のダム」と言えば誰もが黒部を上げるに違いない。巨大なだけでなく、大きなアーチを描く造形は美しくさえある。専攻に土木工学を選ぶ学生の夢は、ダム建設だと聞いたことがある。確かにダムが必要とされる場合、自然に手を加えながら膨大な貯水に耐える構造物を造ることは、技術者の夢が注ぎ込まれる壮大な仕事だろう。

黒部ダムは確かに巨大だ。186メートルの高さを堰堤から覗き込むと、ダムの下から再出発する黒部川本流が小川のせせらぎのようにか細く見える。そこを目掛けて巨大な水塊が2本、放流されて轟音を響かせている。子供のころはクロヨン・ダムと覚えたものだが、それは10キロ下流の黒部川第四発電所に水を送るダムだからだ。落差は550メートルというから、凄まじい勢いだろう。

堰堤はまるで広場のように幅がある。それだけ分厚いコンクリートとアーチ型の構造で、最大2億トンになる水圧に耐えているのだ。このダムが、計画停電に苦しむ関西の電力不足を解消したというのだから、ただの巨軀ではない。そして山の緑に打ち込まれたコンクリートを含め、堰堤の手すりのデザインにまで気を配ったというダムはどこか美しい。自然と人為の融合を楽しむ時、171人の殉職者を出した工事の過酷さを思わずにいられない。

このダム建設で最大の難工事となった赤沢岳地中の破砕帯を抜け、長野県側の扇沢に出る。駆け足ではあったものの、私の脚力でアルペンルートを越えられたことは感謝しなければならない。このルートを担うのは「立山黒部貫光」という、変わった名称の会社である。「貫」は時間を、「光」は大自然を意味し、「日本海側と太平洋側の偏差を正して地方自治の振興に寄与する」ことを企業理念にしているのだという。ルートは完全な独占事業だろうに、驕りや緩みは感じられない社員たちだった。(2023.8.25)


















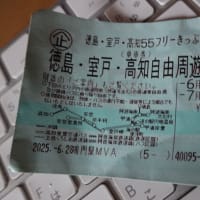



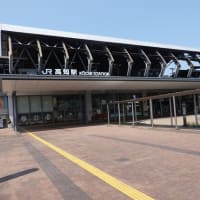










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます