
「頭が前に来る姿勢」が「歩けなくなる」入口 とは、
さすが「名医!」と思わされる分析です。
p.37 長年、数え切れない方々の足腰を拝見する中で、
体が正しいバランスから崩れていく「最初の入り口」を見つけました。
それは「頭が前に来る」姿勢とその姿勢で「歩く」ことです。
p.37 これは諸悪の根源でありながら、日本人に最もよく見られる姿勢で、
中高年の方に限らず、若い人でもこの姿勢になっている人を多く見かけます。
●歩く時、頭を前に出す
●つま先から足を着地している。
そんな歩き方は、鶏を思い浮かべると良いでしょう。鶏は、大きな体に、
不釣り合いな小さな足、いかにも歩きにくそうなデザインです。でも、
一生懸命歩こうとするものだから、一歩一歩、足を前に出すときに、
頭を小刻みに前方へ振ることになります。
あれは重心を前に移しながら、楽に歩くための歩き方です。
このような鶏の歩行にヒントを得て、「前傾姿勢で頭を振りながら
進む歩き方」のことを、僕は「ニワトリ歩き」と呼んでいます。
(中略)頭が前に飛び出ていると、肩や首は凝りを生じます。
通常の位置よりも前に出てしまった頭を支えるために、
背中から首にかけての僧帽筋が胸緊張するからです。
p.39 地球の重力が頭部を引っ張るため、僧帽筋がそれを支えることに
なります。頭部は脊椎の端っこですから、脊椎全体がこの僧帽筋を
応援し、深層筋(インナーマッスル)がずっと余計な仕事をすることに
なるのです。
頭の位置が前にあるあいだじゅう、それを支えるためのたくさんの
筋肉群がずっと仕事をします。頭が10度傾くと筋肉群の負担は2倍。
30度傾くと3から4倍との報告もあります。肩が凝りやすいと言う人が
たいて頭の位置が前に出ていることが多いのはそんな理屈です。
肩こりで腱引きをすると言う昔の人の知恵がありますが、この僧帽筋の
停止部をマッサージします。常に仕事をしている僧帽筋をいたわるのですね。
この後、「ニワトリ歩きによる弊害として、下肢バランスの崩れ、その結果としての
猫背・腰痛・膝痛がある」という説明があり、改善法が示されます。
具体的には、明日お伝えしましょう。










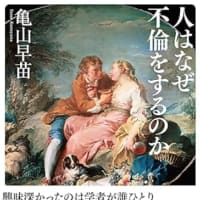

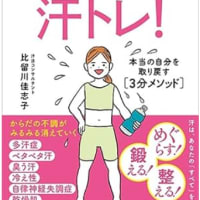
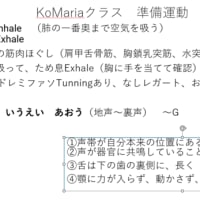








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます