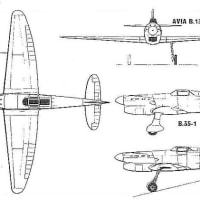日米戦争はなぜ始まったか チャールズ・A・ビアード・藤原書店
翻訳に一点だけ気になることがある。「戦艦」という言葉がよく出てくるのだが、これが軍艦を意味していると思われる場合が多い。ルーズベルトが戦艦ポトマック号に乗って出かけたと書かれているが(P171)、ルーズベルトが使用した、海軍のUSSポトマックはわずか600t余だから、戦艦どころか駆逐艦ですらないかもしれない。明らかに軍艦と訳すべきものであろう。
ところが、駆逐艦や巡洋艦と書かれている箇所もあるばかりではなく、実際に戦艦と訳すべきところを正確に戦艦と訳している箇所もあるからややこしい。最後の戦艦アイオワ級さえ退役して、現役の戦艦は世界中に存在しないにもかかわらず、どこどこの戦艦がと呼ぶ人たちがいまだにいる。彼らは軍艦のことを言っているのである。ちなみに、軍艦はwarshipで戦艦はbattleshipである。
本書は精緻な学術研究書の如くである。実証のために議会とマスコミの報道をこれでもかという位に並べている。最初は武器貸与法が、欧州での戦争に参戦するきっかけになるから反対である、という意見と、その反対に英国を強化するから参戦を阻止すると言う議会でのやり取りである。後者は詭弁に等しい。
かつての国際法は交戦国への戦争関連物資の供与は国際法違反であったが現在はそうではない、などととんでもないことを主張しているからだ。現に同時期の支那事変の日本への石油や鉄くずの輸出は、国際法上の戦争ではないから許される、という立場をアメリカはとっているのである。
ドイツが国際法違反を主張しないのは、アメリカの本格的な参戦を恐れていたからである。中立法の改正というのは、武器の交戦国への輸出は中立違反ではないとする、とんでもないものである。中立法は国際法の中立違反を、国内法で勝手に合法としたものである。米国は一般的に西欧諸国に比べ、国際法に対して厳格ではなく、自己都合で行動する節が今でもある。
倉山満氏によれば、ロシアは国際法をよく知りながら、あえて無視するという。この流儀で言えば米国は、国際法を自己の正義に従って、都合良く解釈するのである。さらに英国に支払い能力がないから武器を「貸す」ということにしたのが武器貸与法である。武器は消耗品だから貸すとほとんどが返ってこない。それどころかソ連などは武器貸与法で借りた軍用機などが残っていても全く返していない。
次は物資の英国への輸送に、パトロールと称して、実質的に護衛をしていることへの議会での賛否両論である。これも賛成派は武器貸与法と同様に詭弁を使っている。ルーズベルトとチャーチルが会談した大西洋会談も同類で、ルーズベルトが参戦の約束をしたのか否かという論争があった。パトロール部隊がドイツの潜水艦を攻撃したのは、潜水艦の攻撃以前に、政府からの命令があったのではないか、という議論もされている。真珠湾攻撃を受けた時の海軍のキンメル大将と陸軍のショート中将を職務怠慢として政府が攻撃し、退役せざるを得なくなったことについても議論があった。
戦争中に二人を軍事法廷で裁くことは、軍の機密を漏らすことになるので、戦争に不利をもたらすと言うので訴追されなかった。戦争の勝利が確実になりつつある時期にも訴追されないのは、政府や陸海軍上部では日本の真珠湾攻撃の可能性がある情報を持っていたにもかかわらず、故意に両将軍に知らせなかったためではないかという疑惑があったからである。
また来栖特使との交渉が始まると、太平洋艦隊はずっと真珠湾に集結停泊していた(P375)という。これは戦争準備だと言うのだ。真珠湾攻撃の72時間前にオーストラリア政府は日本艦隊が真珠湾に向かっていると本土の米政府に警告し、警告は再度行われたが、この情報はハワイのショート中将には伝達されなかったと、ハーネス議員が陸軍委員会で追求した(P377)。
さらに太平洋艦隊を真珠湾に集結するのは、日本に艦隊を全滅させられる危険がある、と反対した海軍作戦部長を、ルーズベルト大統領は通常の半分の任期で解任したと言う(P391)のだ。疑惑は武器貸与法の賛成者やパトロールの賛成者が、欧州戦争に参戦したがっているのではないか、ルーズベルト大統領も同様だったのではないか、ということである。真珠湾攻撃情報の隠匿も疑惑である。結局、上巻では全てが状況証拠による疑惑に過ぎず、文書等による決定的な証拠は提示されていない。
ひどいのは、米軍がグリーンランドを占領した件である。米政府はドイツに利用されるのを防止するために、グリーンランドを「侵略」したのである。ところが記者会見でこのことを聞かれると「それは初耳だな!私が眠っている間の事に違いない(P31)」と笑ったと言うのだ。この当時のアメリカ大統領はマスコミも歯牙にかけない独裁者であったのだ。
多くの日本の識者は日本の北部佛印進駐などをアメリカを挑発したというが、これは米英による武器輸送の仏印ルートの阻止であり、本国のフランス政府とも協議している。グリーンランド占領はもっと乱暴で、ドイツに宣戦布告したも同然である。日本の対支政策を米国が批判するのは勝手だが、禁輸などの戦争行為を実施されるいわれはない。当のアメリカはドイツを直接挑発していたのである。
なお、昭和16年3月のギャラップ調査では米国民の83%が外国の戦争に参戦するのに反対(P111)であったというのだがあてにはならない。人は戦争に賛成か反対かと言われれば、無反対というに決まっているからだ。現に国際法上の参戦となる中立法の改正や武器貸与法は圧倒的多数の賛成で成立した。この背後には多くの支持者がいるからである。
アメリカの政治家、有権者、法律家やマスコミはこれらの法律の意味を知らないほど愚鈍ではない。戦争には反対だが、英国の崩壊とナチスドイツの台頭は許さないのである。即ちこれは参戦を意味する。現に駆逐艦への独潜の攻撃に対して反撃したと大統領が発表するとホワイトハウスに膨大な反響が届き、8対1で好意的だったというのだ。ここまでが上巻である。
下巻だが、これも結局は状況証拠であった。例によって色々な報道や関係者の意見を倦むことなく提示する。ニューヨークタイムズ紙の昭和20年9月1日付けの新聞にハルノートについて「・・・合衆国政府が意図的に日本を、高圧的で独断的な難題でもって挑発し、戦争に追い込んだのであり、日本がわが国を真珠湾で攻撃したのは、この「最後通告」に対して唯一回答可能な返答をしたのだった、という結論を下しても、許されるのかもしれない」(P453)と書く。
戦後もアメリカではルースベルトの開戦に至る政策を擁護する多数派と、故意に日本を戦争に追い込んだという少数派の議論があった。多数派は真珠湾攻撃は、いわれなき侵略行為であり(P480)合衆国の外交政策と行動は、日本のこの国に対する攻撃を正当化するような挑発行為にはまったくあたらなかった(P481)というものである。
これに対して議会の委員会で少数派はスティムソン、マーシャル、スタークらの陸海軍首脳の会議で「次の月曜日(12月1日)にも攻撃される公算が高いとし、わが国にさほど甚大な危険を招くことなく、奴ら(日本)が最初に発砲するように誘導するか、という問題を議論した(P496)という結論を提示した。
だが、多数派ですらルーズベルト政権は、単に対日戦絶対反対ではないと考えている。当時の国務次官補のパーリーは中立と孤立主義からの転換を1938年頃だと見ている。その証拠は1937年10月のルーズベルトの隔離演説である(P561)としているが、隔離演説は秘密でも何でもない。
何とルーズベルトの追悼演説にすら、武器貸与法などの連合国への支援があきらかな参戦行為でありながら「大統領はこの一連の込み入った動きに携わりながらもわが国による侵略行為が外観として現れることすら回避すべく巧みになされたのである。」(P564)としているのは当然であろう。武器貸与法やグリーンランド占領などが参戦行為だと言わないのは児戯に等しい。単にドイツ軍と砲火を交える本格的参戦ではないだけである。
親日派として知られるグル―大使ですら「・・・日本の制度、政治、党利、そして調和を重んじる日本国民と好戦的な軍国主義者の間の激しい対立によく通じていた」(P669)と書くのは著者の見解でもあろう。知日派と言われる人たちですら、日本人を理解してはいなかったのだ。興味深いのは、日本の外交暗号は解読されて「マジック」と呼ばれ、日本側の日米交渉の意向は全て米国に筒抜けになっていたことは以前から知られていたが、このことを公式に認めたのは1980年であったということだ。
著者の独自性は、これらの状況証拠を執拗に追求したことではない。多数派は、「ヒトラーの専制政治を打倒するために」必要だと言われた戦争を開始するためには国民を欺くことさえやむを得なかったということを念頭において詭弁を弄した。少数派は「ヒトラーに対して中立であるという考え方自体が一九四一年に恥ずべきものだったとするならば、テヘランやヤルタで平和と国際的友好の名のもとに交わされた約束はどう評価されるべきなのか。」(P757)として結局は「ヒトラーの体制に劣らず、専制的で非情な新たな全体主義政権」(P756)を強化したことを非難する。
著者がこの本で追求したかったことは、ルーズベルトが詭弁を弄して国民を欺き戦争を開始したこと自体にあるのではない。目的が違法な手段を正当化することにより、憲法のもとで議会に与えられた権限を欺瞞により実質的に大統領が奪ってしまったことを言いたいのだ。そして議会制民主主義を破壊しかねないことだ。こうしたことがかえって専制の危険をまねいたことである。そのことをエピローグで執拗に訴える。
「・・・合衆国大統領は再選を目指す選挙の議会の運動期間中に、この国は戦争に参加することはないと国民に対して公の場で約束しておいて、選挙に勝利した後、国に戦争をもたらすための、あるいは戦争をもたらすことが事実上必至の行動に密かに乗り出してよいことになる。」「合衆国大統領は、その秘密の目的を推進する法律を成立させるため、連邦議会と国民に、その法律の趣旨を偽ってもよいことになる。」「アメリカの軍隊を投入して第三国の領土を占領することを、実際に合衆国大統領として約束しておきながら、公式発表では新たな約束は交わされていない、と宣言してもよいことになる。」「・・・いかなる条約の同盟よりも、合衆国の命運にとってはるかに重大な影響をもたらす秘密合意を外国政府と結んでよいことになる。」「合衆国大統領は、特定の外国政府を合衆国の敵であると勝手に決めつけて、そうした国に対してこれまでのところ、合衆国で受け入れられ強制されてきた国際法の原則と国内法に違反して、随意に戦闘を起こす権力を求めることができ、連邦議会も従順にこれを大統領に付与できるということになる。」(p762~763)
引用はこれで充分だろう。この著書を書く以前からルーズベルトの政策に批判的であったビアードは、第二次大戦戦勝のムードから大きな批判を受け、中傷もされたという。当然であろう。このような米国人を見るたびに思うのは、日本では異論は受け入れられない雰囲気がある、というのは嘘だということである。米国でも異論はビアードのように排斥される。
しかし、それを恐れない強烈な個性があるかどうかが違うのである。かのミッチェル准将は、軍艦に対する航空機の優位論を唱え空軍の独立を強烈に主張したために、ある事故を口実に陸軍を追放された。もうひとつ感じるのは、西洋人の唯我独尊の考え方である。米国は勝手にグリーンランドなど他国の領土を占領しても平然としているのに、日本が協定により仏印に進駐するなどの行為をしても侵略とみなすのである。ビアードにもこの放漫はある。今の日本人は、これらの不条理を感じないように洗脳されつくしている。
ビアードの検証を読んであらためて、当時の米国民の大多数は実は、欧州への参戦に賛成であると考えていたことを実感した。なるほど大統領選挙の際には不参戦は約束された。世論調査も圧倒的に参戦反対である。戦争に参加したいか否かと聞かれれば、反対と答えるのは人情であり建前である。ところが、本書が論証したように、実質的に参戦である武器貸与法や英国への物資輸送の米海軍のエスコートに賛成し、グリーンランド占領に賛成した議員やマスコミは、戦争への道ではないと明らかな詭弁を弄した。
しかもこれは多数派だったのである。多数派だから法律は成立したのである。国民はその議論は詭弁であるとは非難しなかったし、反対派もその点を突きはしなかった。国際法の中立違反、すなわち正確には参戦行為であることを充分に知っている、国際法学者も非難の声を上げることはなかった。少なくとも世論を動かすような発言はしなかった。
できるはずなのに、米国民の特性である激しい批難はしなかったのである。議会の多数派の支持者は国民の数に於いても多数派である。つまり建前は戦争反対だが、暗黙の了解のもとに戦争への道を支持したのである。
それではなぜ世論調査は圧倒的に戦争反対の声をあげたのか。多数派は戦争にはならないからというのは嘘だと知りつつ、武器貸与法などの法律に賛成したのであり、少数派は戦争になるから反対した。つまり、どちらも上っ面だけみれば、戦争に至らない道を求めていた、と言うことになる。だから多数派も世論調査では戦争反対の声を上げた。世論調査が戦争反対の結果を出すのは当然である。
多数派でも少数派でもなく、公然とヨーロッパへの戦争に介入すべきだと主張した人たちがごく一部にいる。彼らだけが、世論調査で戦争賛成の声を上げたのである。これが世論調査では戦争反対が圧倒的であったのに、実は米国民の多数が参戦すべきであったと考えている、という一見矛盾した事態のからくりだと小生は考えている。
脱線するが、ブロンソン・レ―という米国人は、戦前、満洲国出現の必然性、という著書をあらわし、米国流の正義を敷衍して、満洲国の正統性を主張した。その中で、何と自身が米西戦争の原因となったメイン号爆沈の犯人がスペインではなく、限りなく米国自身であったと言う証拠を現場で発見しながら、スペイン人に渡すのを拒否したと告白している。これが米国人の正義の一端を示している。小生はレ―氏の欺瞞を非難しているのではないことを付言する。
閑話休題。戦後も同じである。多数派は、キンメル大将とショート中将が真珠湾攻撃の責任を取らされて解任されたのち、訴追されなかったことについて追及をしなかった。少数派は、ホワイトハウスにやましいことがあるから訴追しなかったと追及した。開戦直後は軍事機密があり、法廷での証言は戦争の遂行に支障をきたす、という弁明がなされたが、戦争が終わるとそれも通用しなくなった。両司令官が解雇ではなく、自発的に退職したことにさせられたことについても少数派は疑惑の目を向けている。解雇という不名誉な措置は、両司令官の何らかの反撃に出ることになるとホワイトハウスは恐れていたというのだ。
私はこの本の上巻を読み終えてルーズベルトが戦争への道を裏で画策していたということについては、この本は結局は、他の本と同じく状況証拠しか提示できないであろうと推測したがやはりその通りであった。私はある時から米国民の多数派は欧州への参戦に賛成であったという確信をもつようになったが、世論調査は参戦の直前まで圧倒的に戦争反対であったと言う矛盾を解消できなかった。しかし、本書で米国での戦前戦後の論争を読んで、この矛盾を解くことが出来た。これが最大の収穫である。