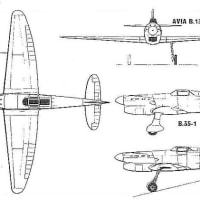第二次大戦の分岐点の定説について、独自の観点からとらえている、というような趣旨の書評につられて読み始めたが、よく調べられているのは流石だが、衒学と情緒的書きぶりに少々嫌気がさして放棄した。読み込めば価値はあるとは思うのだが、気分的にどうにもならない。また簡単な間違いや思い込みが目につくのも気になる。
典型は第三章の「プリンシプルの男」である。書評にはならないが、本項ではこの点の批判だけする。「プリンシプルの男」とは零戦の設計主任の堀越二郎のことである。設計者として必要な資質としての、自分の立てた原則を曲げないという性格を持っているというのだ。本書に書かれている頑固さの例は、安全率の規定を部材によっては緩和すべき、と主張して担当官をねばり強く、説得したというものである。
本書にはないが、類似の例では堀越氏が、艦上戦闘機烈風が要求性能に達しないことが判明したとき、色々な実機のデータから、設計より以前に、誉エンジンに問題があることを立証して、ついに会社のリスクでエンジンを換装することで海軍を説得したのであった。官が民に対して高圧的であった当時にあって、その行動力は物凄いものである。だがこれらの例はプリンシプルと言えるのだろうか。自分が正しい、ということを主張したのであって、何かの原則に基づいて主張したものではない。
逆に、海軍の要求仕様について、戦闘機の性能では格闘性能か高速力が優先すべきか、というような議論を軍のパイロットが議論を始めたとき、堀越は傍観者として見ていた。正否はともかく、二人のパイロットには、戦闘機のあるべき「プリンシプル」があったのに、堀越は持ち合わせていなかったのである。堀越のプリンシプルは別なところにあった。それは重量軽減である。本書にも書かれているが、その執念は尋常ではない。
戦後防衛大学で堀越から航空工学の講義を受講した人物が、堀越教授は重量軽減についてばかり講義して、毎回機体の重量計算ばかりさせていた、ということを小生はある資料で読んだ。それだけで一年の授業が持つのかと不可思議であるが、別な資料でもう一人の同様の証言があり、両人とも堀越を尊敬している風はあっても、非難する様子ではなかったから、事実なのであろう。
堀越自身が、「一キロの重量軽減は多量生産時の工作時間三十時間に値する」(零戦)と述べている位である。当時は一万機に達する大量生産は予期していなかったから、仕方ない、という説もあるが、千機であっても工数低減の影響が大きい多量生産の部類である。その程度の生産量は想定内だし、堀越の言わんとするのは工数が増えても重量軽減の方が大事だ、ということだけである。現に堀越自身の著書によれば、生産工数比較では零戦は、かのP-51の三倍である。
工員の賃金をドル-円換算して比較すると、コストにすれば、零戦の方がP-51より安い、と堀越は言うのだが、人的資源の消費という観点からすれば、工数の大小が問題である。工数が多ければ、他の軍需物資の生産に回せる人員を零戦の生産が食ってしまうことになる。人口が余っていれば問題とはならないが、当時でも人口は日本の方がアメリカよりずっと少ない。
マスタングは生産中にも工数低減の努力をしているから、この差は縮ってはいなかったどころか広がっていたであろう。堀越は七試単戦から5種の戦闘機設計をしており、海軍の要求のシビアさから戦闘機設計のプリンシプルとして、重量軽減に到達したのだろう。しかし、戦後航空工学の講義でそれを教えた、ということは飛行機一般の設計の原則としたということだろう。
しかし、飛行機が空を飛ぶ以上、どんな設計者にとっても重量軽減は原則のひとつであるのは当然である。そして、飛行機設計には他にも色々な要求があり、機種によっても要求の優先順位は異なるので、それらのバランスが設計の妙であろう。それを、重量軽減しか教えない、というのは余りにバランスを欠いている。それは技術者に必要なプリンシプル、というものではなかろうと思うのである。
また、零戦の技術的特徴をいくつか列記しているが、引込み脚や翼の捩じり下げなど、そのほとんどが日本でも外国でも既知のものである。捩じり下げの効果の説明は間違いであるし、沈頭鋲を「ネジ」としているのもいただけない。簡単に確認できるミスである。
零戦は客観的に見れば、隼などの同時期の日本機に比べても格段に優れたものではない。大東亜戦争緒戦の日本戦闘機の優位は、支那事変で実戦を経験した、熟練パイロットの技量に負うところが多い。また隼の戦果さえ米軍は「ゼロ」と恐れていた節さえある。要するに著者は零戦神話に眩惑されている。前述のように書評にはなってないが、これでやめておく。