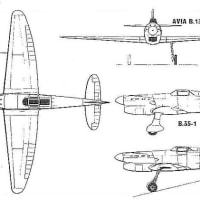このブログに興味をお持ちの方は、ここをクリックして小生のホームページも御覧ください。
書評・支那事變國際法論・立 作太郎・松華堂・昭和13年5月
神田の古書店でタイトルに惹かれて買った本である。何年も放置した後に一気に読んで読み終えた。読み飛ばすと面白くないが、意味を正確に読み取るように精読すれば、国際法が理解でき腑に落ちることが多いので面白く読めることが分かった。もっとも法律の素養がない小生には、読み切れていない部分も多いはずである。同じ論旨の繰り返しに思える部分も意味があるのであろう。繰り返しに思えるのも小生が素人であるのが原因である。読んでいる最中に論理の展開の仕方が、パール判事の東京裁判の判決書に似ている事に気付いた。同じ国際法の専門家であることがなせるわざである。面白いのは、外国の都市や国名の漢字表記が一部に一般的なものではないと思われるものが使われていることである。これは単に当時の外国の都市や国名の漢字表記が現在よりバリエーションが多く、それらの一部が現在では忘れられたと言うことなのだろう。
タイトルからして、支那事変の日本軍の行動を国際法を援用して弁明しようとする本だろうと言う予想は外れた。むしろ戦時国際法の教科書にしてよい位であろう。それこそ国際法の創成期から当時の国際法の説への変遷まで引用しているのである。小生にとってのポイントの一番は、事実上の戦争と国際法上の戦争の区分である。日本が戦時の中立条項によって、アメリカから石油やクズ鉄などの物資の輸入が止まらないように宣戦布告をしなかったのはよく知られているが、支那事変のような事実上の戦争に置いても交戦法規は適用される、という点である。
同時に、意外にも思われる事実は、当時は宣戦布告した国際法上の戦争は少なく、ほとんどが事実上の戦争であったと言うことである。事実上の戦争が常態化している、という事により真珠湾攻撃が宣戦布告なしに行われた、ということは何ら国際法違反ではなく、交戦法規さえ守れば良いということが論理的帰結である。ちなみに本書は冒頭に記した通り、真珠湾攻撃の3年以上前に出版されているから、真珠湾攻撃の擁護のためではなく、当時の戦争の実態を述べたものであることは言うまでもない。
アメリカの中立法についての記述も時代を反映したものである。アメリカは時々国際法を無視した行動や立法をするが、中立法もその典型である。アメリカの中立法は、必ずしも国際法の中立の概念とは相いれない、身勝手なものである。欧州大戦が始まってからも中立法を改正して、参戦していないのにもかかわらず米国はヨーロッパに大量の武器援助をするという国際法上の中立義務違反をした。この時の中立法についての立氏の見解を聞きたいものであるが、残念な事にまだ大戦は始まっていなかった。中立法については、著者は淡々と解説をしているだけであり、特定の国を批難する言辞はなく、著者が純粋に法律的立場から論じていることが分かる。
三章の支那事変における空中爆撃問題は、解釈を拡大すれば米国の日本本土空襲を国際法違反としない見解も生まれかねない危険なものである。例えば、
1.P75「・・・政庁の在る建物・・・の中央幹部の置かれる建物の如きは、支那軍作戦の中枢と緊密の関係あるを以て、之が破壊又は毀損を為し得ると為すの説は有力であると言わねばならぬ。(以下すべて新仮名遣いに直した。)
2.P91「・・・将来の戦争に於いて人民の大聚団(great center of population)に爆弾を投下することが行わるべく、国際法は之を禁ずること無く、倫敦の如き都市が無防守の都市として空襲を免かるるためには、敵の航空隊に降参するの外なしと説けるに端を発し、ホランド教授も参加するに至れる論争に関連して、スペート自身の説を著者中に於いて述べた際、無防守とは軍により占拠されず、其他武力的抵抗を為すの地位に在らざることを意味すると為し、倫敦の如き都市は、陸戦条規又は海軍力を以てする砲撃に関する条約に依りて攻撃を受けざるを得ることとならぬ旨説いたのである。
その後に、国際の慣行が教授の説く所に一致するに至らざることは云々と書いてはいるものの、2.の説はまさに東京への空襲を是認したごとくである。1.にしても、天皇が大元帥であるを以て国会議事堂のみならず、皇居の空襲をも許容されるごとくである。日本軍は誤爆を除き支那の民間施設を破壊したことはないのだから、このような説は日本軍の弁護のためではない。しかもこの本の説くところは、交通機関は軍事利用されるを以て空爆の対象となる。
次の興味は七章の九カ国条約と支那事変である。米国のフェンウィック教授が国際法専門誌に、宣戦布告があろうとなかろうと支那と戦争をしているのは、九カ国条約違反である(P219)と書いたのは九カ国条約と不戦条約を混同しているばかりではなく、不戦条約も自衛戦争を禁止していない、と説くのは当然であろう。しかも自衛戦争か否かの判断は国家主権に属するとの留保をしたのは他ならぬ米国である。しかも九カ国条約の言う門戸開放とは、元来「支那に於いて領土を占領せる者が、従来支那の行へる如く、自由に其門戸を開放すべき」(P237)であったのが、支那の全土に適用されるように変更されたのが九カ国条約である、というのである。九カ国条約は、要するに日本をも含む欧米諸国が支那で自由勝手に行動して良いというひどいものなのである。
九カ国条約の義務については、結論から言えば、支那の赤化に伴う抗日運動の激化は、国際法の言う事情変更の原則によって、条約義務が消滅している、と説く(P259)。もちろん事情変更の内容によっては義務が消滅する内容は限定される。いずれにしても支那の抗日運動は現在想像される範囲を超えたテロの連続、と言うべきものであった。イラク戦争終結後のイラクでのテロと同然であった。これに対して日本は国際法上の正当な権利を行使すべきであったのに、日本の政治家はしなかったのである。日本政府は支那の在留邦人をテロから守るために国際法上の権利を行使すべきだったのである。英米は支那の外国人への暴行に対して一致して砲撃した。しかし共同行動を要請された幣原外相は断った。
その他は紹介しないが、いかに当時の日本人がいかに真面目に戦時国際法を研究していたか良く分かる。戦後大東亜戦争について、この本の程度に於いて戦時国際法上の研究をした論文を知らない。日本の侵略をあげつらうものが、戦時国際法をつまみ食いして利用した程度のレベルが低いものしか見ないのである。今の日本ではまともな戦時国際法の図書を寡聞にして知らない。まだまだこの本に教えてもらえることはある。例えば国際法は、国際的慣習と国家間の条約により成り立つものとされている。しかし、条約にも、国際法となるべき慣習をなすものと、単に条約関係国相互の約束に過ぎないものがあると教えている。
何かの本で、戦前は、ゲリラ等の政府ではない団体は交戦団体と認めなかった、と書いたものを読んだ記憶がある。しかしそれは間違いであった。本書によれば、「・・・内乱の現在の事態および内乱後の将来の事態に関して利害関係を有する第三国は、政府と叛徒との間の闘争に関して対等の地位を認むるの必要を感ずることあるを以て、国際法は、特に交戦団体の承認の制度を認め、・・・(P19)」と書いてある。つまり反政府ゲリラは無条件ではないにしても、当時より戦時国際法の交戦団体と認められることがあったことが分かる。
さてこの本は今では国会図書館位でしか見られないから、皆様読みたくなっても、入手不可能に等しいから( ^^;)と考える次第です。