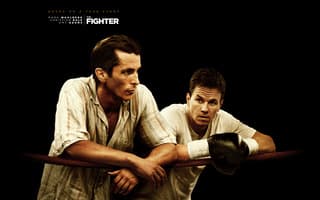(英題:Gulliver's Travels)
※エンディングについても触れています。ご注意!

----これって、誰もが知っているあのお話だよね。
ガリバーが小人の国に行くという…。
「そう。
ただ、原作では確か四部作になっていて、
次が巨人の国。あと、空の上に浮かぶ国に行ったり、
人間と馬とが主従逆になっている国に行ったりする。
ぼくは最後の『馬の国』が
いちばんオモシロかった記憶がある」
----よく知られている割には
意外に映画になっていないよね。
「そうなんだ。
なぜだろう?
CG登場までは、合成が難しかったのかな?
小人との比率があまりにも大きすぎるし…。
ただ、他の物語をも含めれば、
『天空の城ラピュタ』や
『猿の惑星』に影響を与えているなど、
まったく映画と無縁というわけでもないけどね。
東映動画には『ガリバーの宇宙旅行』というのもあるし…。
さて、この映画、
誰もが知っているお話だけに、
ストーリーを語っても仕方がない。
今回の映画化に際しては、
舞台を現代に移し替えていることを意識すればそれでいいと思う。
ガリバーを演じているのはジャック・ブラック。
ここがまずポイントだね。
彼は、ニューヨークの新聞社に勤める郵便係。
旅行記者になる夢も、5年越しの恋もかなえられないでいる彼が、
ひょんなことからバミューダ・トライアングルの取材の仕事をゲット。
ところが、その海で遭難し、
小人たちが住む“リリパット王国”へ。
図体の大きさを生かして王国の危機を救ったことから、
ヒーローとしてあがめられていく存在となるが…」

----ジャック・ブラックだと、
コメディ色が強くなりそう。
「そうだね。
ぼくも観る前は、それを心配したんだけど、
そこが絶妙のさじ加減。
体は大きいけど中身は小さいという情けなさを見事に演じていた。
そこに、彼ならではの個性、
“ロック”が生かされていて、
おとぎ話の中に現代性を融和させた
なんともユニークな作品となっていた。
実は、エンディングで突如ミュージカルになるんだけど、
そこで使われる曲が秀逸。
エドウィン・スター『黒い戦争』。
これもジャック・ブラックのアイデアらしいよ」
----へぇ~っ。監督は誰ニャの?
「やはり巨大化した女性がヒロインだった、
『モンスターVSエイリアン』のロブ・レターマン。
こういう100%どころか200%ありえないお話って、
メリエス『月世界旅行』の頃から映画の持つひとつの特性。
この映画では、
そこにiphoneやコーラの缶など、
こちらの世界のそれも現代のモノを持ちこみ、
さらには
映画『タイタニック』『スター・ウォーズ』を合体させた
ほら話を芝居で上演させるという楽しいお遊びも。
セット、CG合成にも手を抜いていないし、
はたまた、巨人の国も一部登場させるなど楽しさ満点。
オスカーとかにはまったく無縁だけど、ぼくは大好きな一本だね」

(byえいwithフォーン)
フォーンの一言「初めにジャック・ブラックありきの映画なのニャ」
※ただ、3D効果は感じられなかった度


 こちらのお花屋さんもよろしく。
こちらのお花屋さんもよろしく。
こちらは噂のtwitter。

「ラムの大通り」のツイッター

 人気blogランキングもよろしく
人気blogランキングもよろしく
☆「CINEMA INDEX」☆「ラムの大通り」タイトル索引
(他のタイトルはこちらをクリック→)

※画像はオフィシャル(壁紙ダウンロードサイト)より。
※エンディングについても触れています。ご注意!

----これって、誰もが知っているあのお話だよね。
ガリバーが小人の国に行くという…。
「そう。
ただ、原作では確か四部作になっていて、
次が巨人の国。あと、空の上に浮かぶ国に行ったり、
人間と馬とが主従逆になっている国に行ったりする。
ぼくは最後の『馬の国』が
いちばんオモシロかった記憶がある」
----よく知られている割には
意外に映画になっていないよね。
「そうなんだ。
なぜだろう?
CG登場までは、合成が難しかったのかな?
小人との比率があまりにも大きすぎるし…。
ただ、他の物語をも含めれば、
『天空の城ラピュタ』や
『猿の惑星』に影響を与えているなど、
まったく映画と無縁というわけでもないけどね。
東映動画には『ガリバーの宇宙旅行』というのもあるし…。
さて、この映画、
誰もが知っているお話だけに、
ストーリーを語っても仕方がない。
今回の映画化に際しては、
舞台を現代に移し替えていることを意識すればそれでいいと思う。
ガリバーを演じているのはジャック・ブラック。
ここがまずポイントだね。
彼は、ニューヨークの新聞社に勤める郵便係。
旅行記者になる夢も、5年越しの恋もかなえられないでいる彼が、
ひょんなことからバミューダ・トライアングルの取材の仕事をゲット。
ところが、その海で遭難し、
小人たちが住む“リリパット王国”へ。
図体の大きさを生かして王国の危機を救ったことから、
ヒーローとしてあがめられていく存在となるが…」

----ジャック・ブラックだと、
コメディ色が強くなりそう。
「そうだね。
ぼくも観る前は、それを心配したんだけど、
そこが絶妙のさじ加減。
体は大きいけど中身は小さいという情けなさを見事に演じていた。
そこに、彼ならではの個性、
“ロック”が生かされていて、
おとぎ話の中に現代性を融和させた
なんともユニークな作品となっていた。
実は、エンディングで突如ミュージカルになるんだけど、
そこで使われる曲が秀逸。
エドウィン・スター『黒い戦争』。
これもジャック・ブラックのアイデアらしいよ」
----へぇ~っ。監督は誰ニャの?
「やはり巨大化した女性がヒロインだった、
『モンスターVSエイリアン』のロブ・レターマン。
こういう100%どころか200%ありえないお話って、
メリエス『月世界旅行』の頃から映画の持つひとつの特性。
この映画では、
そこにiphoneやコーラの缶など、
こちらの世界のそれも現代のモノを持ちこみ、
さらには
映画『タイタニック』『スター・ウォーズ』を合体させた
ほら話を芝居で上演させるという楽しいお遊びも。
セット、CG合成にも手を抜いていないし、
はたまた、巨人の国も一部登場させるなど楽しさ満点。
オスカーとかにはまったく無縁だけど、ぼくは大好きな一本だね」

(byえいwithフォーン)
フォーンの一言「初めにジャック・ブラックありきの映画なのニャ」

※ただ、3D効果は感じられなかった度



 こちらのお花屋さんもよろしく。
こちらのお花屋さんもよろしく。こちらは噂のtwitter。
「ラムの大通り」のツイッター

☆「CINEMA INDEX」☆「ラムの大通り」タイトル索引
(他のタイトルはこちらをクリック→)
※画像はオフィシャル(壁紙ダウンロードサイト)より。