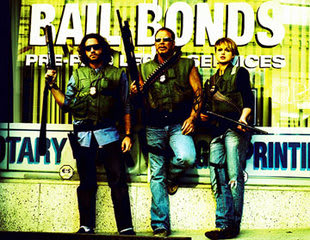1920年代後半から1930年代にかけてのお話。人々は現代人とはかなり違う。女性は特に違っただろう。そんな時代の仕事のできるシングルマザーをアンジーは実にうまく演じた。彼女が演じたクリスティンコリンズは非常に難しい状況におかれるのだが、彼女の抑えた演技と、感情を爆発させるときの演技、どちらも本当に素晴らしかった。心配していた自分が恥ずかしい。
一人息子が失踪したというだけでもかなりまいってしまう状況なのにもかかわらず、まったくの他人を息子だと言って帰され、その子までが自分がウォルターだと主張し、警察に訴えれば訴えるほど頭がおかしいと扱われ、とうとう精神病院にまで送り込まれる。誰がどう考えてもおかしな状況で、歯医者や学校の先生が戻ってきたウォルターは偽者だと主張しているのに、警察は自分たちの非を認めたくないためにクリスティンを狂人扱いする。警察も自分たちのやっていることは重々承知の上だろう。それでも、そのパワーをフルに利用し、警察に刃向かうもの全てを押さえつけようとする。クリスティンの件がまかり通ったのは、このときのロス市警が腐敗しきっていて、市民も警察に不満は持ちながらも、警察ににらまれるのが怖いために行動を起こせなかったからだろう。
クリスティンは、はからずも結果的にこの警察権力と戦った女性というふうになってしまうのだけど、それはひとえに彼女の母親としての強さがあったからだろう。ウォルターはどこかで必ず生きている。その想いが彼女をそこまでさせたのだろう。本当は警察権力を失墜させることなんて彼女にはどうでも良かったのだと思う。でも、彼女はたった一人の息子を取り返すために警察と戦うはめになってしまう。そんな事態を招いたのは他でもない警察であり、結局警察は墓穴を掘ったということなのだが。
映画としては少しスリリングさに欠けるところがあるとは思うのだけど、クリスティンの母親としての強さにスポットを当てた場合、あのような演出になるのはある程度理解はできる。あの当時、特に女性がどれだけ警察だけでなく社会において、下等なものだと見られていたかということが、精神病院に入れられている娼婦キャロルエイミーライアンとクリスティンの会話において、垣間見ることができるようになっていたり、クリスティンの事件と重大なかかわりを持ってくる連続殺人事件が明らかになるシークエンスなどはさすがのイーストウッドの演出と言えると思う。静かではあるが、全体的にとても丁寧に作られていることが観客に伝わる素晴らしい演出である。(娼婦のキャロルに「適切な言葉で話さなきゃだめよ」と言われて、お上品なクリスティンが医者に「FUCK」という言葉を使うシーンは胸がスカッとしたな)
演技に関して言えば、先に書いたアンジーだけでなく、憎むべき警部役のジェフリードノヴァンも、観客が本当に心の底から憎ったらしいと思ってしまうほど良い演技をしているし、出番は非常に少ないけど、クリスティンに協力してくれるハーン弁護士ジェフリーピアソンも登場シーンすべてにおいて、大きな存在感があって、役のせいもあるけど、ものすごい安心感を感じさせてくれた。ジョンマルコヴィッチの演技についてはここで語る必要もないだろう。彼の普通に善人の役ってめずらしいな。しかし、彼が敵役だと絶対に勝てない気がするけど、今回味方で本当に良かった。
最後にウォルターと一緒に誘拐されていた少年が5年たって出てくる場面では、クリスティンはそれがウォルターではなかったことに大きな落胆を覚えたに違いないのに、同じ立場であったその子の母親を祝福し、彼が戻ってきたことが、ウォルターが生きているかもしれないという希望につながったというのが、母って偉大だなぁと思わせた。
ウォルターをかたっていた少年が最後に警察に自分がウォルターだと言えと言われたという場面が少しだけあるけど、そこの部分があまり突っ込まれていなくて、本当にあの子は警察に脅されたかうまいこと言われたかしたのかどうかよく分からないまま終わってしまったのが、唯一残念だった。
オマケ
 Changelingってどういう意味?と思って調べると「取り替えられた子、すりかえられた子」とあった。え?なんでそういう言葉にひとつの単語が独立して与えられてるわけ?と思ってもう少し調べると、西洋の伝説で人間の子供がフェアリーやトロールの子と取り替えられるというお話の伝承があったらしく、事実としては発達障害や自閉症の子が昔は理解されていなかったため、この子はトロールの子に違いないというふうに思われていたということらしい。
Changelingってどういう意味?と思って調べると「取り替えられた子、すりかえられた子」とあった。え?なんでそういう言葉にひとつの単語が独立して与えられてるわけ?と思ってもう少し調べると、西洋の伝説で人間の子供がフェアリーやトロールの子と取り替えられるというお話の伝承があったらしく、事実としては発達障害や自閉症の子が昔は理解されていなかったため、この子はトロールの子に違いないというふうに思われていたということらしい。

















 」って本気でビックリしていたところだ。
」って本気でビックリしていたところだ。 それにしても、戦争のためにはジャンジャカジャンジャカお金を出す政治家も学校建設のためにはビタ一文出さないってね、それもそれで典型的だけど、あのときアメリカが学校建設をしていたら、どうなっていたんだろう?反米意識の高いイスラム原理主義は育たなかっただろうけど、その代わりアメリカバンザイ国が誕生していたんだろうか?戦後のGHQと同じ?それはそれで怖いような…
それにしても、戦争のためにはジャンジャカジャンジャカお金を出す政治家も学校建設のためにはビタ一文出さないってね、それもそれで典型的だけど、あのときアメリカが学校建設をしていたら、どうなっていたんだろう?反米意識の高いイスラム原理主義は育たなかっただろうけど、その代わりアメリカバンザイ国が誕生していたんだろうか?戦後のGHQと同じ?それはそれで怖いような…