実はこの12月14日にお送りした童話「私の猫 カモフラージュ」の翻訳者から「あの童話は、著者の実体験が反映しているというよりも創作の要素が強いでしょう。彼女の父親は、ケンブリッジ大学の教授であり、彼女自身もケンブリッジを卒業しています」という連絡が入りました。「ほう、そうですか」と頷くのみですが、それを、聞いても、別に<私があの童話を面白いと思った、観点>は微塵も揺らぎません。むしろ、創作であの主人公を作り出し、その周辺の人々(特にお母さん)の描写をしたのなら、ますます著者を尊敬します。ただ、翻訳者によると、この童話は著者のほかの作品に比べると地味で、増刷の回数が少ないからか(?) 本屋で、手に入らないケースが多くてそれは、残念だそうです。
その地味だというポイントですが、もう一度、お母さんに戻ると、お母さんは引越し後の転校先として、<大学へは進学の出来ないコースである>、モダーンスクールを選びます。その理由を主人公が『お母さんは、きっと、グラマースクール<そちらに進学すると将来大学まで進むことができる>の校長(お母さんは一時期お父さんと別居したので、そこに務めている)と、けんかをしたからよ』などと想像するのですが、そこら辺りがとても、厳しく、しかも地味だと読者が、感じるところでしょう。と言うのも日本人には、欧州の学校制度が、きちんとは、理解をされていないからです。
~~~~~~~~~~
日本では、建前としては、・・・・・誰でも、どんな学校でも選べることになっていて、・・・・・誰でも出世の手がかりとなり、より上位のカーストへ、上がる事のできる大学へ進学できることになっています。しかし、現実には、居住している地域の問題やら、親の経済力、等で、実際には、差が出てきています。
それでも、その現実を直視しえない家庭で、問題が頻発します。少年が事件を起こすときに、その影には、中学、高校時代、お尻を引っぱたいて、よい進学先へ進ませようと、躍起になる、教育ママが存在しています。西鉄バスハイジャック事件もそうでしたし、酒鬼薔薇聖斗事件も、最近の秋葉原通り魔事件(これは、大人なので、親は出てきませんが、中学時代から、高校にかけて、勉強が出来たと評判だったそうで)、同じ種類の両親だと思います。母親だけがママゴンでも、それを、見逃す父親がいるわけで、両親そろっての責任です。
日本の学校制度とは、その種のネガティヴなプレッシャーを親子双方に与えていますが、方で、まあ、最新の制度といえば、いえるので、欧州の文学に触れたときに、ちょっとした違和感を持つことがあります。
~~~~~~~~~~
今日のタイトルとなっている、本は、私が結婚後、新たに読了した小説のうち、最も感銘を与えられた本ですが、これも最初のうちは、『あれ、感じが悪いなあ。だけど、書評がよいから我慢をして読もう』と思ったポイントがあって、それがドイツにおける実質的なカーストの問題でした。
主人公は今では、法史学者となっている中年の男性で、かれが15歳のギムナジウム(これもドイツのエリートコース)の生徒だったときに、三十六歳の市電の運転手だった女性と偶然の機会に結ばれることの回想から始まります。小説はとてもよい構成になっていて、彼が重症の黄疸にかかり、道路で吐いてしまったときに助けてくれた女性が、ハンナでした。この奇跡的な偶然が、普通なら、出遭わないであろう、階層の違う二人を引き合わせます。そして、ハンナと言う、文盲である女性の、個人史にドイツの現代史(特にナチズムの残渣・・・・・日本で言えば、ハンナはBC級戦犯に当たることになるのだろうか?)が重ねあわされ、非常に重厚な構成を持ち始めます。
でも、文体は繊細で優しく、私は逗子のアトリエから上野の美術館へ行こうと思っている車中でほとんどを、読み終わり、新橋で、横須賀線から乗り換えようとして、一駅だけ乗ったのですが、その1,2分の間に、クライマックスが来てしまい、滂沱と涙が溢れ、『これでは、電車に乗っていられないわね』と考えて、一応、有楽町で京浜東北線を降りたのです。
その場所は、階段のそばでした。私は階段を構成している壁の傍にしゃがみこみ、誰からもみとがめられないようにして、ぽろぽろっと涙を流し続けました。その涙の粒の大きかったこと。70センチの落差で、落ちるのに、1.5センチ以上の黒い円を描くのですよ。私はその時に既に60歳に近く、『見るべきほどのことは、見つ(はたす)』と言う感じで、すれっからしに近いと、自分では自覚をしていたのに、まったく、少女のように泣かされてしまいました。
今、それが、どこだったのだろうと、本の頁を、めくり返しておりますが、多分、190頁以降でしょう。ともかく、今、再読している時間がありませんが、著者は、ベルンハルト・シュミッツで、私の本は新潮社から出ていますが、今はどういう形で手に入るかは知りません。
ううーん、今は落ち着いて読書をしている時間さえない。でも、四十代から、五十六歳まで、ほとんどの時間を家事と読書に費やして、一日に一冊は読んだのは、今でも心の財産には、なっています。
2008年12月20日 雨宮舜(川崎 千恵子)
その地味だというポイントですが、もう一度、お母さんに戻ると、お母さんは引越し後の転校先として、<大学へは進学の出来ないコースである>、モダーンスクールを選びます。その理由を主人公が『お母さんは、きっと、グラマースクール<そちらに進学すると将来大学まで進むことができる>の校長(お母さんは一時期お父さんと別居したので、そこに務めている)と、けんかをしたからよ』などと想像するのですが、そこら辺りがとても、厳しく、しかも地味だと読者が、感じるところでしょう。と言うのも日本人には、欧州の学校制度が、きちんとは、理解をされていないからです。
~~~~~~~~~~
日本では、建前としては、・・・・・誰でも、どんな学校でも選べることになっていて、・・・・・誰でも出世の手がかりとなり、より上位のカーストへ、上がる事のできる大学へ進学できることになっています。しかし、現実には、居住している地域の問題やら、親の経済力、等で、実際には、差が出てきています。
それでも、その現実を直視しえない家庭で、問題が頻発します。少年が事件を起こすときに、その影には、中学、高校時代、お尻を引っぱたいて、よい進学先へ進ませようと、躍起になる、教育ママが存在しています。西鉄バスハイジャック事件もそうでしたし、酒鬼薔薇聖斗事件も、最近の秋葉原通り魔事件(これは、大人なので、親は出てきませんが、中学時代から、高校にかけて、勉強が出来たと評判だったそうで)、同じ種類の両親だと思います。母親だけがママゴンでも、それを、見逃す父親がいるわけで、両親そろっての責任です。
日本の学校制度とは、その種のネガティヴなプレッシャーを親子双方に与えていますが、方で、まあ、最新の制度といえば、いえるので、欧州の文学に触れたときに、ちょっとした違和感を持つことがあります。
~~~~~~~~~~
今日のタイトルとなっている、本は、私が結婚後、新たに読了した小説のうち、最も感銘を与えられた本ですが、これも最初のうちは、『あれ、感じが悪いなあ。だけど、書評がよいから我慢をして読もう』と思ったポイントがあって、それがドイツにおける実質的なカーストの問題でした。
主人公は今では、法史学者となっている中年の男性で、かれが15歳のギムナジウム(これもドイツのエリートコース)の生徒だったときに、三十六歳の市電の運転手だった女性と偶然の機会に結ばれることの回想から始まります。小説はとてもよい構成になっていて、彼が重症の黄疸にかかり、道路で吐いてしまったときに助けてくれた女性が、ハンナでした。この奇跡的な偶然が、普通なら、出遭わないであろう、階層の違う二人を引き合わせます。そして、ハンナと言う、文盲である女性の、個人史にドイツの現代史(特にナチズムの残渣・・・・・日本で言えば、ハンナはBC級戦犯に当たることになるのだろうか?)が重ねあわされ、非常に重厚な構成を持ち始めます。
でも、文体は繊細で優しく、私は逗子のアトリエから上野の美術館へ行こうと思っている車中でほとんどを、読み終わり、新橋で、横須賀線から乗り換えようとして、一駅だけ乗ったのですが、その1,2分の間に、クライマックスが来てしまい、滂沱と涙が溢れ、『これでは、電車に乗っていられないわね』と考えて、一応、有楽町で京浜東北線を降りたのです。
その場所は、階段のそばでした。私は階段を構成している壁の傍にしゃがみこみ、誰からもみとがめられないようにして、ぽろぽろっと涙を流し続けました。その涙の粒の大きかったこと。70センチの落差で、落ちるのに、1.5センチ以上の黒い円を描くのですよ。私はその時に既に60歳に近く、『見るべきほどのことは、見つ(はたす)』と言う感じで、すれっからしに近いと、自分では自覚をしていたのに、まったく、少女のように泣かされてしまいました。
今、それが、どこだったのだろうと、本の頁を、めくり返しておりますが、多分、190頁以降でしょう。ともかく、今、再読している時間がありませんが、著者は、ベルンハルト・シュミッツで、私の本は新潮社から出ていますが、今はどういう形で手に入るかは知りません。
ううーん、今は落ち着いて読書をしている時間さえない。でも、四十代から、五十六歳まで、ほとんどの時間を家事と読書に費やして、一日に一冊は読んだのは、今でも心の財産には、なっています。
2008年12月20日 雨宮舜(川崎 千恵子)











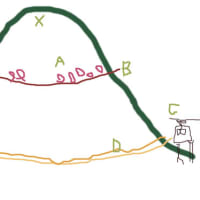





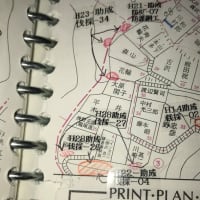







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます