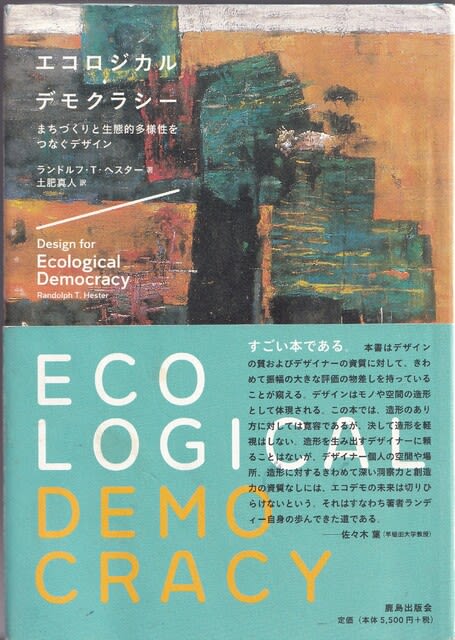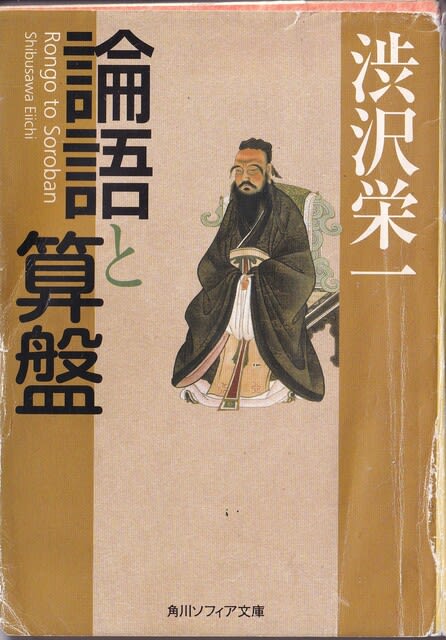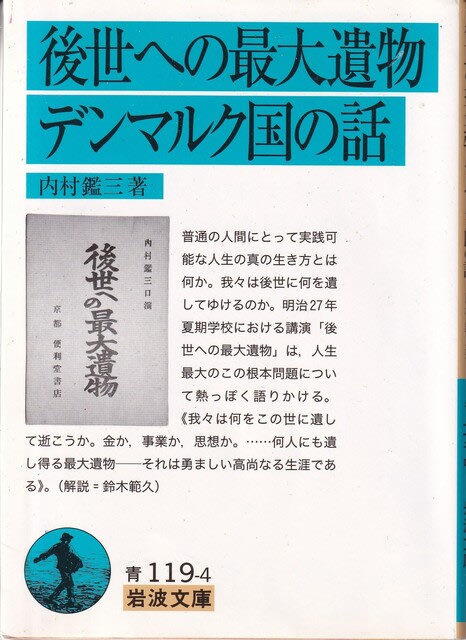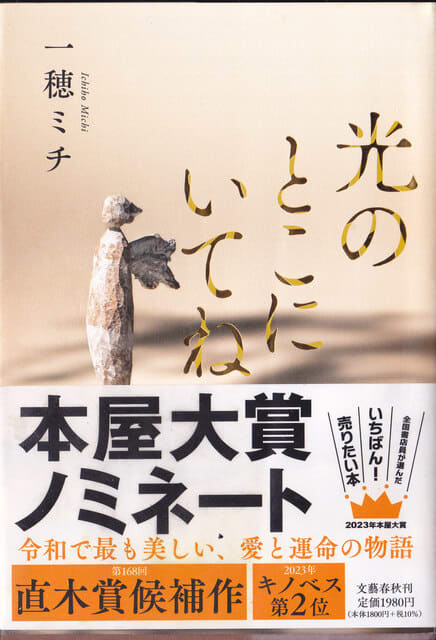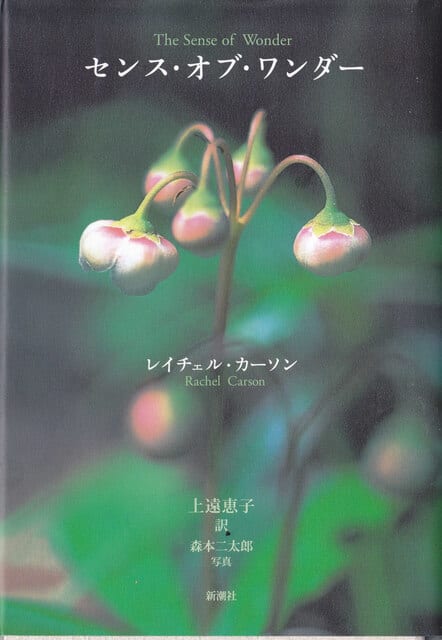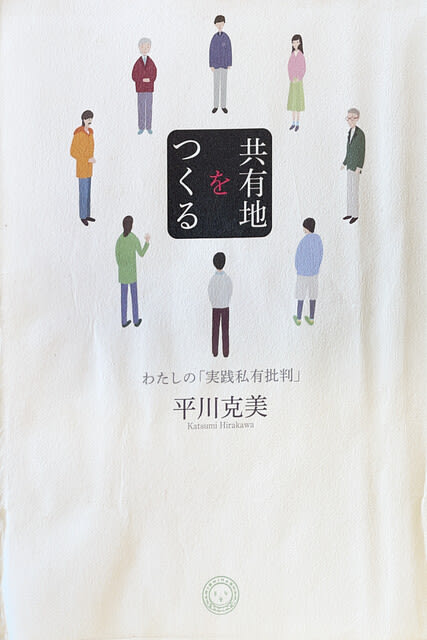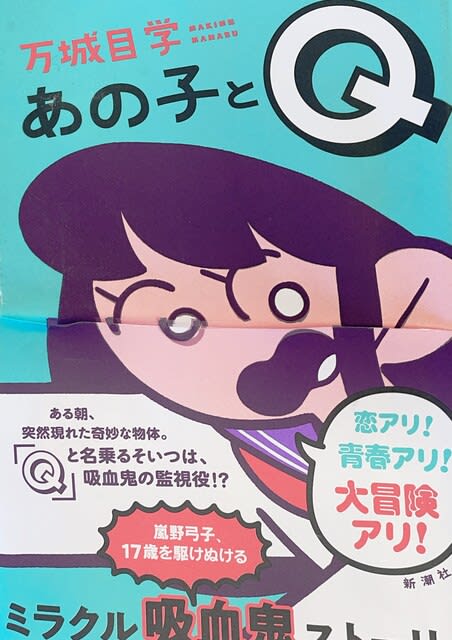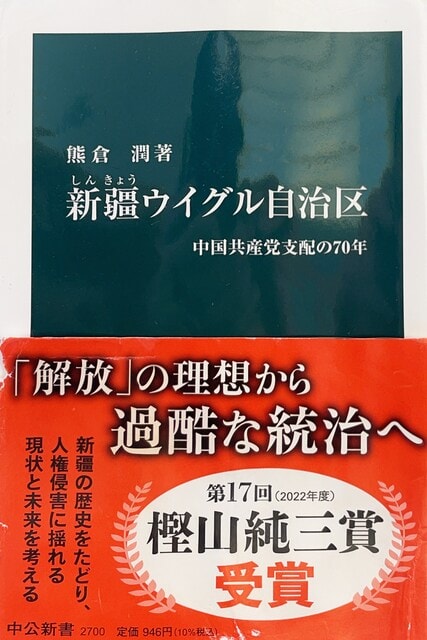地域にとっての 神聖さ 特別さ 糀谷八幡湿地保存会 田んぼの稲刈り
備忘録として
以下は
著書の中で具体的に記しておきたいもの(自分勝手なピックアップ)
・社交(交流=人が人と出逢う)が生まれるデザインを配置せよ。
社交が生まれる空間は内部への志向性と円形の特徴を持つ。
ベンチを並行しても、そこからは何も生まれない。
・まちの中のちょっとした角、こぶ、出っ張り、交差点が社交(交流)の場となることも
多い。
・コミュニティについて話し合う場合、半径7,5mのを超えない円の中ですべし。
そうでないとアイコンタクトが効かない。参加者から一体感が失せる。
・自ら不便さを選ぶことも、コミュニティの力を強めるためには許容されるべきだ。
・とっくに時代遅れになっている道路幅員、駐車場面積、低密度、分離する土地利用など
の厳格な基準がエコロジカルデモクラシーのためのデザインへの障壁になることも多い
(p71)
・エコロジカルデモクラシーの実現には、今までそれが違法とされてきた規則や基準を変える ことも必要になる。(p199)
ゾーニング、セットバック、建築基準なども一律の適用でなく、土地にあった変更をすべき
・自らそこに住むことをしない不動産投機家はすべてを破壊する
・半径400mの区域内には5000~6000人が住むべきである。(都市の密度)
・密度を達成すれば、高さへのボーナス、公共交通利用へのインセンティブ、減免をする
などの特典を付けるもあり。
・開発にあたっては、公園、駐車場、広域生活道路などが義務付けられるが、
この要件が 密度を低くし、公共交通を成立しなくし、ダメにしている場合もある。
ボンエルフ、クルドサック(袋小路)X交差点を活用する(p227)
・道や駐車場は町の半分の面積を占める。
あえて道を狭めて家や農地を増やすことも検討すべき(p236)
・生態系も断片化してはダメ、つなげること。オープンスペース債権の活用も。
これはオープンスペースを設ける資金調達のための市債発行のことか!?
・ロサンゼルスでは、近隣地区に高速道路が通る計画を阻止し、
クルマを通り抜けさせない障害物や装置を付けた。
・東京では平均気温が2、9度上昇、これは地球全体の5倍のペース。
それを抑制するため、1000m2以上の敷地の建物は屋上緑化を義務化した。
・シカゴでは面積の半分以上が屋根か道路である。そこで屋根と道の緑化をした。(p290)
・オープンスペースを設ける場合、その中に隠れる場を組み込むとよい。
・富、技術、過度の専門化、専門家への依存、グローバリゼーション、農作業の消滅、
標準化、移動社会への変化が、私たち自身が都市を考えることを疎遠にさせてしまった。
・永橋為介「間違った情報を持つ善良な人は、間違った人である。」
・都市農園をそこここに配置し、食を育む場をつくるべし。
何かを発見し、何かを教育し、何かを研究する機会をつくって、何かを耕す場をつくる。
そして、時々論争を呼ぶ体験をさせる。そんなランドスケープをつくるべし。
・4歳の妹「もしも世界がもっとゆっくり動いていたら、いつもお休みの日みたいなのにね ぇ。」
ーーーではもっと速く動いていたら?ーーー
・6歳のお姉さん「世界は気を失っちゃうわ。」
・速度が人を殺す。速度が都市を支配してきた。
アンダンテ(歩くような速さで)やアダージョ(ゆっくりと)が必要。
・街に走る車の量を2割減らすと、喘息発作の救急が41,6%減った。
・歩くためのマチづくりへ
土地利用とゾーニングの変更(駐車場と車道からオープンスペースと駐輪場へ転換を)
オープンスペースにつながる遊歩道は、より多くの人が行きかう道から優先的に。
クルマの速度を抑えよ(道を狭くし、緑地帯や樹木を植える)
・X交差点を設け、クルドサック、一方通行、バンプ、ボンエルフを活用、
行き止まりにしたりして、歩く人のためのマチをつくれ。
自転車道と歩道は別々に作るよりは、同じ空間に備えた方がよい(p423)
ベビーカー、障害者にももちろん配慮
距離を示す表示板を掲げたり、ウォーキングクラブを結成したりする。
・私たちの課題は、再び自然とつながり、壊れかけたコミュニティを新たに形成すること。
以上、自分が気になったことの列挙でした。
桜の季節が終わると、木々の新緑の出番だ
以下は、著書の構成に合わせた、まとめ です。
・私たちは、いつのまにか支えあい助け合える「コミュニティの力」を衰退させてしまった。便利だがバラバラで孤立した無責任な社会、助け合う力を持てない社会になってしまった。
いま、その状況を打破し、コミュニティの力を復活、再生する鍵を握るのが、エコロジカルな(広義の生態系=人と人、人と自然、生物たちとのつながり を考慮した)直接参加型の民主主義(デモクラシー)によるマチづくりである。
エコロジカルデモクラシーを進めることが、支えあい助け合える「コミュニティの力」を呼び起こす。
都市は従来とは異なった方法、つまり、エコロジーに十分考慮した市民参加型で作るべし。
と同時に、都市の作られ方、ランドスケープ次第で、人々の参加や社交も影響を受ける。
つまり、都市の形態が、エコロジカルデモクラシーの成否を決める一面もある。
それほど、マチづくり(デザイン)は力を持つものなのだ。
そこで、都市をデザインするにあたっては、
A.エコロジカルデモクラシーをもっと可能にするデザインを。
B.エコロジカルデモクラシーをもっと回復し持続可能にするデザインを。
C.エコロジカルデモクラシーをもっと推進するデザインを。
追求していくべきである。
そのために①から⑮までの指針を留意する必要がある。
A.エコロジカルデモクラシーをもっと可能にするデザインを
隣人とつながる場をつくろう!(お金がなくてもより長く、不必要な技術に頼らなくても)
①センターを強める。分散はダメ
徒歩で行けるように、半径400mの範囲に1つくらいセンターはあってよい。場所もそうだが、経験を共有することが大事。それがシビックプライドを高める。椅子やベンチの置き方一つでも、社会性を高められる。円形が特徴。半径7,5mを超えない円内に設定する。イベント準備もセンターでやれば人が興味持って助けてくれる。
所沢駅前の車両工場跡地開発に対しては、青年会議者がセントラルパークづくりを提言したことがあった。市の土地ではないので難しかったが、それも一つのセンターづくり、オープンスペースづくりなんだろう。もちろん商業施設もセンターである。この4月、商業施設に出店する具体のお店も決まったようだ。活動できる広場も入る。建物は駅から出たら「森のように見える」ようなものにと市は要望してきた。果たしてどうなるか。
新所沢パルコと小手指西友の撤退は、センターづくりの失敗である。市は駅を中心に(センターとして)徒歩や公共交通で集まることを考えていたが、スーパーマーケットは各地にできて、分散、拡張しすぎてしまい、センターが失われた。ただ、各地の出店を阻止することは既存の法律ではできなかった。
三ヶ島地区では、各区の神社がセンターであろう。村の鎮守はそういう役目を果たしてきた。
(私の感想)
②つながりを意識し、多くの人とつながる。
広い道路はまちと人々を分断する。排水路も暗渠化でダメになる。
食べ物も都市内で生産する。野生生物の棲み家も配慮。つなげる、あえて藪をつくる。
コミュニティガーデンも有効。対立した時は、パワーマップを作ってみるとよい。(金の動き、だれが得するのか?)
確かに463バイパスで商店街は分断し、地域も分かれた。広い道路は川と同じ。横断歩道は橋と同じ。マチづくり協議会や自治会の行うイベント、清掃活動、古紙回収などすべてこれ。学校農園を用意したり、学校ビオトープも市民農園も。もし鎖国したら農村は一気に見直される。都市を養うのは農村だけ。
まちなかみどり保全制度もセンターづくり。
③公正に
市民参画が進むと公正さが焦点に。情報への平等なアクセス権を。誰もが近くで利用でき、排除されないこと。(値段、距離)
広場や公園などは排除されないが、ディズニーランドはお金がないとは入れない。
④賢明な地位の追求
隣の芝生をうらやむところから発してはダメ。身の程知らずの承認欲求は道を誤る。自分たちのマチの特長をのばそう。概して、異種混交がよく、泥、汚さが面白い。焦点を当て「見える化」して価値を高めよう。
流山や越ケ谷と人口増の観点だけで比較したり、横浜と同じような観光地化を求めたり、それらは不賢明な地位の追求だと想起した。調整区域の下水道を求める声も、実際には(下水が入ったのに)浄化槽のままのお宅もある。真に望んでいるわけではないが、市街化区域との比較だけで望まれている場合があるのではないか・・・。
⑤聖性を持つように
スピリット、神話、物語、聖なる場所を地図に落とそう。そのマチ独自の聖性がみんなの知るところとなれば、今度はそれがコミュニティを強くしてくれる。
松井地区や小手指地区や山口地区が、地元の文化財を顕彰して、地図化したり道標を立てたり冊子や広報誌にしたりするのも聖性化だ。柳瀬では新たに「滝の城」が、歴史発掘から特別さの演出がされるようになった。滝の城まつりである。
B.エコロジカルデモクラシーをもっと回復し持続できるデザインを。
⑥特別さの発見、演出、創造
地形と水循環により「流域」ができている。また、その土地ならではの文化や特色がある。手と足を使い、瞑想(心で感じ取って)して、デザインを。きっとそれは廃棄物、消費エネルギー、再生不能エネルギーに依存しない安価で持続可能な都市となる。
里山保全に加えて水田保全を合わせたのはこれか。富岡地区の活動においては、ウォークラリーがその役目を演じているかも。
⑦選択的多様性
生物多様性と文化的多様性がある方がよい(野放図ではいけないが)。
野生生物の棲み家も、文化の維持も企図せよ。時にはアクセスしにくくし、保全する。
⑧密度と小ささこそ鍵
密度がないとセンターもできない。1haあたり30~37戸ないとだめ。スーパーマーケットも多すぎては自滅する。抑える。1haあたり17戸だったのを40戸にすると公共交通の利用はぐんと増える。
少なくとも路線バスには25戸、路面電車には34戸が必要。クルマこそ低密度の共犯者。
密度を増やすことでスペースをつくり、緑をつくり、センターを維持する。
パルコや西友の撤退の原因の一つに、(ネット販売の利用やロピアの進出などもあげられるが)
新所沢小手指地域のスパーマーケットの多さもきっとあげられる。
あっという間にたくさん出店されてしまった。本当はそれほどなくても十分なのにと思っていた。
企業は企業で商圏制圧のために無理をする。コンビニの前にコンビニが建ち、山田うどんの向かいに山田うどんができたのも、他店の出店を抑えるためのものだ。消費者とは違うレベルでの戦いがある。
企業は撤退できるが、消費者は取り残される。都市計画の出番はこんなところにもあるのだと思う。
(ちなみに遅ればせながら葬祭センターの進出は都市計画によって一定の制限は課しましたが・・・)
⑨都市の範囲を区切る(限定する)
都市と農村(森林)を区別すべし。都市と都市は農村や森林で分けるべし。近隣地区同士でも30m~400mくらいグリーンベルトが欲しい。都市は大きくなりすぎてもコミュニティがダメになる。
人口は25万人以下、できれば10万人以下がよい。顔見知り、声の届く範囲というのはあるもので、
プラトンは5040人が市民参加できる限界とみた。
これがかの前明石市長が所沢を狙ったポイントであった。政治に関心はあるが地元のことはあまり知らない、顔の見えない、コミュニティに根付いていない一定の人々の層が存在することだ。
10万都市でもなく(みんな顔見知りで付け入るスキがない)50万都市でもなく(大きすぎて手に負えない)、30万都市がねらい目だ、と指摘していた。
⑩多くの用途に使える設計をせよ
多くの用途に使える、その最たるものは「空」である。オープンスペースは強い。
建物の場合は「構造」こそ大切。
何を大切に肝腎とするか、都市の「フレームワーク」を決めたら、それに権限を与えよ。
普段の法を抑えてでも。
航空公園の魅力は「空」にある。
「東町を考える会」の主たるフレームワークは、「今住んでいる人が健全に住み続けられること」にある。 道路を通し、道幅を広げることは、マンション建設を許し、24時間日陰住まいの人を増やすことにつながってしまう。既存の規定の道路幅員、基準でいったら阻止できない。だから、みんなで考えて合意をつくろうとしている。市としても道路をかぎ型に通した際には、普段は車を侵入させないようにした。それは都市計画職員の大殊勲だ。 他方、消防車がゆとりで消火活動できる幅を求めることは、主ではなく「従」なるフレームワークだと思うのだが。
「こぶし団地を考える会」の趣旨も然り。既存の法を当てはめているだけでは達成できない。だから、市が乗り出して応援を始めたのだ。
C.エコロジカルデモクラシーをもっと推進するデザインを!
(まちが人々の心に触れるようにしなさい)
⑪未来の都市像は日常の中にある
排除、分離、禁止するのではなく、みんなできるようにしたい。
もつれたとデザインの話し合いのもつれも、よく調べ、聴き、観察し、共感するだけでなく、ともに懐古し、歴史を刻み、昇華させないと人々はその変化を受け入れようとはしない。
航空公園では、犬の散歩もスケボーの練習も子どもの遊びもお年寄りの散歩も求められていた。
犬はドッグランで何とかしたが、スケボーはうまく同居させてやれなかった。
県議時代の苦い思い出である。
⑫自然に生きる
自然は人間を健康にし、長生きさせてくれる。人はなぜ草原ででんぐり返ししてしまうのか、なぜ雪を見ると幸宥だるまをつくってしまうのか、なぜ砂浜に出あうと人をうずめてみたくなるのか、夕立ちの後の水たまりをなぜ人は飛び跳ねたくなってしまうのだろうか。
これが私がずっと求めてきた自然との共生だ。自然は私たちを癒し、元気にしてくれる。
思索を成就させてくれる。こども時代に自然の中で経験したことは、大きくなってからも生きている。野生生物も含めて共に生きるようにしていきたい。教育委員の清水国明さんが、「人間は自然の中で何クソっと生きていく力をたくさん持っているが、それを使わないでいられることでストレスを感じてしまう。
自然の中で生きていくと、細胞がありがとうって言って、疲れても喜んでいる」と言われたことはとても印象深い。
⑬科学を使うこと
生態学は自然ばかりを相手にしてきたが、これからは都市の生態学が必要だ。
長く住まうことで得られる土地の知恵、科学による生態系への理解を一緒にして、人々がともに考え、汗して、参加していこう。
学者や知識ある人が加わって、活動を進めている。
例えば中心市街地周辺グランドデザイン、プレイスメイキング、環境保全団体の各種活動。
自分は菩提樹池のかいぼり作業で、池の真ん中の日向には全く生き物がいないことを知った。
水温が上がりすぎで住めないのだ。言われてみてはそうなのだが、日が当たるとはそういうことなのか。
⑭お互い奉仕すること
海外では、裏庭の使い方から始まり、空き地やか各家をつなげ、野性生物の回廊を育てていることも多い。奉仕の心だけが利己主義、商業主義に打ち勝てる。
選挙での公約「オオムラサキの回廊」がそれだったんだけどなぁ・・・
奉仕(献身的な活動)は、地域のあちこちで行われている。街路樹や公園清掃などもそうなればいいなぁ。
⑮歩くこと(そのゆったりとしたペースを取り戻すこと)
都市デザインはスペースだけを相手にしてきたが、ペースも考えるべき。速度は都市の魅力の1つだが、制御されないそれは急かし、競争させ、浅はかにし、短期にして無謀にさせる。歩く旅は自己変革を導く。地面のデザインがペースをコントロールする。
直線にするか、曲げるか、狭めるか、広くするか、土で行くか草むらかアスファルトか、これらでペースは変わってくる。市のトコトコ健幸マイレージも、まさに地についてきた。ウォーキングコースも設定され、道標も進められ、ベンチも遊歩道も進行中だ。木かげづくりも樹冠を広げる剪定を心がけている。
京都にある「哲学の道」がアスファルトになってしまったらきっと意味をなさないんだと思う。