
 読書「庭仕事の愉しみ」ヘルマン・ヘッセ
読書「庭仕事の愉しみ」ヘルマン・ヘッセ
岡田朝雄訳 草思社文庫 2011年発行
麦わら帽子をかぶり、農作業服をまとい、背中にはカゴを背負ったヘッセの写真がある。詩人・文豪として知られたヘッセは50才を過ぎて自分の家と庭を持ち、庭いじりに没頭するようになり、それは85才で亡くなるまで続いた。
花木を育て、野菜など植え、庭仕事を日がな一日続ける日々が続いた。だが、いわゆる農夫ではなく、庭仕事をしながら哲学し瞑想したのであった。ゆったりとした暮らしがそこにある。
特に木に対する愛着が大きかった。林や森に対してはもちろんのこと、一本独立して立つ木には、孤独な人間と同じようだといって尊敬の念を抱いた。木は神聖なもの、木と話をし、傾聴することのできる人は真理を体得すると。
ヘッセは老化と共に眼や頭の痛みが酷くなるようになり、長時間の読書や著述ができなくなった。そのために心理的な気分転換が必要で庭仕事や炭焼き(焚き火)に身を入れ、同時に瞑想や想像の世界に浸り気持ちの集中を図ったという。
ヘッセによれば、世俗の国家、王朝や国民は滅亡し、明日にはもう存在しなくなることもあるが、結局、花たちが何千年も変わることなく、年ごとに草原に回帰することは反論の余地がないように、現代史の騒乱とはかかわりのない秩序がこの世に存在するのだ、そういう自然との交わりの中に身をおくこと(庭仕事)、その大きな秩序の中で絶対的な平安を得たという。
ヘッセの老年になってからの著作「人は成熟するにつれて若くなる」も、孤独な散歩者ヘッセの老年哲学を著したものだ。
そのなかで、「神の大きな庭の中で私たちはよろこんで花咲き、咲き終わろう」という文章がある。ヘッセの庭は神から与えられた庭であり、そこでの庭仕事は彼にとってやり遂げなければならなかったもう一つの仕事であったことであろう、
そして彼もまた咲き終わった、しかし、彼を思い起こし、その思想にふれ共に瞑想するものにとって、ヘッセはいつまでも共に寄り添ってくれる友人である。















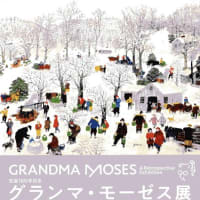




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます