 ことしもいつの間にやら終わりつつあります
ことしもいつの間にやら終わりつつあります
12月4日の朝日新聞朝刊「福島 広がる格差」を読んでいました、
原発事故以来の4回目の避難住民聞き取り調査の結果についてです
戻りたい人は初の半数割れであった(45%)、生計のめどが立たない
人が42%、原発の中間貯蔵施設を8割の人が理解を示すが一体
中間貯蔵施設とはいつまでのことかとあきれる、かつ最終処分場が
いつまでも検討されていないことに不信感、復興五輪の良い影響があ
ると思う人は14%しかない、などなどです
こんな状態で一方でやたらと予算を誘い込みコンクリート工事の増強
に浮かれる五輪推進者たち、原発再稼働をもくろむ政府、故郷に帰る
期待はほとんどなくなってしまっている現状、・・・・
これで今年も暮れてゆきます
ところでうちの庭にこの冬になってモグラがやけにうごいているのを
発見しました、普段は動きを見せないモグラ、春になって動くのは分か
りますが、なぜこんな寒い冬に土を盛り上げてモグラ塚をこしらえ動き
回っているのでしょうか、何か気になります
今年も大勢の皆さんにご訪問いただきありがとうございました
また、新年にブログ再開したいと思います










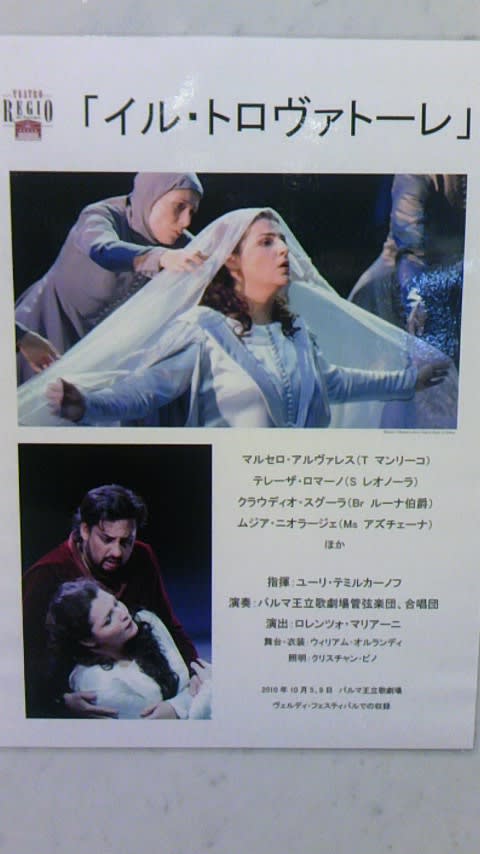

 船橋市の東武百貨店で猫写真家である岩合光昭さんの展覧会
船橋市の東武百貨店で猫写真家である岩合光昭さんの展覧会








 朝日新聞12月2日の朝刊で、「高齢者住宅の父、今は幸せ」という
朝日新聞12月2日の朝刊で、「高齢者住宅の父、今は幸せ」という