デカルトRené Descartesは確実に真verumであるといえることから哲学を開始しなければならなかったので,とりあえずはすべての事柄についてそれを疑うという方法論的懐疑doute méthodiqueを実行しました。そのようにして最終的に得た結論が,すべてのものを疑っている自分の精神mensは確実に存在するということでした。そのことが「我思うゆえに我ありcogito, ergo sum」というテーゼに示されています。スピノザは『デカルトの哲学原理Renati des Cartes principiorum philosophiae pars Ⅰ,et Ⅱ, more geometrico demonstratae』の中で,したがってこのテーゼは三段論法,思うということはあることとであるという前提があり,我は思っているから我はあるという三段論法なのではなくて,単一命題である,我は思いつつあるという意味の単一命題なのであると指摘しました。

スピノザは真理veritasの規範は真理それ自身にあると考えましたから,方法論的懐疑はまったく必要としませんでした。ただこの単一命題のうち,我思うということ,つまり私が思うということは,無条件に前提しています。第二部公理二にはそのような意味が含まれていると解せるからです。
「人間は思惟する(Homo cogitat)〈,あるいは他面から言えば,我々は我々が思惟することを知る〉。」
この公理Axiomaの,あるいはより以降の部分は遺稿集のオランダ語版De Nagelate Schriftenから補われたものですから,この公理は単純に僕たちは思惟するということをいっています。僕たちが思惟するということを僕たちは知っているということは,観念ideaと観念の観念idea ideaeの関係で説明することができますが,この公理が真であることを知っているというほどの意味に解しても問題ないでしょう。
思うということは思惟作用のひとつです。つまり我々は思惟するということのうちには,我々は思うということが含まれています。そしてスピノザはこれを公理として,つまり証明する必要がないこととして示しています。つまりスピノザにとって,僕たちが思うということ,あるいは思惟している僕たちの精神があるということは,方法論的懐疑のような論証Demonstratioを経ずとも成立する事柄だったのです。
ここまでをまとめると次のようになります。
まず,人間の精神mens humanaの現実的有actuale esseを構成する観念ideaが,現実的に存在する物体corpusの観念でなければならないということを僕たちは知ります。ではそれがどのような物体であるのかということを検討すると,その精神の観念対象ideatumとなっている物体である,身体corpusの観念であると結論されます。この検証過程は第二部定理一三証明の内容そのものですから,ここでは割愛します。そしてそのことによって,僕たちは僕たちが感じている通りに僕たちの身体が存在するということを知るようになるのです。この順序からは,スピノザは人間の身体あるいは自分の身体というものが,ほかの諸々の物体から切断されて独立したものであるという考え方についてはこれを排除しているのであって,むしろ諸々の物体の一部として僕たちの身体が存在するというように考えていることが明確に理解できると思います。
なお,前もっていっておいたように,人間の身体humanum corpusといういい方は,スピノザがそういういい方をしないというわけではありませんが,むしろデカルトRené Descartesが好んで用いるいい方です。また,スピノザの哲学において自分自身といわれるならそれは自分の精神というのと同じ意味なのであって,自分の身体のことを自分自身とはスピノザはいいません。というか,スピノザは人間の身体といういい方はしますが,自分の身体といういい方自体をしません。このことが,スピノザは人間の身体というのを物体の一部とみなしていることおよびデカルトは人間の身体を他の物体から独立したものとみなしていることと,一定の関係を有しているとみることもできるでしょう。
このスピノザの考え方は,さらに第二部公理四からなお明らかになっているといえます。この公理Axiomaでは,僕たちは物体が多様の仕方で刺激されるafficiのを感じるということをいっています。ここでいわれている物体というのは,身体のことであり,とくに自分の身体であるということはいうまでもありません。だから岩波文庫版の訳者である畠中尚志は,この部分に身体という訳注を付しているのです。そもそも僕たちが刺激されると感じる物体は,僕たちの身体のほかにはあり得ません。

スピノザは真理veritasの規範は真理それ自身にあると考えましたから,方法論的懐疑はまったく必要としませんでした。ただこの単一命題のうち,我思うということ,つまり私が思うということは,無条件に前提しています。第二部公理二にはそのような意味が含まれていると解せるからです。
「人間は思惟する(Homo cogitat)〈,あるいは他面から言えば,我々は我々が思惟することを知る〉。」
この公理Axiomaの,あるいはより以降の部分は遺稿集のオランダ語版De Nagelate Schriftenから補われたものですから,この公理は単純に僕たちは思惟するということをいっています。僕たちが思惟するということを僕たちは知っているということは,観念ideaと観念の観念idea ideaeの関係で説明することができますが,この公理が真であることを知っているというほどの意味に解しても問題ないでしょう。
思うということは思惟作用のひとつです。つまり我々は思惟するということのうちには,我々は思うということが含まれています。そしてスピノザはこれを公理として,つまり証明する必要がないこととして示しています。つまりスピノザにとって,僕たちが思うということ,あるいは思惟している僕たちの精神があるということは,方法論的懐疑のような論証Demonstratioを経ずとも成立する事柄だったのです。
ここまでをまとめると次のようになります。
まず,人間の精神mens humanaの現実的有actuale esseを構成する観念ideaが,現実的に存在する物体corpusの観念でなければならないということを僕たちは知ります。ではそれがどのような物体であるのかということを検討すると,その精神の観念対象ideatumとなっている物体である,身体corpusの観念であると結論されます。この検証過程は第二部定理一三証明の内容そのものですから,ここでは割愛します。そしてそのことによって,僕たちは僕たちが感じている通りに僕たちの身体が存在するということを知るようになるのです。この順序からは,スピノザは人間の身体あるいは自分の身体というものが,ほかの諸々の物体から切断されて独立したものであるという考え方についてはこれを排除しているのであって,むしろ諸々の物体の一部として僕たちの身体が存在するというように考えていることが明確に理解できると思います。
なお,前もっていっておいたように,人間の身体humanum corpusといういい方は,スピノザがそういういい方をしないというわけではありませんが,むしろデカルトRené Descartesが好んで用いるいい方です。また,スピノザの哲学において自分自身といわれるならそれは自分の精神というのと同じ意味なのであって,自分の身体のことを自分自身とはスピノザはいいません。というか,スピノザは人間の身体といういい方はしますが,自分の身体といういい方自体をしません。このことが,スピノザは人間の身体というのを物体の一部とみなしていることおよびデカルトは人間の身体を他の物体から独立したものとみなしていることと,一定の関係を有しているとみることもできるでしょう。
このスピノザの考え方は,さらに第二部公理四からなお明らかになっているといえます。この公理Axiomaでは,僕たちは物体が多様の仕方で刺激されるafficiのを感じるということをいっています。ここでいわれている物体というのは,身体のことであり,とくに自分の身体であるということはいうまでもありません。だから岩波文庫版の訳者である畠中尚志は,この部分に身体という訳注を付しているのです。そもそも僕たちが刺激されると感じる物体は,僕たちの身体のほかにはあり得ません。










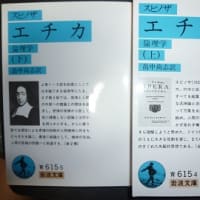



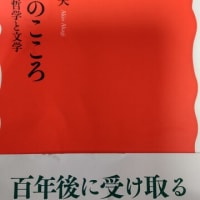

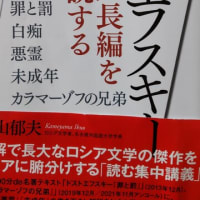





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます