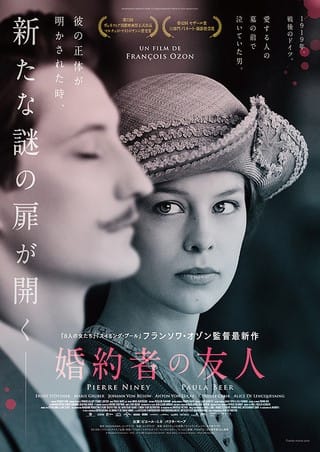・ いまタイムリーなテーマの法廷劇。

米国歴史学者デボラ・E・リプシュタット(レイチェル・ワイズ)が、<ホロコースト否定論>の英国歴史家デイヴィッド・アーヴィング(ティモシー・スポール)に名誉棄損で提訴される。
受けて立つことを決意したリプシュタットは、渡英し<ホロコースト否定論>を覆すため弁護団を組織する。裁判は00年1月王立裁判所で始まった。
5年間に渡って争われた実話をもとにドラマ化された地味ながらスリリングな法廷劇で、歴史修正のフェイクニュースが蔓延する今、タイムリーなテーマでもある。
監督は「ボディ・ガード」(92)でお馴染みのミック・ジャクソン。近年はドキュメント作品が多いという理由で起用された。
モデルであるD・リプシュタットの原作をデヴィッド・ヘアが脚本化。原題は「Denial」(否認)。
訴えられた側に立証責任がある英国の司法制度が現代にはそぐわないのでは?と思わせる。もし敗訴すれば<ホロコーストはなく収容所は消毒施設だった>というアーウィングの主張がまかり通ってしまう。
多額の基金を集め組織された大弁護団は、アーウィングの著作が事実の歪曲と偏見によるものだと地道に証明する手法を取った。
ストレートに発言しようと主張するリップシュタットや生存者の証言を抑えたのが事務弁護士のアンソニー・ジュリアス(アンドリュー・スコット)で、陪審員ではなく判事による公判に持ち込んだ。
法廷弁護士リチャード・ランプトン(トム・ウィルキンソン)はアーヴィングが事実からかけ離れている差別主義者の思い込みであり、ユダヤ人を忌み嫌う感情論に偏っていないかを地道に検証して行く。
近年日本を取り巻く近代史(太平洋戦争・南京事件・慰安婦問題など)がネットで騒がれ、様々なメディアを巻き込での論争があるが、事実の解明がこのようにされていけばと想わずにはいられない。
ヒラリー・スワンクに代わってヒロインに扮したR・ワイズは、チームを信じることの難しさ・素晴らしさを表情豊かに演じていた。
魅力的だったのはランプトン弁護士役のT・ウィルキンソン。決して感情を露わにすることなくコツコツと役割を果たし、優しい思いやりにも長けている。もう一人の主役ともいえる。
敵役のアーウィングを演じたT・スポールもああ言えばこう言うタイプのうるさ型を好演。
終盤、グレイ裁判長が「人が純粋に信じていることを嘘と断言してよいのか?」と問うシーンがあるが、なるほど相応しい人物像だ。
<歴史を否定する人と同じ土俵に立ってはいけない>という金言を改めて噛みしめるドラマだった。