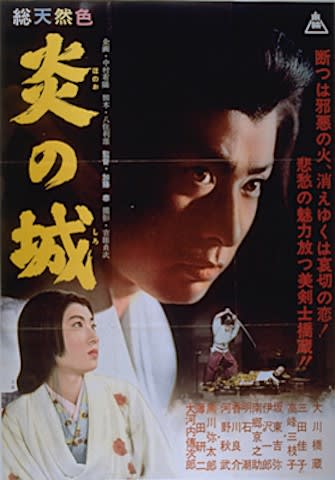・ 製作裏話に映画作りへの魂を観た!
国鉄が<安全な超特急が謳い文句>の新幹線を爆破するというパニック・映画を作ろうとしたのは、衰退が見え始めた実録路線からの脱却を狙っていた東映・岡田社長の肝いりでスタートした。
加藤阿礼の原案を佐藤純也が監督・共同脚本化、高倉健・千葉真一・宇津井健を始め山本圭・志村喬・丹波哲郎・永井智雄・渡辺文雄など多彩な顔ぶれが出演。
ある日東京駅発ひかり109号に爆弾を仕掛けたという脅迫電話が掛かる。ATS(列車自動制御装置)・CTC(列車集中制御装置)による安全神話を覆すような時速80KM以下に速度を落とすと爆発するというもの。
誰も殺さずに巨額の身代金(500万ドル)を得ようとしたのは沖田(高倉健)という男で町の零細工業経営者。沖縄出身の集団就職青年大城(織田あきら)と過激波崩れの古賀(山本圭)が加わっていた。
国鉄の新幹線爆破をどう防ぐのか、乗客の安全をどう守るのか極限状態での焦りと緊張ぶり、警察の犯人逮捕を最優先した捜査、高度成長の時代に取り残された犯人たちの犯行にいたる背景などを描いた娯楽超大作だ。
いまなら鉄道会社のタイアップで全面協力のもと乗客安全のため奮闘する職員たちの美談で大ヒットする作品が想定されるが、映画としての迫力や魅力には乏しいのでは?
国鉄と東映は従来から良好な関係にあり、本作でも協力を得られるものと踏んでいた。国鉄もシナリオを見て「新幹線危機一髪」という題なら協力しても良いということだった。
ところが、岡田は頑として譲らない。映画屋としてのカンが働いたのだろう。国鉄の協力なしでも断固製作するという号令をかけた。
今なら許されないことだが、新幹線走行映像は盗み撮り、セットで本物そっくりの12両編成の新幹線を作り、ミニチュアで遠景を撮影したり、私鉄(西武)の協力を得たり、北海道の原野で本物の貨物列車を爆破したりアラユル知恵を絞っての挙行だったという。
あら探しをすれば切りがないほどの映像だが、その迫力は映画作りのエネルギーが画面を通し観客に迫ってくる。
主演した高倉健はシナリオを読んで、どんな役でもいいからとオファーして実現した。岡田は菅原文太を指示したが、新幹線が主役の映画だと拒否、当初宇津井健が演じた倉持運転司令長役だった高倉に回ってきたもの。
結果はW健がはまり役となったが、その分サスペンス・アクションのテンポが中だるみしたのは否めない。
紆余曲折のため封切り二日前に完成したという信じられない状況で宣伝もままならず、興業成績も振るわなかったが、その後犯人側のシーンを大幅カットしたフランス版が大ヒット。
さらに「スピード」(94)が参考にしたという話題もあって国内でもDVD化されるなど評判を呼び映画が再評価されている。
熱い男たちの映画は、今観ても面白い。