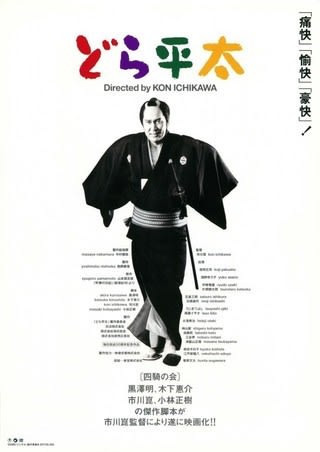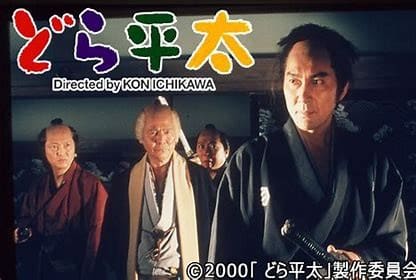・ 「松本サリン事件」、社会派・熊井啓監督の魂心作。

「帝銀事件 死刑囚」(64)で監督デビューした熊井啓。「忍川」(72) 「サンダカン八番娼館 望郷」(74)などの文芸作品から「黒部の太陽」(68) 「天平の甍」(80) などのエンタテインメント大作まで幅広い作品を手掛けているが、デビュー作や「日本の熱い日々 謀殺 下山事件」(81)など社会派イメージの印象が色濃い監督だ。
松本市育ちの熊井は94年6月27日に起きた<松本サリン事件>とはとても縁が深く、第一通報者の河野義行夫人の祖父と監督の母は旧長野高等女学校(現・長野西高校)の校長と教師の間柄で、何度か河野家に遊びに行ったことがあるそうだ。
20年経ってもこの事件は鮮明に記憶に残っている。TV・新聞などメディアによる連日の情報で、筆者を含め大多数の人は被害者である河野さんを容疑者だと思っていた。
情報はどのように作られ、どのように変化していったのか?しっかり検証したという記憶はなく、真犯人に誤解された河野さんおよびその家族は気の毒だったでは済まされない。
平石耕一の戯曲「NEWS NEWS」をもとに熊井自身が脚本化した「強引な警察の捜査手法と報道機関の過熱取材」がテーマで、事件の1年後高校生の取材に応えたローカルテレビ局TV信濃の報道部長・笹野(中井貴一)ら4人のスタッフが振り返るという内容。
TV局の笹野や3人の記者、神戸夫妻(寺尾聡・二木てるみ)、長野県警松本署の吉田警部(石橋蓮司)が、事件発生からそれぞれがどのような言動だったかを明らかにして行く。
警察発表に誘導されるようにマスコミがあたかも<青酸カリが大量殺人の原因であるような誤った初期報道>が致命的。それがサリンという聞きなれない毒物が原因と判明すると、あたかも簡単に作れる危険薬物であるかのような誤報が追い打ちとなってしまう。
「TV信濃」では誤報を避けるため<青酸カリによる大量殺人が可能か>裏付けを取ろうとするが、はっきりしないまま他局に先を越されてしまう。
その後毒ガスはサリンと判明、大学教授藤島(藤村俊二)の「サリンは薬品をバケツで混ぜ合わせて簡単に作れる」との証言を放送したが・・・。
さらに取材を進めるうち、古屋教授(岩崎加根子)から大がかりな装置と複雑な製法が必要であるとの情報を得て<後藤夫妻は被害者であるという裏付けのサリン特番>を放送すると大きな反響があった。
それは、皮肉にも視聴者からの抗議電話が殺到し、局内の反感を呼んでしまうという結果。被害者の後藤家には無言電話や石が投げられ完全に犯人扱いの村八分状態はエスカレートという予期せぬ反響となってしまった。
一途な高校生(遠野なぎ子)の感情には大人の事情は到底理解できない。民放局はスポンサーありきで、視聴率が何より大切であること。警察には検挙率が最優先で、取材記者には記者クラブという暗黙のルールがあることなどなど・・・。
熊井監督は、当初被害者を中心にした事件の真相解明ドラマを描いてみたがシックリ来ず、若い目で事件を見る発想に変えたという。
その分とても純粋な高校生から見たサリン事件は、TV局報道関係者4人それぞれの心情や、警察や報道機関から犯人扱いされた家族の過酷な心境が類型的に描かれるという突っ込みに中途半端な印象が付きまとってしまった。
それでも、限られた予算でこれだけのスタッフを揃え、愚直なまでに思いの丈を映像に遺した熊井監督に敬意を表したい。その後の大事件発生でもスピード競争ばかりが目立ち、同じような過ちが繰り返されている。マスコミへの信頼度は益々希薄になっているのが現状だから。
筆者にとって遺作となった「海は見ていた」(02)のほうが清廉な熊井監督らしくて、数段好きなのだが・・・。