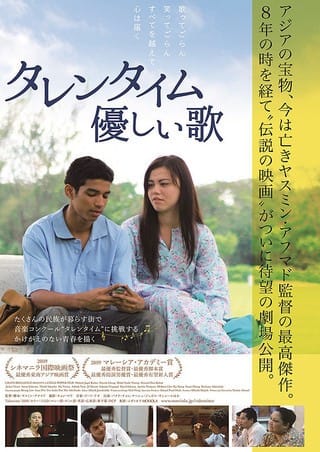・ 英国・炭鉱ものに外れなし!
1984年英国北東部炭鉱の街でボクシングを習っている11歳の少年・ビリーがバレエと出会い、名門ロイヤル・バレエ・スクールを受験することになるハートフル・ストーリー。
リー・ホールのオリジナル・シナリオを舞台出身のスティーブン・ダルドリーが監督。出演はジェイミー・ベル、サンドラ・ウィルキンソンなど。原題は「Billy Elliot」
長編映画監督デビューのS・ダルドリーは、英国北東部のナマリを持ちダンスが得意な少年という条件でオーディションしてJ・ベルを選んでいる。当時13歳だったが、少女に混じってバレエを懸命に踊る純粋さとUKロックの流れに乗ってタップを踏む姿は11歳の少年らしく不自然さはない。
一種のサクセス・ストーリーだが、家族の愛情物語でもある。英国は鉄の女サッチャー首相時代、20余りの炭鉱閉鎖を断行し炭鉱不況に陥っている。そんな時代を背景とした作品には「ブラス!」(96)、「フルモンティ」(97)などハート・ウォーミングな名画が誕生している。本作もそのひとつ。
母を亡くしたビリーは、炭鉱で働く父ジャッキー(ゲイリー・ルイス)と兄トニー(ジェイミー・ドラヴェン)がストライキ闘争中。そんなギスギスした家庭環境で認知症気味の祖母(ジーン・ヘイウッド)の面倒を見ながら苦手なボクシングのレッスンに通う。その練習場にバレエ教室が移ってきた。興味半分で観ているとウィルキンソン先生(ジュリー・ウォルターズ)に勧められ、少女に混じってレッスンを受けることに・・・。
過酷な暮らしだが、11歳の少年にとって踊ることで全てを忘れ夢中になれる。男はボクシングかサッカーをやるもんでバレエなんてとんでもないという父が、息子のためにスト破りをするシーンが中盤のハイライト。父と兄の諍いがあって無骨な父の想いがヒシヒシと伝わってくる。
中流家庭のウィルキンソン先生はビリーの素質を見抜き自費でロイヤル・バレエ・スクール受験をさせようとするが、父は自分の息子の面倒は自分でみると言い切る男気が潔い。ジャッキーを演じたG・ルイスの好演が光る。
ウィルキンソンの想い入れは消化不良気味で複雑な心境だが、英国社会の階級格差が歴然とあるシークエンスでもある。
女装趣味の友達や、おませな先生の娘ダニーなどホノボノとしたシーンにも監督自身も身近なテーマであるジェンダーの問題が垣間見られる。
18歳になったときのビリーに宛てた亡き母からの手紙を先生が朗読したり、スクール合否の通知を家族がハラハラしながら待つところなど、ベタなシーンも思わず引きずり込まれてしまう。
特別出演のロイヤルバレエ団のプリンシバル、アダム・クーパーによる同性愛の悲恋を描いた<白鳥の湖>はエンディングに相応しく必見もの。
ミュージカルが映画化される事例は数多くミュージカルかミュージカル化されるのは極めて珍しい。エルトン・ジョンの音楽で05~12舞台公演され大ヒットした本作。
監督はその後「めぐりあう時間たち」(02)、「愛を読むひと」(08)、「ものすごくうるさくて、ありえないほど近い」(11)とコンスタントに作品を手掛け、12年ロンドン・オリンピックの開会・閉会式のプロデューサーを務めるなど大活躍。主演したJ・ベルも大人の俳優として活躍中で、ふたりにとって記念すべき作品となった。
英国では名匠ジョン・フォード監督作品「わがふるさとは緑なりき」(41)を始め炭鉱街を舞台にした傑作も多く、日本でも「幸せの黄色いハンカチ」(77)、「フラガール」(06)など大ヒット作があり、<炭鉱ものに外れなし>は本当だった。