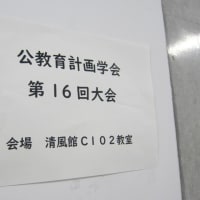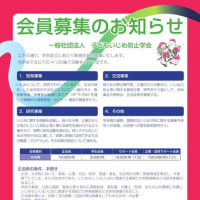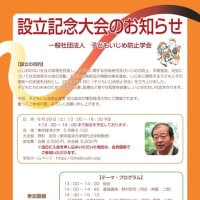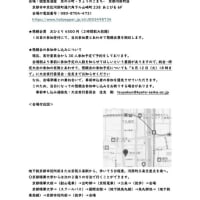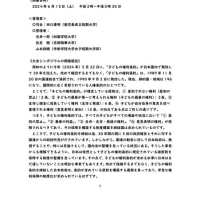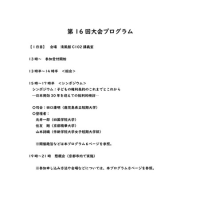部活動の大会 平日開催の是非を問う 「授業よりも部活動優先」の危うさ
(Yahoo!ニュース、2017年5月28日)
https://news.yahoo.co.jp/byline/ryouchida/20170528-00071413/
昨日から書き始めている「正直なところいかがなものか」と思っていることの2つめは、この記事です。
「結局、彼は、『授業が大事』『学習指導要領にもとづく正規の教育課程が大事』というその枠組みを越えられないんだな」ということですね。
あれだけ「教育を問う」とか「学校を問う」とか言っているわりには、たとえば彼は「部活動」であったり「2分の1成人式」であったり・・・と、どちらかというと、「特別活動」や「正規の教育課程外の教育活動」だったりする部分を問うていて、「本丸」ともいえる「授業」や「学習指導要領の枠組み」それ自体は「不問」にしているんだな、と。
この彼の論理の延長線上でたとえば教員の多忙化緩和策や部活動の活動日数・時間数規制をしていくと、結局、どういう学校ができあがり、どういう教育が営まれるか。
結論から言えば「がっちがちに固められた学習指導要領の枠組みのなかで、教職員と子どもがひたすら、授業に専念しているような、別の意味で『余裕のない』学校」かと。
ちなみに、このがっちがちに固められた学習指導要領の枠組みそのものが、子どもや教職員の負担しきれないくらいの学習内容を質・量ともに消化することを求めていたら・・・。彼の発想を前提にすると、多忙化は部分的に緩和されるかもしれませんが、抜本的には解消されません。だからこそ、教員の多忙化や部活動の活動日数等の規制の必要性は一方で認めるものの、他方で私は「ものたりない」と、彼らの多忙化緩和のキャンペーンについては思ってきました。
もちろん「学校は本来、勉強するところだ」とか、「学校での教育は本来、学問をするところだ」とか、そういう価値観があるのは認めます。彼も、もしかしたらそういう価値観の持ち主なのかもしれません。
でも、「学校で子どもが学んだり、経験したりする必要のあること」のなかに、「精一杯、自分の今、手持ちの力で、何かにチャレンジすることの大切さ」みたいなものを入れてみる。これを仮に「今を生きる経験」と呼んでおきます。また、この「今を生きる経験」そのものが「いまどきの中高生にとって必要な学習経験であり、学問への入り口になるものだ」と考えてみます。
ちなみに、私はどちらかというと、学校のなかであれ外であれ、子どもたちの「今を生きる経験」を充実させてほしいし、おとなたちはその「今を生きる経験」にできる限り、向き合ってほしいと願っています。
そういう風に考えてみたときに、「はたして今の学習指導要領の枠組みや、日々営んでいる授業のなかに、そのような子どもたちの『今を生きる経験』みたいなものが多々、含まれているのか?」という疑問もわいてきます。
だとすると、むしろ「いまどきの中高生にとって、『今を生きる経験』の場になっているのは、学習指導要領の枠組みに沿った日々の授業よりも、部活動だ!」なんて話も出てくるかもしれませんね。
そして、「いまどきの中高生にとっての『今を生きる経験』の時空間・仲間を保障するためには、むしろ学習指導要領の枠組みなんてぶっとばし、日々の授業もいったん脇において、熱心に部活動やることのほうが大事」なんて発想もでてきますよね。
とすれば・・・。「平日に数日、部活動の試合をしたからといって、どうなの?」という意見や、「学校の授業を休んでも、それにかわりうる貴重な経験をするんなら、別にいいじゃん」という意見にも、それなりに「一理ある」ということになりますよね。
さらにここへ「シーズン中は平日に試合等をして、土日はしっかりやすむ。試合で出られなかった授業は、オフシーズンなどに補習をする」なんて発想も組み入れたら、どうなりますか? 「別に何か、問題ありますか?」ということになりますよね。
要するに「大会日程と休養日、そして授業時間の確保。この3つを両立可能なカリキュラムをうまく組んだら、それでいいじゃん」って発想もあるわけですが、なぜこういう発想に彼は立たないんでしょうか?
私はやっぱり、彼は「学校」や「教育」のあり方を問うというわりには、「学校」や「教育」は「かくあるべし」ということに強いこだわりを持っている。なおかつ、そこだけは常に「不問」にされている。そして、その「不問」になっているこだわりの部分が、実は意外と「学習指導要領の枠組み」だったりするのではないか・・・と思っています。
いかがでしょうか? こんな風に考えていくとと、「教育」や「学校」のあり方を問いたい彼のまじめさ、善意は否定しないものの、やはりその「問い方」やその「問い」の前提にある価値観の部分で、私などは「いかがなものか?」と思ってしまうんですよね。
いまどきの教職員や子どもを最も追いつめたり、苦しめたりしているものが、もしかしたら「学習指導要領」かもしれないと思ったら、彼のような議論にはならないような気もするんですよねえ。
なお、「学習指導要領」自体もよく読み込むと、けっこう融通の利くものになっているところがあります。そういう「融通の利くもの」として読み込んでみると、先の私が言う「大会日程と休養日、そして授業時間の確保。この3つを両立可能なカリキュラム」だって実現可能かもしれません。
でも、こんな発想、今の彼からは出てこないだろうなあ・・・。