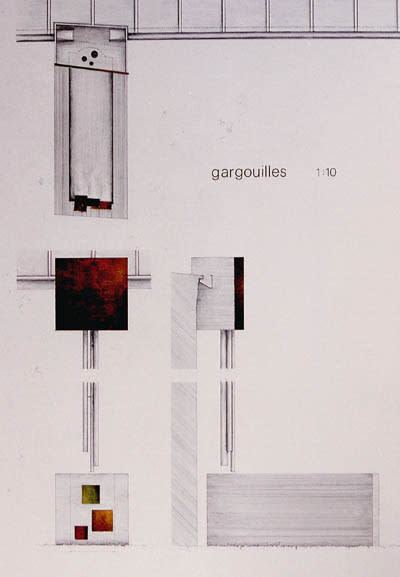桜坂の家も竣工から1年が経ち、先日、1年点検を行いました。工務店の監督さんと一緒に、じっくりと見て廻りました。結果、数箇所にペンキの剥げ落ちが見られたので、その手直し。玄関のドアチェックの調整など。細かな部分を何点か手を入れることになりました。手作りでつくられた家は、こうして少しずつ手をいれながらずっと住み続けていくもの。
久々に眺める桜坂の家。オマエ、すこし大きくなったんじゃないか?どこか、こんもりと山のような外観。植えてから1年経った植木はだんだん大きくなってきました。建物と緑の調和。その植木の間からダイニングテーブルのペンダントライトが垣間見え、穏やかな生活の様子がしのばれます。
道路に面してしつらえられたコンクリート製の雨樋受けの花壇には、賑やかに花が植わっています。小さな花壇ですが、その中だけを思いきっていろいろな色の花を植えるのが、とても楽しいのだそうです。そんな楽しみがあるのも、建物の表情が簡素で穏やかだからかもしれません。
帰り道、桜坂のそばを流れる六郷用水を通りながら駅へ。静かな木漏れ日のなかを歩んでいくと、桜坂の家に求めた住まいの在り方が、どんどんと思い出されてきました。古びた街の記憶。自分が生まれる以前からこの街にあり続けた、静かで穏やかな雰囲気に寄り添うような佇まいを、桜坂の家に求めたのでした。身の丈にあったちょうどよい大きさの、穏やかで素朴な質感をもち、そして内部では、きりりと引き締まった日本的な空間が支配するような。
設計をはじめる際、若い住まい手から最初に言われた要望は、「ワインのように年月と共に家も住まい手も味わいを増していく、そんなあり方を求めたい」
この家はそんな住まい手の気持ちに対しても、そして桜坂の「地霊」に対しても、僕なりの回答としてデザインしたものです。