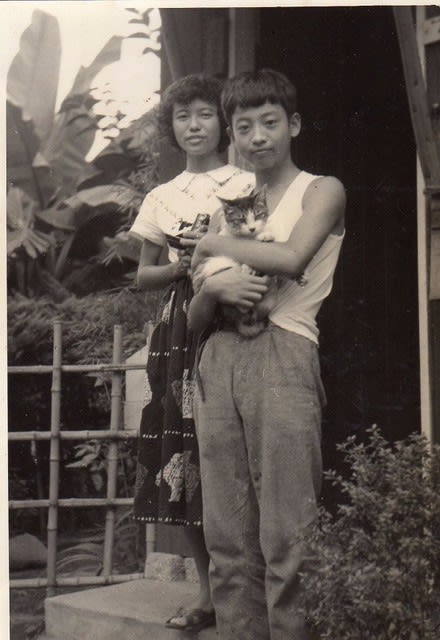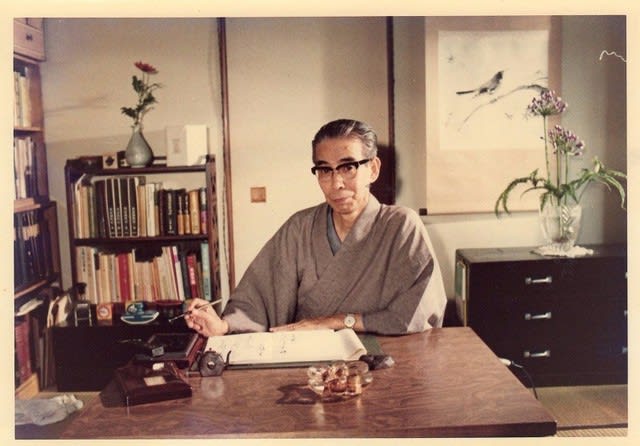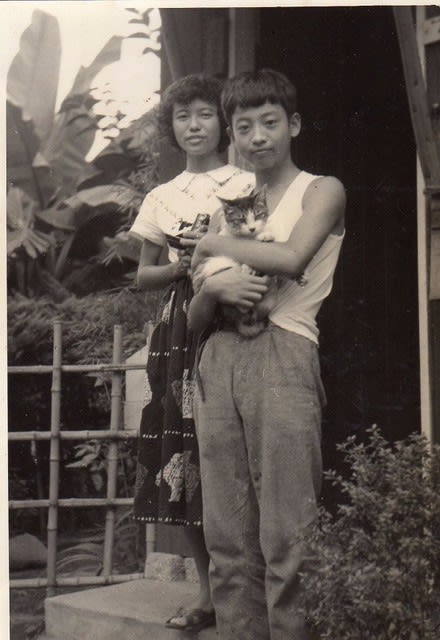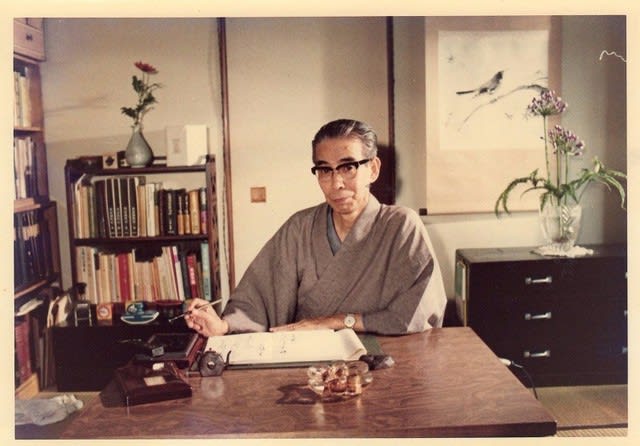終戦直後の東京の様子(一郎からと志へ) 昭和20年9月7日
パパは相変わらず、十日市に行く日を心待ちにしている。荷物を持てるとよいが、汽車がすごく混んでいるらしいので、それが心配だ。今一番困っている下宿先と食糧のこと。復員3000万人というから、地方でも職は難しいだろう。折角いい地位を失うようになったら困る。君たちをよぶにしては、家が第一の問題だ。
米軍は食糧を持ってくるし、軍票も使わないというから、急に食糧難やインフレになることもあるまい。反対にデフレの傾向があるから、政策さえよければ、何とか維持しうるだろう。荷物の輸送は自由になると新聞に出ている。疎開者の復帰はまだ制限しているようだ。全くどうしていいのか分からぬ。 8日に大湊に米軍が上陸するそうだ、あるいは八戸あたりも海岸に少し位は駐屯するよう遠からずなるかも知れぬ。地方民はあわてることだろう。しかし、東京の様子ではそう心配しなくてもよい。夜間外出せぬこと、途中で合図しても笑ったり、また手を振ったりしないこと、何かくれを言ったらおとなしくやっておくこと、家の戸締りをよくすること、等々を心得ておく必要があろう。
東京も明日進駐、米軍将校の自動車を昨日見た。電車や停車場にも時々米兵を見受ける。
至っておとなしく秩序あるようだ。ある米兵など女の客に席を譲っていた。これはアメリカの風習かも分からない。
終戦直後の汽車の混み方は、尋常ではなかったらしい。父はずっと旅行がきらいだったのは、この頃の記憶が頭に残っていたようだ。
当時、復員する人が3000万人もいたのは今の人には想像もできない。
日本人は、もともと攘夷の思想があり、米軍の進駐を恐れていたようだが、予想外に米軍の行動は、紳士的で秩序だっていたので、皆驚いている様子が書かれている。