
覆い被さるような梢から色素が滴り落ちて、身も心も緑に染まってしまいそうな広場。そんなところでゲートボールに興じていられるのは、生活に屈託がないという証明であろう。これは年老いて後の、一つの幸福なシーンだと、私もそのおすそ分けに預かって、しばらく眺めていたのである。ここは新潟県妙高市の市中公園。最近までは「新井」と言った、長野県境の街である。日曜日の朝、この街で90分を過ごした。
 直江津から長野に向かう途中、信越線新井駅で列車の乗り継ぎ時間が生じた。ぶらりと歩いてみる。北国街道の新井宿として栄えた旧市街は駅の西側である。緩やかな坂を登って行くと市役所があった。近隣の町村と合併した新井市は、自ら名を捨て「妙高市」となった。確かに「新井」より「妙高」が、全国的には通りがいいであろう。市役所は新しい街へと脱皮中であるかのように、新庁舎前の旧庁舎を解体していた。
直江津から長野に向かう途中、信越線新井駅で列車の乗り継ぎ時間が生じた。ぶらりと歩いてみる。北国街道の新井宿として栄えた旧市街は駅の西側である。緩やかな坂を登って行くと市役所があった。近隣の町村と合併した新井市は、自ら名を捨て「妙高市」となった。確かに「新井」より「妙高」が、全国的には通りがいいであろう。市役所は新しい街へと脱皮中であるかのように、新庁舎前の旧庁舎を解体していた。「中町」とあるから、かつては中心商店街だったのだろう、旧北国街道との辻に八十二銀行の支店があった。ここまで来ると経済圏は長野に含まれるのかもしれない。確かに直行快速で2時間20分かかる新潟市に対し、長野市へはその半分の時間で行ける。沿線で配布されている観光パンフレットも「信越高原」として資源を共有しており、県境など意識にないらしい。
 旧街道界隈は、例によって寂れが目立ち痛々しい。それでも坂を登っていくと、市民会館や図書館、高校などが固まっている公共空間に出た。市中によくこれ程のスペースが確保できたと感心させられるほど、広々として緑も濃い。子どもたちは元気に図書館に駆け込んでいき、広場ではお年寄りがゲートボールだ。高校からは運動部の掛け声が響いてくる。
旧街道界隈は、例によって寂れが目立ち痛々しい。それでも坂を登っていくと、市民会館や図書館、高校などが固まっている公共空間に出た。市中によくこれ程のスペースが確保できたと感心させられるほど、広々として緑も濃い。子どもたちは元気に図書館に駆け込んでいき、広場ではお年寄りがゲートボールだ。高校からは運動部の掛け声が響いてくる。 街のはるか背後を固める妙高山(2454m)は巨大な山塊で、その稜線は雄大である。その姿が街に落ち着きを、そして暮らしに安定感を与えているように感じた。岡倉天心が晩年の休息地に妙高高原を選んだ根拠は、この雄大な開放感ではなかったか。
街のはるか背後を固める妙高山(2454m)は巨大な山塊で、その稜線は雄大である。その姿が街に落ち着きを、そして暮らしに安定感を与えているように感じた。岡倉天心が晩年の休息地に妙高高原を選んだ根拠は、この雄大な開放感ではなかったか。 新潟市に育った私にとって、新井はただひたすら雪深い、遠隔の街というイメージしかなかった。スキーの選手を輩出し、「かんずり」という不思議な名前の特産品のある街、といった程度の知識である。わずか90分間の訪問で何が分かろうというものでもないけれど、「遠隔」のイメージに含まれる小さく侘しげな街という思い込みは全く的外れで、確かに小さいけれども、侘しさなどとは縁遠い、静かな街であった。
新潟市に育った私にとって、新井はただひたすら雪深い、遠隔の街というイメージしかなかった。スキーの選手を輩出し、「かんずり」という不思議な名前の特産品のある街、といった程度の知識である。わずか90分間の訪問で何が分かろうというものでもないけれど、「遠隔」のイメージに含まれる小さく侘しげな街という思い込みは全く的外れで、確かに小さいけれども、侘しさなどとは縁遠い、静かな街であった。 ただ歩いていて奇妙に感じたのは、道路がいくつも拡幅整備の途中で放置されていることだった。広い道と路地が混在しているのだ。不思議な都市計画である。
ただ歩いていて奇妙に感じたのは、道路がいくつも拡幅整備の途中で放置されていることだった。広い道と路地が混在しているのだ。不思議な都市計画である。市民会館の壁面に、この地方で採れる野菜の一覧であろうか、巨大なパッチワークが飾られていた。市民の手作りなのだろう、温かみがあって微笑ましい。インテリアショップの店先には、唐辛子がディスプレーに使われていた。日本3大発酵食品のひとつだという「かんずり」の原料である。土産にすると喜ばれるのだが、私自身は苦手な味である。(2008.6.22)










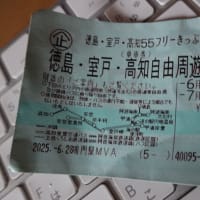



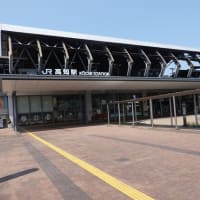










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます