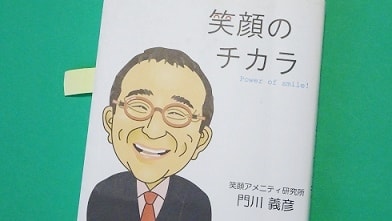トッシーです。いつもありがとうございます。
「笑顔でいるための心と体の12ヶ条」その7、後半です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第7条 いい息をしよう
呼吸をすると首にある呼吸中枢が刺激され、それが近くにある自律神経に伝わります。自律神経には、交感神経と副交感神経の二系統があり、吸う時は交感神経が興奮し、吐く時は副交感神経が興奮します。
自律神経は心臓や胃といった内臓の働きを人の意志とは無関係に調整しています。交感神経が強く働けば、心臓の鼓動は早くなり、血圧は上昇し、消化器の働きは抑制されます。副交感神経が強く働けば、反応は逆になって血圧も下がってきます。起きている時は交感神経が優位に働き、寝ている時は副交感神経が中心に働いています。
いろいろな呼吸法を体験してみましたが、それぞれに共通している点は、吐く息に重点が置かれていることです。その理由は、副交感神経を刺激し、寝ている時のようにリラックスしようというのが狙いなのではないでしょうか。吐く息を長くすると、リラックス効果が増すことは科学的に証明されています。
ストレスの多い生活では、交感神経が興奮することが多いので、逆に副交感神経を刺激することによって、心と体のバランスがとりやすくなるというわけです。どんなに頭にきてもフーッと息を吐くだけで怒りは静まります。呼吸の働きは偉大なものです。心と体をリラックスさせる呼吸法を紹介しましょう。
①まず肩の力を抜き、リラックスして座る。
②背筋を伸ばし、正しい姿勢を意識しながら、軽く目を閉じて大きくゆっくりと深呼吸をする。
③ゆっくりと5つ数えながら鼻から息を吸って、軽く止め、さらに10数えながら口から吐く。
④手のひらでお腹の動きを感じてみる。腹式呼吸になっていますか。
⑤おへその下(丹田)に気を込めて、さらにゆっくりと呼吸を繰り返す。
⑥以上を3分間実行する。
呼吸は生きることすべての基本です。呼吸をうまく行うことで、人間の自然治癒力を高めることもできるのです。そのポイントは、吐く息をゆっくりと長くです。
人間は、1分間に約15~17回呼吸を繰り返しています。15回を基準にすると、1時間に900回、1日に2万1600回、1年で788万4000回となります。それでは一生でどれほどの呼吸を繰り返すのでしょうか。気が遠くなるほどの呼吸の回数です。
呼吸の数と壽命は関係があります。鶴は千年、亀は万年といわれるぐらい、長寿の動物は呼吸が長いそうです。緊張すると誰でも呼吸は早くなります。長生きとは、長い息なのです。健康づくりはゆっくりと長く吐く息が基本です。
笑顔アメニティ研究所 門川 義彦著「笑顔のチカラ」より
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ついてる。ありがとうございます。感謝しています。 トッシーです。
トッシーです。