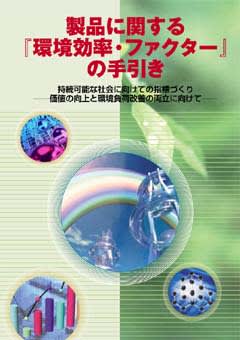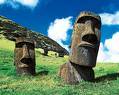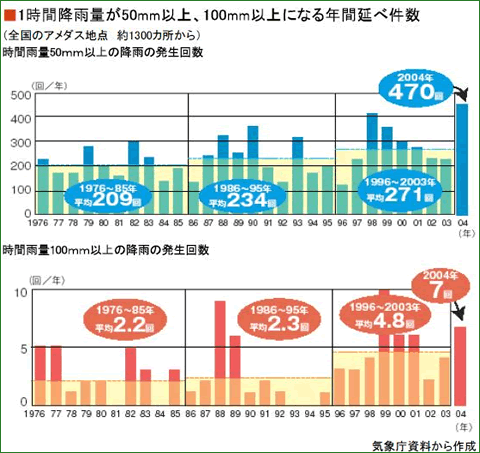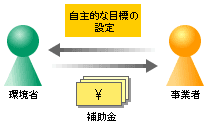主な家電製品では、以前に比べて何倍環境に優しくなったか(環境効率が何倍か)が表示されることになりそうです。
12月24日のこのブルグで、「環境効率とファクター」に付いて触れましたが、これに関連する以下の新聞発表を見つけましたので要点を紹介します。
一月前の2006年11月27日に、大手家電メーカー五社(東芝、日立、富士通、松下そして三菱電機)が以下の新聞発表をしていました。題して、『家電4製品の環境効率改善度指標「ファクターX」について「標準化ガイドライン」を制定』と。
これまで各社は、性能や使いやすくて環境への影響を低減した製品には「環境効率」や「ファクターX」を用いて訴えてきました。しかし、各社各様の表示形式や算出方法があり、算出の基礎となるデータ等についても公開には限度があるため、残念ながら消費者にとってわかり難いという欠点がありました。
今回、第一ステップとして、家庭での電力消費量が大きい家電4製品(冒頭の図参照)を選定し、「製品の価値(主要機能の性能)」と「環境への影響(ライフサイクル全体における温室効果ガスの排出量)」について、一定の条件の下で指標算出方式等を統一する「標準化ガイドライン」を制定しました。
このガイドラインを利用すると、過去(上記4製品では当面2000年度を想定)に販売された自社の同型製品に対する対象製品の価値(機能)向上と環境への影響(温室効果ガスの排出量)の低減という、製品の環境効率の改善度合いを端的に示すことが可能です。
対象基準となる過去の製品が各社異なるため他社製品との比較はできませんが、自社製品間における「買い替え効果の目安」として活用されることを期待しています。
今後は、引き続きパーソナル・コンピュータ、携帯電話など適用製品の拡大や技術的課題の解決に取り組み、将来的にはグローバルスタンダード化に向けた活動も展望しているとのこと。
12月24日のこのブルグで、「環境効率とファクター」に付いて触れましたが、これに関連する以下の新聞発表を見つけましたので要点を紹介します。
一月前の2006年11月27日に、大手家電メーカー五社(東芝、日立、富士通、松下そして三菱電機)が以下の新聞発表をしていました。題して、『家電4製品の環境効率改善度指標「ファクターX」について「標準化ガイドライン」を制定』と。
これまで各社は、性能や使いやすくて環境への影響を低減した製品には「環境効率」や「ファクターX」を用いて訴えてきました。しかし、各社各様の表示形式や算出方法があり、算出の基礎となるデータ等についても公開には限度があるため、残念ながら消費者にとってわかり難いという欠点がありました。
今回、第一ステップとして、家庭での電力消費量が大きい家電4製品(冒頭の図参照)を選定し、「製品の価値(主要機能の性能)」と「環境への影響(ライフサイクル全体における温室効果ガスの排出量)」について、一定の条件の下で指標算出方式等を統一する「標準化ガイドライン」を制定しました。
このガイドラインを利用すると、過去(上記4製品では当面2000年度を想定)に販売された自社の同型製品に対する対象製品の価値(機能)向上と環境への影響(温室効果ガスの排出量)の低減という、製品の環境効率の改善度合いを端的に示すことが可能です。
対象基準となる過去の製品が各社異なるため他社製品との比較はできませんが、自社製品間における「買い替え効果の目安」として活用されることを期待しています。
今後は、引き続きパーソナル・コンピュータ、携帯電話など適用製品の拡大や技術的課題の解決に取り組み、将来的にはグローバルスタンダード化に向けた活動も展望しているとのこと。