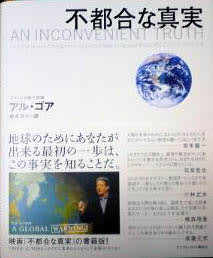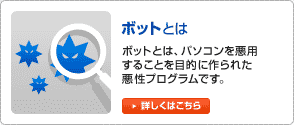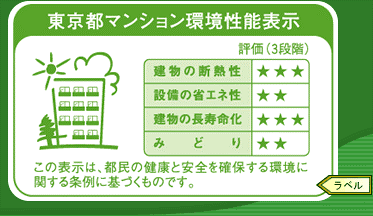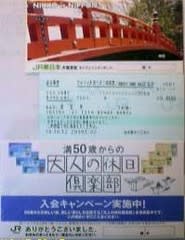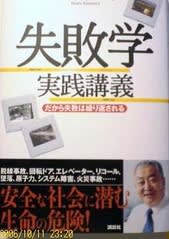この連休は特段の行楽スケジュールを立てていない。引越騒ぎのため、手が付かなかった事柄がいろいろ残っていること、長女の間近かな出産に備えて妻が何かと忙しく、出掛ける暇が無いなどの理由による。
当方としては、そのため集中してCDMの宿題や勉強に取組めるし、人通りの少ない朝の街中を通勤・通学の人々を気にせず歩き回る絶好のチャンスでもある。
今朝は、街の中心部を横切って片道20分ほどの調(つきのみや)神社へ出掛ける。「調」は「つきのみや」と読む。
この神社は平安期に編集された「延喜式神明帳」にも記載される古社として名高く、朝廷に納める御調物(みつぎもの)を集めた場所で、宮を建て調の宮と呼んでいると言う。調が月と同じ読みから、月待信仰に結びつき、狛犬の代わりに兎が置かれている。社名から「ツキ」に恵まれるとされ、心を鎮めて社殿に向かい、二礼-二拍-一礼し、幸運を祈願。
連休が明けると、またぞろ仕事で多忙になり朝のウォーキングを続けられなくなるが、今後は新たな環境に合わせて、6:30にはスタートした方が良さそうだ。
当方としては、そのため集中してCDMの宿題や勉強に取組めるし、人通りの少ない朝の街中を通勤・通学の人々を気にせず歩き回る絶好のチャンスでもある。
今朝は、街の中心部を横切って片道20分ほどの調(つきのみや)神社へ出掛ける。「調」は「つきのみや」と読む。
この神社は平安期に編集された「延喜式神明帳」にも記載される古社として名高く、朝廷に納める御調物(みつぎもの)を集めた場所で、宮を建て調の宮と呼んでいると言う。調が月と同じ読みから、月待信仰に結びつき、狛犬の代わりに兎が置かれている。社名から「ツキ」に恵まれるとされ、心を鎮めて社殿に向かい、二礼-二拍-一礼し、幸運を祈願。
連休が明けると、またぞろ仕事で多忙になり朝のウォーキングを続けられなくなるが、今後は新たな環境に合わせて、6:30にはスタートした方が良さそうだ。