 「やった!」サッカーワールドカップ、強敵デンマークに3-1で勝利を収め、日本は決勝トーナメント進出を決めた。
「やった!」サッカーワールドカップ、強敵デンマークに3-1で勝利を収め、日本は決勝トーナメント進出を決めた。 「それほどうれしいとは思わない」 勝利の立役者本田圭祐はそう言った。
「それほどうれしいとは思わない」 勝利の立役者本田圭祐はそう言った。
「(自分には)持ってるものがありますね」「(自分にとっての)目標は優勝ですから」
緒戦、カメルーンに貴重な1点をもたらした時の彼の言葉だ。
正直このことばを聞いて、なんとふてぶてしい男だろうとぼくは思った。
オランダ戦でボールを奪われ、圧倒され、何の働きもしない彼の姿を見て「いやあ、言ってるほどの者じゃないよ・・・」と言っていた彼のおじいさんの言葉を思い出し、やっぱり単なる<ビッグマウス>にすぎないのか、口ほどにもないやつだとぼくは彼の評価を下げた。
 しかし、今回のデンマーク戦でぼくは彼を完璧に見直した。
しかし、今回のデンマーク戦でぼくは彼を完璧に見直した。

フリーキックを遠藤ではなく、彼が打とうとしていたとき、ぼくは前の試合、彼の浮き上がった失敗キックを思い出していた。
ヨーロッパ選手権のとき、ロシアのチームの一員として成功したキックだって、相手のゴールキーパーのミスかもしれないじゃないかと・・・。
しかし今回のフリーキックは評判どおりの無回転で落ちる完璧なものだった。
それと、3点目のアシストがすばらしかった。普通の選手ならあの時自分でシュートしただろう。しかし、彼は冷静にサイドの岡崎に送って完璧を期した。
そういえば、カメルーンから奪った貴重な1点も彼の冷静な足捌きから生まれている。
 「今回はゴールしたとき観客席に向かいましたが?(前回はベンチに向かった)」
「今回はゴールしたとき観客席に向かいましたが?(前回はベンチに向かった)」バカなインタビュアーが彼に心情的なコメントを期待して質問したが、彼は「ただ、近かったから・・・」といなした。さらに「胸の国旗のマークに手を触れたように見えたのですが?」と国を背負う言葉を引き出そうとすると「それは当たり前のことで、むしろテストマッチの際はその意識が強すぎてから回りしていたので、今は自然体でやている」と返した。
つまり、彼は単なる大口たたきではなかった。冷静に状況を見極め処理するクールガイでもあった。
「それほどうれしいとも思わなかった・・・」
月並みでない、この言葉に彼の本心が現れていると、ぼくは彼を改めて見直した。
彼はこんなものでは満足しないのだ。
 日本に新たなスターが誕生した。
日本に新たなスターが誕生した。









 井上ひさしが肺がんで亡くなった。享年75歳。
井上ひさしが肺がんで亡くなった。享年75歳。

 ・・・いまは体育館より広いところで、みんな勝手にやっている時代なんです。そこで誰かが面白いことを言ったときに、勝手なことをやっていた人が、一瞬パッと見て「あ、そうか」と笑って、また勝手なことをやりますね。みんなの目を一瞬でもひきつけるのは、笑いによってしかできない。叫び声やお説教ではこっちを向かせることはできない。・・・
・・・いまは体育館より広いところで、みんな勝手にやっている時代なんです。そこで誰かが面白いことを言ったときに、勝手なことをやっていた人が、一瞬パッと見て「あ、そうか」と笑って、また勝手なことをやりますね。みんなの目を一瞬でもひきつけるのは、笑いによってしかできない。叫び声やお説教ではこっちを向かせることはできない。・・・ なるほど! 時代を見る目は確かだ。10年以上前の彼の言葉だが、今やテレビ界は<お笑い>満載で若い視聴者を取り込もうとしている。
なるほど! 時代を見る目は確かだ。10年以上前の彼の言葉だが、今やテレビ界は<お笑い>満載で若い視聴者を取り込もうとしている。


 彼の考え方や、生活態度はともかく、少なくとも<書くこと>に対する姿勢はぼくにとって魅力そのものだ。
彼の考え方や、生活態度はともかく、少なくとも<書くこと>に対する姿勢はぼくにとって魅力そのものだ。

 昨日見たNHKの特集番組では、その最初のステップとなった時のことを描いている。
昨日見たNHKの特集番組では、その最初のステップとなった時のことを描いている。 コソボとセルビアを結ぶ橋がある。
コソボとセルビアを結ぶ橋がある。 しかしタテマエは理解できても、言葉が違い、宗教が異なる彼らは顔を付き合わせれば、辛かった過去を思い出し、お互いを根っから信じあうことができない。
しかしタテマエは理解できても、言葉が違い、宗教が異なる彼らは顔を付き合わせれば、辛かった過去を思い出し、お互いを根っから信じあうことができない。 しかし、演目<バルトークのルーマニア民族舞曲>の練習に入ると、スピードは合わない、4分音符が合わない。お互い教えられた方法が異なっているのでバラバラだ。
しかし、演目<バルトークのルーマニア民族舞曲>の練習に入ると、スピードは合わない、4分音符が合わない。お互い教えられた方法が異なっているのでバラバラだ。




 そしてついに15番で石川はボギーを叩き彼に並ばれた。
そしてついに15番で石川はボギーを叩き彼に並ばれた。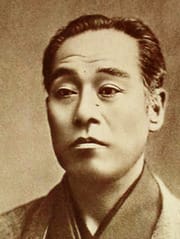

 「日本のことを尊敬される国にしたいんです」という深い思いが彼の根底にある。
「日本のことを尊敬される国にしたいんです」という深い思いが彼の根底にある。 このNGOは<マイクロクレジット>という無担保で貧しい人々に融資して自立支援するやり方で、担保も無いのに100%近い回収を可能にした実績を持っていた。
このNGOは<マイクロクレジット>という無担保で貧しい人々に融資して自立支援するやり方で、担保も無いのに100%近い回収を可能にした実績を持っていた。
 見ている人はちゃんと見ているということか。
見ている人はちゃんと見ているということか。 

 ピアノの発表会では、周囲への反発心から課題曲を弾いていても途中から自分で勝手に編曲して弾いたりした。
ピアノの発表会では、周囲への反発心から課題曲を弾いていても途中から自分で勝手に編曲して弾いたりした。