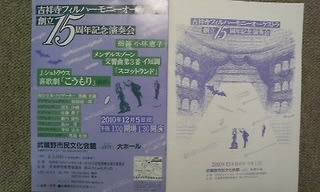ちょうど一年前になるが、昨年12月13日のブログを読み返すと、「素敵だった『山びこの会』忘年会」と題して、この会の生い立ちから素晴らしい活動について触れている。昨夜、再び巡ってきた「忘年会」に参加させてもらった。実は私は正式会員でなく、山行にも参加していないが、昨年のいきさつ(娘と息子が小コンサートを演奏)から参加を許されたのだ。
行ってみると、私のように山にも行かずに暮れの酒飲み会だけに出るような人が何人かいたので、その点門戸が開かれた会なのだ。そしてそこにこの会の素晴らしさがあるのかもしれない。来るものを拒まず、去るものを追わず、全く肩に力の入ってない会で、しかも14年目を迎えて会員数は増えている。(最初の数人から今や70人を超えた)
私は昨年初めてそのことを知って、「今どきこのような会が、未だ日本にあったのか?」と思い続けて来たのであるが、会員の高い自覚と自由な意思に基づいた運営が、今や珍しくなった“長期成長型サークル”を生み出したのだろう。
昨夜の忘年会には、新たな会員3名を迎えた総勢73名の中の59人(80%)が参加、しかも、それに続く二次会にそのうちの半数が参加して、時間の果てるのも知らず話し合っていた。
このような会の存在を見ると、日本も未だ捨てたものではない、と思うのだが。