
「東海道五十三驛もの」は2007年1月の「通し狂言 梅初春五十三驛」を観ている。菊五郎の化け猫と子役ちゃん達のパラパラが楽しかったが、今月は猿之助十八番の中でも一番の当り狂言だということでさてさてどんな感じかと興味津々。

【猿之助十八番の内 獨道中五十三驛(ひとりたびごじゅうさんつぎ)】
市川右近十五役早替りならびに宙乗り相勤め申し候
あらすじのエッセンスを下記に公式サイトより引用。
「由留木家に伝わる二つの家宝をめぐって、敵味方が追いつ追われつ、東海道五十三次の宿々を舞台に日本各地を駆けめぐります。『東海道中膝栗毛』でおなじみの弥次さん喜多さんの女房おやえ、おきちもコミカルに登場。」

主な配役は以下の通り。
市川右近=お三実は猫の怪/江戸兵衛/丁稚長吉/信濃屋お半/芸者雪野/帯屋長右衛門/弁天小僧/土手の道哲/女房お絹/鳶頭右之吉/雷/船頭澤七/鬼門の喜兵衛/土手のお六/由留木調之助
市川段治郎=丹波与八郎
市川笑也=重の井姫/荵の方
市川笑三郎=弥次郎兵衛女房おやえ
市川春猿=喜多八女房おきち
市川門之助=由井民部之助/十文字屋おもん
市川弘太郎=石井半次郎
市川寿猿=赤羽屋次郎作/赤星十三郎
市川猿弥=赤堀水右衛門/雲助逸平

四世鶴屋南北の作品を1981年に猿之助が復活上演。初演時に十八役を替ったところ、市川段治郎が由留木家の忠臣丹波与八郎を右近が十五役を替わる(初演時とは内容が変わっているため)。
「五十三驛もの」というのは物語はなんとなく通っているだけで、いろいろな歌舞伎狂言の書替え趣向てんこもりと役者の魅力を楽しむものだということがよくわかる。中でもお約束的な岡崎の化け猫の場面はやはり菊五郎の時と比べてしまう。猿之助の復活の方が先だから、菊五郎はそれと違った趣向にしたのだということも思い当たる。今回の化け猫に操られる猫たちは吊り人形だった。食い殺されるおくらを追い詰める場面は右近の化け猫も天井裏に上がってバーを使って降りてくる。このへんも役者の肉体的条件による演出の違いを思った。十二単の化け猫姿の右近の宙乗りも三階席で間近に観ることができてラッキー!

笑也の重の井姫に道中双六を見せる自然薯の三吉が丹波与八郎でというあたりで、「恋女房染分手綱」と「桜姫東文章」の趣向とわかって嬉しくなる。段治郎と玉三郎の「桜姫~」と重なるからだ。さらに「忠臣蔵」六段目の趣向になって勘平的役割の与八郎が敵方の江戸兵衛の鉄砲で撃たれてその傷が元で足腰たたずの照手姫が引く車に乗る小栗判官状態へ。世話をしてくれる逸平が一文字屋ならぬ十文字屋の女将から五十両を盗んだ騒動から重の井姫が身売り。おかる的に別れの場面になっての六段目の趣向は手が込んでいる!!

海中での海星や海老、蛸とのなどとの立ち廻りは「ヤマトタケル」の熊襲の兄弟の衣裳も連想して楽しかった。
二幕最後の重の井姫が悪者に斬られて身を沈める滝壺の本水の装置も見事。姫の百度の水垢離の効あって与八郎の病全快での立ち回りも見応え十分。まさに水もしたたるいい男!袖や裾の水を絞るのは斧定九郎のパロディだろうし、さらに犬の身震いのように全身の水を飛ばすのはこれは客席へのサービスか(笑)
三幕は主に右近の十二役早替りを楽しめばいい。「お染の七役」「お半長右衛門」「二人椀久」「弁天小僧」「願人坊主」などの趣向がわかっているとただただ早替りに喚声を上げる以上に楽しめるだろう。それにしても右近は顔もすっきりして女方の役々も可愛いこと!!

全編を通す狂言回し役の笑三郎と春猿は女二人の漫才芸人のように面白すぎる。座頭の右近が化け猫まで一時間も登場しないために冒頭に口上の場面を新しく追加したらしいが、そこから二人の現在の言葉を持ち込んだお笑いが炸裂。途中も春猿が麻生(アサオ)大臣のように言葉を言い間違えるネタが大ウケ!「未曾有(ミゾユウ)のピンチ」とか、「定額給付金はさもしいからもらわない」「やっぱりもらう」とかねぇ。このコンビで数年前の歌舞伎鑑賞教室の前半の解説部分が盛り上がったというのも納得だった。

写真は公式サイトより今回公演のチラシ画像。















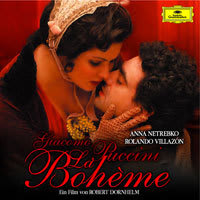



































 →
→