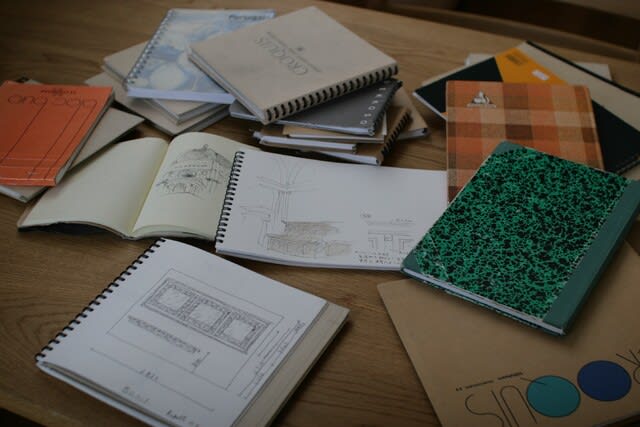大学で建築を勉強したいと希望する高校生が、ぼくのアトリエに遊びに来てくれました。
都内でいくつかの話題の建築を見学し、その後ぼくのアトリエへ。見学してきた建築、すごくカッコよかったです!そんな素朴な感想を聞いているだけで、とても嬉しくなります。
住宅の設計を中心に仕事をしているぼくの小さなアトリエ。小さな空間で、少人数のメンバーで設計を進めていくのは、独特の充実感があります。
模型やスケッチや図面など、少しばかり実際の仕事の風景を見てもらいました。彼にとってちょっとしたいい思い出になってくれるといいのですが・・・。
話の流れで、ひょんなことからスペインの建築家ガウディのことに話が及びました。実はぼくの卒業論文のテーマはガウディでした。当時は、友人や先輩からは「今時ガウディとかやって、なんか役に立つの?」とよく言われました。
ぼくにしたってよくわかりませんから、言葉を濁すことしかできませんでした。でも今では、ガウディの建築にはこれからますます大きな可能性があるとはっきりと思います。
そんな話をしながら、ぼくが学生だったときにガウディの建築に取り組み、見学したときのことを思い出していました。
写真は、バルセロナにあるガウディ設計の集合住宅「カサ・ミラ」の屋上。不思議なカタチの煙突がニョキニョキ生えています。
この造形、あらためて見るとホントにすごいですね。煙が上りやすくするための実験をしながら見つけたカタチだそう。それが不思議な宇宙人のようにも見えるのも愛嬌ですね。
よく見ると、下から覗きこむ大学生の頃のぼくの姿が(笑)訪問してくれた高校生の彼も、やがて旅行に出て夢中で建築を見て回るのでしょうか。そんな時期が、絶対に必要です。
ガウディの建築は、名作といわれるものはだいたい未完成なのです。未完成なのに名作と言われるのも不思議ですが、建築は時代とともに変化していくべきものだから、完成なんて永遠にあり得ないのだよ、と言われているようです。
実際に、ガウディのいくつかの建築は、全体像が描かれないまま造られました。そう、あのサグラダファミリア、でさえも。
技術革新により、あと数年後には完成するという話ですが、だからこそ、完成しないことの意義についても考えてみたくもなります。