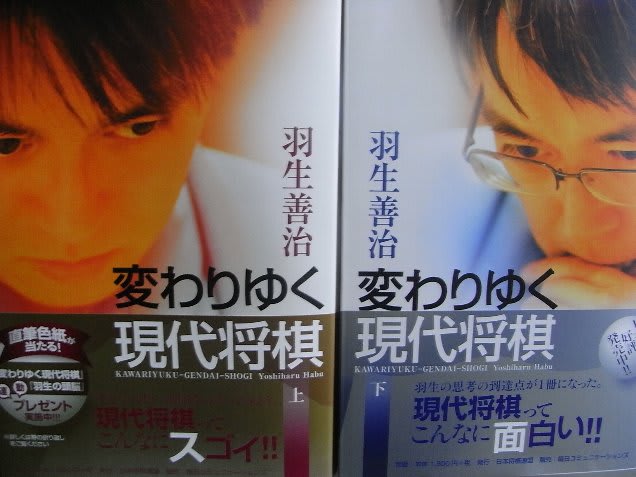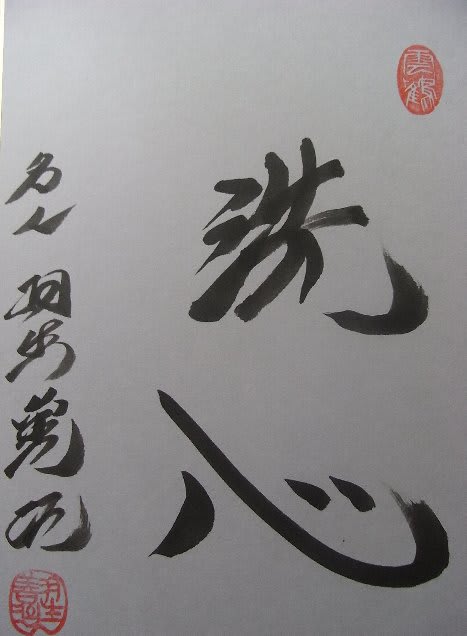各閣僚、小沢氏に進退判断促す 「参院選への影響心配」(共同通信) - goo ニュース
一時は落ち着いたかと思っていたら、ここにきて、「検察審査会」なるものが、
『これやっぱおかしいじゃん!』ともの申して政局に大きな影響を与えるようなことに。
いや、それはいいのだけど、
検察審査会、って知ってました?
知らなかったですよ、そんなの。
今回起訴相当と議決した。
これで検察がまた不起訴にしたとしても、再度検察審査会が、起訴相当と決めれば、
これは結果「起訴」になる。

すごい権限ですよね。
裁判員よりもすごいかもしれないこのことを、何で今まで知らせてくれなかったのよん?
冷たいじゃん。
知らなかったおいらが無知で悪いってことかい?
ムチで打たれても仕方ない?
---------------------------------------------
 選出
選出
司法に一般国民の常識を反映させるという目的で、検察審査会法第4条により、各検察審査会管轄地域の衆議院議員の選挙権を有する国民の中から、くじで無作為に選ばれた11名で構成される。任期は6か月で、そのうち半数が3か月ごとに改選される。審査員が欠けた場合に備えて、補充員がいる。
 除外
除外
検察審査会法第5条・第6条により以下の者からは選出できないとされている。
学校教育法に定める義務教育を終了しない者、1年以上の懲役または禁錮以上の刑に処せられた者
天皇・皇后・太皇太后、皇太后・皇嗣・国務大臣・裁判官・検察官・会計検査院検査官・裁判所常勤職員・法務省常勤職員・国家公安委員会委員・都道府県公安委員会委員・警察職員・司法警察職員・自衛官・都道府県知事・市町村長・弁護士・弁理士・公証人・司法書士
 免除
免除
検察審査会法第8条により以下の者から免除出来るとされている。
70歳以上・国会議員(会期中のみ)・地方議会議員(会期中のみ)・国家公務員・地方公共団体職員・教員・学生・過去5年以内に検察審査員又は補充員・過去5年以内に裁判員又は補充裁判員・ 過去3年以内に選任予定裁判員・過去1年以内に裁判員候補者として出頭したことがある者・重病者・海外旅行中等
 責務
責務
検察審査会法第43条・第44条により、検察審査会を正当な理由なく欠席することは禁止され、守秘義務を負い、審査された事件から得られた情報を、他に漏らすことは終生禁止されている。これらについては、招集に応じないとき等は10万円以下の過料、職務上の秘密を漏えいした場合は6年以下の懲役または50万円以下の罰金を科す旨の罰則規定がある。
---------------------------------------------------
へー、こんなのあったんだ。
司法に国民の視点も取り入れようということで、あれだけ物議をかもした裁判員制度。
それはいいけど、そんなことのずっと前からこういうのあったわけだ。
いつご指名されても仕方なかったような制度があったわけなのね。
しかもそう簡単には断れない。
同じようだよねえ。
それ、先に言って欲しかったよなあ。
以前、アマの視点、裁判員制度のことと書いたのだけど、そんな前代未聞のことではなかったんだねえ。
マスコミも含め、あの大騒ぎはなんだったんだろうか。
ずっと前から(昭和23年だってよ!)こんな制度があったのであれば、裁判員制度の導入で、あれだけ騒ぐって言うのおかしいのではないですかい?
なんかこの国、おかしくないですかい?
一時は落ち着いたかと思っていたら、ここにきて、「検察審査会」なるものが、
『これやっぱおかしいじゃん!』ともの申して政局に大きな影響を与えるようなことに。
いや、それはいいのだけど、
検察審査会、って知ってました?
知らなかったですよ、そんなの。
今回起訴相当と議決した。
これで検察がまた不起訴にしたとしても、再度検察審査会が、起訴相当と決めれば、
これは結果「起訴」になる。

すごい権限ですよね。
裁判員よりもすごいかもしれないこのことを、何で今まで知らせてくれなかったのよん?
冷たいじゃん。
知らなかったおいらが無知で悪いってことかい?
ムチで打たれても仕方ない?
---------------------------------------------
 選出
選出 司法に一般国民の常識を反映させるという目的で、検察審査会法第4条により、各検察審査会管轄地域の衆議院議員の選挙権を有する国民の中から、くじで無作為に選ばれた11名で構成される。任期は6か月で、そのうち半数が3か月ごとに改選される。審査員が欠けた場合に備えて、補充員がいる。
 除外
除外検察審査会法第5条・第6条により以下の者からは選出できないとされている。
学校教育法に定める義務教育を終了しない者、1年以上の懲役または禁錮以上の刑に処せられた者
天皇・皇后・太皇太后、皇太后・皇嗣・国務大臣・裁判官・検察官・会計検査院検査官・裁判所常勤職員・法務省常勤職員・国家公安委員会委員・都道府県公安委員会委員・警察職員・司法警察職員・自衛官・都道府県知事・市町村長・弁護士・弁理士・公証人・司法書士
 免除
免除検察審査会法第8条により以下の者から免除出来るとされている。
70歳以上・国会議員(会期中のみ)・地方議会議員(会期中のみ)・国家公務員・地方公共団体職員・教員・学生・過去5年以内に検察審査員又は補充員・過去5年以内に裁判員又は補充裁判員・ 過去3年以内に選任予定裁判員・過去1年以内に裁判員候補者として出頭したことがある者・重病者・海外旅行中等
 責務
責務検察審査会法第43条・第44条により、検察審査会を正当な理由なく欠席することは禁止され、守秘義務を負い、審査された事件から得られた情報を、他に漏らすことは終生禁止されている。これらについては、招集に応じないとき等は10万円以下の過料、職務上の秘密を漏えいした場合は6年以下の懲役または50万円以下の罰金を科す旨の罰則規定がある。
---------------------------------------------------
へー、こんなのあったんだ。
司法に国民の視点も取り入れようということで、あれだけ物議をかもした裁判員制度。
それはいいけど、そんなことのずっと前からこういうのあったわけだ。
いつご指名されても仕方なかったような制度があったわけなのね。
しかもそう簡単には断れない。
同じようだよねえ。
それ、先に言って欲しかったよなあ。
以前、アマの視点、裁判員制度のことと書いたのだけど、そんな前代未聞のことではなかったんだねえ。

マスコミも含め、あの大騒ぎはなんだったんだろうか。

ずっと前から(昭和23年だってよ!)こんな制度があったのであれば、裁判員制度の導入で、あれだけ騒ぐって言うのおかしいのではないですかい?

なんかこの国、おかしくないですかい?













 「外食市場」
「外食市場」