電王戦考察・その2・その3・その4・その5と電王戦についていろいろ思うところを書いてきました。
もう飽きたよって言われるのはわかるけど、しつこい、しぶとい、っていうのが持ち味、棋風。
いろいろ心配したり問題提起したりしましたが、この後、どこに行こうとしてるのかもはやわからなくなってきました。大体、書こうと思ってたあのことはもう書いたのか、まだなのかも曖昧になってきた。(いつもこれじゃん。)
“果敢”にも“難解”なテーマを“何回”も“書かん”としてることは褒めてあげてもいいけど、最後がそれじゃあ閉まんねーよ。
電王戦はこれからもつづくのでしょうけど、果たしてどうするのか、次は誰が出るのか、あるいは持ち時間のハンディとか事前貸出しをどうするのか、とか、いろいろ議論はあると思います。
しかし、阿部光瑠四段が指摘したように、これは全く別物という説、賛成です。(参考:番外編)将棋とコンピュータ将棋の違い)
別の競技を無理やり条件を揃えようとしても無理がある。
猪木とアリのプロレスでもボクシングでもない格闘技のように、どうやったところで、これじゃあっちが不利、それでは公平性に欠ける、とかって意見が出てくる。
コンピュータの進化は人間が苦手としてきたことへの対応など、メリットは山ほどあるとは思うし、人間の進化を助けるものであるという側面はよくわかる。
しかし、いずれコンピュータの方が人間が逆立ちしても及ばないほど強くなっていくのは時間の問題だと思うけど、そうなった時にどのようにつきあうのか。
3年後か30年後かはわからないけど、そうなることを前提にして今からどのような関係性を作っていくのがいいのか。
チェスはコンピュータに負けてからどうも発展の速度が落ちているらしいけど(そのせいなのかどうかは要検証)、 将棋はその轍を踏まないようにできるのかどうか。
極端に言うと、序盤で勝負が見えてしまうというような、将棋の持つゲーム性が魅力ないものになってしまう可能性をはらんではいないのか。
見えてなかったものが丸裸にされて、毀損するようなことにはならないのだろうか。
将棋ってこんなもんか。思ってたよりも浅い。なんだ、意外につまらない。欠点があって楽しめない。
将棋のゲームとしての側面ばかりをすごい勢いで突き詰めていくと、文化としての側面とのバランスが悪くなり、おかしなことになっていかないのだろうか。
茂木健一郎さんのこの本に興味深いフレーズがありました。
これは柔道の話です。
【講道館において生み出された文化としての柔道と、オリンピック競技となり国際化した文明としての柔道の間には数々の齟齬がある。
カラー柔道着は文化としての柔道の視点から見れば醜い堕落であることだろう。一方、文明としての柔道の観点からは、グローバル化する中で、カラー柔道着は避けて通れない変化だったのかもしれない。】
将棋における文化と文明の視点。
ガラパゴス化とグローバル化のクロスポイント。
コンピュータが代表する文明の波、時代の嵐に飲み込まれていくと、いまだかつて将棋が経験したことのない未知の世界に足を踏み入れていくことになる。
400年の歴史を誇る名人戦に象徴される伝統文化としての将棋は、これから青い柔道着を纏うことになっていくのだろうか?
それにしても技術革新、それに伴うグローバル化のスピードは速い。
これは前の記事(その2)に対するssayさんのコメントです。
【いえ、あまりに急展開すぎたのですよね。
現役A級棋士の三浦八段が負けたのは、結果としては仕方ありませんが、あまりにも私達に心の準備ができていませんでした。もう少し、何年か掛かりで段階を踏んでいただければ・・・。】
ほんと、ここ、失敗しましたね。明らかな作戦負けです。
棋士の成長のスピードとコンピュータの進化のスピードは全く違うので、もしも何回かのシリーズでやるのなら、今回の5対5はもう1年から1年半くらい早くやればよかったのではと思います。
一回とは言え、A級棋士が負けてしまったからには、次回の時期、メンバーややり方をどうするのか。
連盟新体制にとってはかなり難しい局面です。
どちらかの三冠が登場したりすればそりゃ興行的には盛り上がるものの、コテンパに負けてしまった時のリスクは計り知れない。
どちらにしても、勝つか負けるかハラハラドキドキという勝負ができるのは、ここ数年なんだろうと思いますし(1,2年か?)、客観的に見たら、平手で普通に勝負できる期間は限られてくるのだと思います。
いつの日か棋士に勝てるようなソフトを作りたい。
そしてその途方もない夢が実現する。
その夢の向こう側には何があるんだろ?
何度も言うけど、別に否定はしてません。
電王戦の話から多少ずれてしまうけど、僕の感覚から言えば、もっとゆっくり人間が全力を出し切りつつ、考えながら進化していけばいいのではないだろうかと思う。
もっとゆっくり、君は速すぎる
この朝が続くように、
石の道をただブラブラと楽しいことがありそうな
すてきな気分
《サイモンとガーファンクル「59番街橋の歌」》
そんなに急いでどこへゆく。何かに急かされ焦りすぎているのではないか。
自分を見失っているのではないか。
例えば、昔は10時間とか6時間とかかかっていた大阪までの移動だって、もう2時間半が当たり前。
そしてもっともっと早く行けないかいろいろやってる。
何時間で行けたら満足するの?
要望、欲望はいつになったら止まるの?
足るを知る、 ですね。
昔鈍行列車に揺られてゆっくりのんびりと旅行していたのが懐かしい。
景色を楽しむ。経過を楽しむ。いろいろ振り返って考える。
皆すごいスピードで走っている。
脇目も振らずに突進している。
ドッグイヤー、マウスイヤー。
技術、経済、文明など、すべてが加速している。アクセル全開。
そのことが人間にとって本当に幸せなことなのかどうか。
すっかり余裕をなくしてることがいろんな問題を起こしたり、解決のネックになっているのではないか。
将棋は将棋でコンピュータの力を借りずとも、徐々に少しずつ進化発展していけばいいのではないか。
長い歴史の中で、将棋を愛してやまないその時代のトップ棋士たちが、己のすべてを賭けた盤上の一手。
それが凝縮して受け継がれ、新たな時代の中で定着したり修正されたりしつつ、大きな川の流れのようになってゆったりと流れ続けている。
自然の中で大きなうねりとなって流れているこの川が、一歩コンピュータとの関係を間違うと、違う流れ方になっていかないのだろうか。
こんなことを考えつつ再度上記の茂木さんの本から引用させてもらいます。
【日本人は、「文化」は理解しても、「文明」は、畢竟、理解していないのではないか。
そのことが、近代における日本の失敗、そして、今、ヴィジョンなくさまよう我が国の現状に関わるのではないか。】
将棋とコンピュータの交わり、そしてその未来のことに思いを巡らしていたら、何だか知らないけど大げさな話になってきちゃいました。
【近代における日本の失敗、そして、今、ヴィジョンなくさまよう我が国の現状】の中に将棋が迷いこまないことを祈っています。
【文明は文化を包摂し、文化は、文明というゆりかごの中で新陳代謝する。そのような人間のありさまを曇りのない目で見れば、ひとつの文化の純粋さに固執することは、必ずしも永続可能な態度ではないということが明らかにされるだろう。】
大きな目で見れば、こういうことにもなるのだろう。
文化としての逞しさ、時代の変遷の中でもみくちゃにされたとしてもしっかりと着実に進化し続けられる力、それが問われているのだと思います。
そういう意味からしたら、絶滅危惧種をいろんな危険にさらさないようにして守ろうとする姿勢ではなく、これだけ着実に根付いて日本中の老若男女からしっかり支持されているのだから、ほっといたとしても、時代の波に翻弄されずに大きなうねりになっていくのかなあ、と楽観的にも思えます。
【文化は、文明というゆりかごの中で新陳代謝する。】
いい言葉ですよね。
細胞が活発になり、細胞分裂してどんどん増殖していく。
将棋の健康。将棋の幸せ。
明るい将棋の未来を願っています。
何か大げさな話になってきたし、どこに向かって進むのやら皆目見当もつかないのだけど、多分、まだ続きます。(しつこい!)
 20代の反乱
20代の反乱 20代の反乱・その2
20代の反乱・その2 30代に負けるな!
30代に負けるな! 羽生世代の逆襲
羽生世代の逆襲 羽生世代の復権
羽生世代の復権 羽生世代の時代
羽生世代の時代 まわるまわるよ時代はまわる
まわるまわるよ時代はまわる

















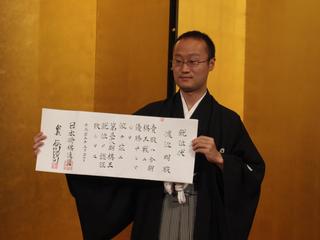














 ホレ、スイスイスーダララッタ、スラスラスイスイスイ~
ホレ、スイスイスーダララッタ、スラスラスイスイスイ~ 




