
今宵、信州・安曇野は満月である。あまねく月光に照らされた大地は、俺たちトノサマガエルの棲家なのだ。昨日までは大雨だったから、安曇野の大地はいつも以上に水を含み、田植えを終えた稲田は満々と水が張られている。月が梢の上まで昇った。人間どもは家に引っ込んだ。さあ、俺たちの刻が来た。白い腹を大きく膨らませ、喉を震わせ「ケロロッ」。俺の一声を合図に、みんな一斉に得意の喉を披露し始める。人間にはこれが合唱に聞こえるらしい。

トノサマガエルの大合唱である。俺も知らないけれど、この辺りだけで数千匹はいるであろう仲間たちが、一斉に声を上げるのだ。そりゃあ賑やかになるさ。一際高く伸びやかな喉自慢カエルや、それを引き立てるように低音をリズミカルに繰り返す「ケロッ」「グエッ」のバックコーラス。湧水地に建つホテルの2階のベランダに、爺さんが出てきた。満月を浴びて、白い口髭を光らせている。俺たちの合唱があんまり賑やかで、目が覚めたのだろう。

キョロキョロ辺りを見回している。カエルの鳴き声にも色々あると楽しんでいるのか、月光を浴びながら、ベランダを動こうとしない。ひょっとして気がついたのだろうか。これは合唱ではなく、カエルたちの会話なのだ、と。そうなのだ、この時間は俺たちの重要な情報交換タイムなのだ。「大雨の時期だから、流されるなよ」「あそこの水路は壁が改修されたから、落ちたら這い上がれなくなるぞ」「今年はツバメが多い。好物の子虫が横取りされる」

安曇野市が信州大学と連携して編纂している『安曇野風土記』の第1巻は、「水で結ばれたふるさと」と題して「安曇野と水」を詳述している。この土地を語るには、まず「水」なのだろう。ベランダの爺さんは、新潟の中学時代の同級生御一行で、長い外国暮らしから帰り、安曇野に落ち着いた友人を歓迎しようと、60年来の親しい仲間5人が集ったのだという。見晴らす限り「水鏡の里」になる安曇野だから、いい時期にやって来たと言えるだろう。

吾輩が本拠地としているこの辺り、つまり安曇野市穂高の東端あたりは、北から下る高瀬川が、西からの穂高川と共に、南からやってくる犀川に流れ込む「三川合流部」と呼ばれる、安曇野で最も標高が低い地域である。犀川は合流部に入る手前で、梓川と奈良井川の水が合わさって名を新たにした川だ。松本平のすべての川が、この合流部で一体化するのである。水は表流水として流れ下るだけでなく、膨大な量が地中に染み、湧水としてここに現れる。

『安曇野風土記』を書いた笹本正治さんは、安曇野の水について「水は天空と私たちの世界をつなぎ、なおかつ循環しています。私たち市域の水は犀川となり、千曲川とつながり、信濃川になり、日本海に流れます。海の水は国境に規制されませんので、この水は世界とつながります」と書いている。北アルプス・常念山脈の水が潤す大地で小旅行を楽しむジジババ5人組は、信濃川の河口の街で育ったものだから、安曇野とは水で繋がっていた事になる。

さて、夜も更けて来た。人間の時間で言えば23時ころだろうか。安曇野蛙は仁義に厚い。いつまでもゲロゲロ鳴いていたのでは、迷惑を及ぼすかもしれない。俺の一声で今夜の情報交換会議は終了する。どうだ、騒めきはぴたりと止んで、全くの無音になっただろう。無音という「音」が、耳の奥で響いているのではないか。いずれにせよ都会では、味わえたくても味わえない感覚だろう。安曇野は水と音無しの世界である。おやすみなさい。(2025.6.12-13)







トノサマガエルの大合唱である。俺も知らないけれど、この辺りだけで数千匹はいるであろう仲間たちが、一斉に声を上げるのだ。そりゃあ賑やかになるさ。一際高く伸びやかな喉自慢カエルや、それを引き立てるように低音をリズミカルに繰り返す「ケロッ」「グエッ」のバックコーラス。湧水地に建つホテルの2階のベランダに、爺さんが出てきた。満月を浴びて、白い口髭を光らせている。俺たちの合唱があんまり賑やかで、目が覚めたのだろう。

キョロキョロ辺りを見回している。カエルの鳴き声にも色々あると楽しんでいるのか、月光を浴びながら、ベランダを動こうとしない。ひょっとして気がついたのだろうか。これは合唱ではなく、カエルたちの会話なのだ、と。そうなのだ、この時間は俺たちの重要な情報交換タイムなのだ。「大雨の時期だから、流されるなよ」「あそこの水路は壁が改修されたから、落ちたら這い上がれなくなるぞ」「今年はツバメが多い。好物の子虫が横取りされる」

安曇野市が信州大学と連携して編纂している『安曇野風土記』の第1巻は、「水で結ばれたふるさと」と題して「安曇野と水」を詳述している。この土地を語るには、まず「水」なのだろう。ベランダの爺さんは、新潟の中学時代の同級生御一行で、長い外国暮らしから帰り、安曇野に落ち着いた友人を歓迎しようと、60年来の親しい仲間5人が集ったのだという。見晴らす限り「水鏡の里」になる安曇野だから、いい時期にやって来たと言えるだろう。

吾輩が本拠地としているこの辺り、つまり安曇野市穂高の東端あたりは、北から下る高瀬川が、西からの穂高川と共に、南からやってくる犀川に流れ込む「三川合流部」と呼ばれる、安曇野で最も標高が低い地域である。犀川は合流部に入る手前で、梓川と奈良井川の水が合わさって名を新たにした川だ。松本平のすべての川が、この合流部で一体化するのである。水は表流水として流れ下るだけでなく、膨大な量が地中に染み、湧水としてここに現れる。

『安曇野風土記』を書いた笹本正治さんは、安曇野の水について「水は天空と私たちの世界をつなぎ、なおかつ循環しています。私たち市域の水は犀川となり、千曲川とつながり、信濃川になり、日本海に流れます。海の水は国境に規制されませんので、この水は世界とつながります」と書いている。北アルプス・常念山脈の水が潤す大地で小旅行を楽しむジジババ5人組は、信濃川の河口の街で育ったものだから、安曇野とは水で繋がっていた事になる。

さて、夜も更けて来た。人間の時間で言えば23時ころだろうか。安曇野蛙は仁義に厚い。いつまでもゲロゲロ鳴いていたのでは、迷惑を及ぼすかもしれない。俺の一声で今夜の情報交換会議は終了する。どうだ、騒めきはぴたりと止んで、全くの無音になっただろう。無音という「音」が、耳の奥で響いているのではないか。いずれにせよ都会では、味わえたくても味わえない感覚だろう。安曇野は水と音無しの世界である。おやすみなさい。(2025.6.12-13)
















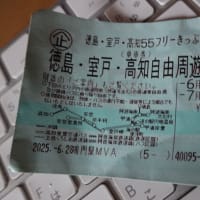



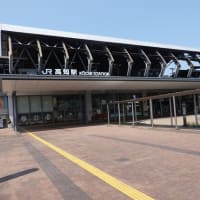










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます