
佐渡は新潟市の沖合67キロに浮かぶ日本海の離島である。面積は855.41平方キロあって、北方領土や沖縄本島を除けば日本で最も大きな島だ。子供のころ「日本で唯一の自給自足できる島」だと教わった豊かな島は、昭和30年には12万7530人の暮らしがあった。だが人口は、今は6万1000人にまで減ったという。新潟市で育った私にとって佐渡は、夕日を浴びながら眺める水平線の長い山陵であった。その佐渡を再訪した。

再方とはいっても、小学4年生の夏休みに家族でドンデン山に登って以来のことであり、50余年ぶりになる。細かいことになるが、私は新潟市に転居する前の幼児期、西蒲原の稲作地帯で育った。そこからは夕日は弥彦山に落ちた。弥彦の裏が日本海であり、佐渡は山に隠れて見えなかった。新潟市に移ってからのワンパク期は、白秋が「海は荒海 向こうは佐渡よ」と詠った砂山が遊び場となり、佐渡に日が落ちると帰宅する日々を過ごした。
 (両津港に向かう佐渡汽船から眺めた弥彦山)
(両津港に向かう佐渡汽船から眺めた弥彦山)
佐渡から「こちら」はどう見えるのか? 今回、その思いが幾分晴れた。早朝、大佐渡スカイラインを登り、佐渡最高峰の金北山(1172m)山頂に近い展望台に立って、大佐渡側から国中平野を鳥瞰した。平野は小佐渡の山並みに塞がれていて、その稜線の向こうに小さな山塊が浮かんでいた。山容からして弥彦山に違いない。なるほど、近いといえば近いけれど、平野部での暮らしから越後は見えない。見えないけれど、こんなにも近い。
 (大佐渡の北端・弾崎)
(大佐渡の北端・弾崎)
佐渡の博物館で『離島 佐渡 第2版』という本を買った。編者は地質の研究者らしく、その分野が詳しい。そこでまず世界地図からみた佐渡の生い立ちを知った。確かに太平洋は、アリューシャン列島、千島列島、日本列島、琉球諸島、マリアナ初頭、フィリピン諸島と、その西縁を弧状列島がつないでいる。さらに日本列島の日本海側には、礼文島、利尻島、奥尻島、飛島、粟島、佐渡島、隠岐島等が同じように弓なりに点在している。
 (大佐渡の南端・台ケ鼻)
(大佐渡の南端・台ケ鼻)
同書によれば男鹿半島や能登半島は「島のなり損ない」で、これらを加えれば島々の姿はより鮮明になる。つまりは地球生成に遡る気の遠くなる話になるのだけれど、佐渡もこうした地球規模の天地創造の中にあって、大陸から切り離され、しかし本州とは合体することなく点々と連なる島として定着した。最初は2つの島だった佐渡は、海進による堆積の繰り返しで間がつながった。それは弥生時代後期(1800年前)と、ごく最近のことだ。
 (小佐渡の北端・姫崎)
(小佐渡の北端・姫崎)
佐渡がこれらの島々にあって特異なのは、その大きさや独特の島姿とともに、マグマが熱水溶液を大地の割れ目に押し込み、島内に金銀鉱床を形成させた気まぐれによる。これによって佐渡は江戸時代以降、独自の歴史を刻むことになる。縄文のころから島に住みついた佐渡人の末裔は、この金銀によって潤うというより、余計な苦難を背負い込むことになった、のではないだろうか。
 (小佐渡の南端・沢崎)
(小佐渡の南端・沢崎)
離島には、ロマンチックで謎めいた雰囲気がある、と観光パンフレットは誘う。そしてそれは、日本人の海洋民族的DNAがうずくからだと講釈されたりするけれど、そんなものは「本土側」の勝手な理屈であるに違いない。佐渡の成り立ちをまず頭に入れて、島の内側から「離島の匂い」を嗅ぎ回ってみることにする。 (2013.6.4-6)


再方とはいっても、小学4年生の夏休みに家族でドンデン山に登って以来のことであり、50余年ぶりになる。細かいことになるが、私は新潟市に転居する前の幼児期、西蒲原の稲作地帯で育った。そこからは夕日は弥彦山に落ちた。弥彦の裏が日本海であり、佐渡は山に隠れて見えなかった。新潟市に移ってからのワンパク期は、白秋が「海は荒海 向こうは佐渡よ」と詠った砂山が遊び場となり、佐渡に日が落ちると帰宅する日々を過ごした。
 (両津港に向かう佐渡汽船から眺めた弥彦山)
(両津港に向かう佐渡汽船から眺めた弥彦山)佐渡から「こちら」はどう見えるのか? 今回、その思いが幾分晴れた。早朝、大佐渡スカイラインを登り、佐渡最高峰の金北山(1172m)山頂に近い展望台に立って、大佐渡側から国中平野を鳥瞰した。平野は小佐渡の山並みに塞がれていて、その稜線の向こうに小さな山塊が浮かんでいた。山容からして弥彦山に違いない。なるほど、近いといえば近いけれど、平野部での暮らしから越後は見えない。見えないけれど、こんなにも近い。
 (大佐渡の北端・弾崎)
(大佐渡の北端・弾崎)佐渡の博物館で『離島 佐渡 第2版』という本を買った。編者は地質の研究者らしく、その分野が詳しい。そこでまず世界地図からみた佐渡の生い立ちを知った。確かに太平洋は、アリューシャン列島、千島列島、日本列島、琉球諸島、マリアナ初頭、フィリピン諸島と、その西縁を弧状列島がつないでいる。さらに日本列島の日本海側には、礼文島、利尻島、奥尻島、飛島、粟島、佐渡島、隠岐島等が同じように弓なりに点在している。
 (大佐渡の南端・台ケ鼻)
(大佐渡の南端・台ケ鼻)同書によれば男鹿半島や能登半島は「島のなり損ない」で、これらを加えれば島々の姿はより鮮明になる。つまりは地球生成に遡る気の遠くなる話になるのだけれど、佐渡もこうした地球規模の天地創造の中にあって、大陸から切り離され、しかし本州とは合体することなく点々と連なる島として定着した。最初は2つの島だった佐渡は、海進による堆積の繰り返しで間がつながった。それは弥生時代後期(1800年前)と、ごく最近のことだ。
 (小佐渡の北端・姫崎)
(小佐渡の北端・姫崎) 佐渡がこれらの島々にあって特異なのは、その大きさや独特の島姿とともに、マグマが熱水溶液を大地の割れ目に押し込み、島内に金銀鉱床を形成させた気まぐれによる。これによって佐渡は江戸時代以降、独自の歴史を刻むことになる。縄文のころから島に住みついた佐渡人の末裔は、この金銀によって潤うというより、余計な苦難を背負い込むことになった、のではないだろうか。
 (小佐渡の南端・沢崎)
(小佐渡の南端・沢崎) 離島には、ロマンチックで謎めいた雰囲気がある、と観光パンフレットは誘う。そしてそれは、日本人の海洋民族的DNAがうずくからだと講釈されたりするけれど、そんなものは「本土側」の勝手な理屈であるに違いない。佐渡の成り立ちをまず頭に入れて、島の内側から「離島の匂い」を嗅ぎ回ってみることにする。 (2013.6.4-6)











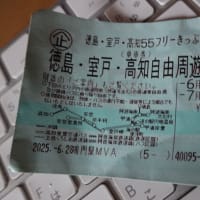



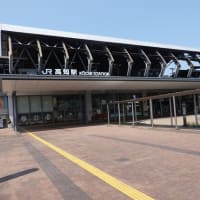










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます