
大洲の街を意識したきっかけは、中江藤樹である。琵琶湖のほとり安曇川町にこの近江聖人を訪ねた折り、若き日の与右衛門(藤樹)が仕官し、後に脱藩した地であると知ったからだ。脱藩は重罪のはず。しかし与右衛門はその後、郷里で私塾を開き、41年の天寿を全うしている。それを黙認した大洲とはどのような土地なのか、歩いてみたいと思ってきた。肱川のほとりの小盆地。南予地方北部の、松山と宇和島の中間にある街だった。

大洲の市街地を一回りして、感じたのは「心地よさ」である。港町・宇和島からやって来たからだろうか、大漁旗の喧騒はなく、内陸部だから潮の香も遠い街は、爽やかな風が吹き抜けているような静けさがある。人口は44000人ほど。宇和島の6割程度だから、藩政時代の宇和島10万石と大洲6万石がそのまま街の規模となって今も続いているかのようだ。城跡の丘に登ると、肱川が大きな石の河原を形成しながら蛇行して行く。

夏が終わるころになると、大洲市民は毎年、こうした肱川の河原で「いもたき」の宴を開く。特産の里芋で、強い粘りが特色だという「夏芋」を大鍋で煮て、大勢で月を愛でながら楽しむのだ。山形の「芋煮会」と似ている催しだが、こちらは出汁をイリコでとることが特色らしい。伊予のことだから、あちこちの宴席で句会も開かれているかもしれない。静かな街で、季節を味わいながら夜長を過ごす、地方の、羨ましい暮らしがある。

さて与右衛門さん。城跡の丘を登っていくと、一目でそれとわかる坐像を見つけた。大洲には「大洲藤樹会」という組織があるようで、碑文には「大洲は、先生が10歳から27歳まで過ごされた立志・感恩・勉学の地である。大洲の人々は、先生ゆかりの地として、その学徳を追慕し、藤樹先生の心をいつまでも継承しようと、この城山に銅像を建立した」とある。脱藩者でありながら、ここでもこれほど尊崇されている事に驚き、安堵する。

陽明学者・中江藤樹(1608-1648)の教えには、やたらと知、徳、恩といった言葉が頻発し、凡々と生きる私などは辟易とさせられる。ただ人間とは、多くの人々に感銘を与え、聖人と称えられるほどの存在に成り得るのだ、ということを実証した人物として、藤樹の人格は興味深い。母孝行のため脱藩を決行した藤樹は、大洲藩にとっては藩を街を知己を捨てた裏切り者であろう。しかしそれでも追慕されるその人柄は、ただ感動である。

街を見晴らす城山で、最も清々しく感じたのは3本のケヤキだった。復元された天守の広場で、枝を大きく広げて立っている。もともとここに生えていたものか、城山の整備に伴って移植されたものかは分からない。ただこの盆地の真ん中の丘の上で、肱川を渡ってくる川風を柔らかく受け止め、涼やかな葉ずれの音に変えて街に送り出しているような、そんな気持ちにさせられる。城山の一角では、発掘調査の現地説明会が開かれていた。

街を廻ると、かわいい女の子二人が、かわいいヘルメットをかぶって道路左側を1列になり、自転車を走らせて行く。藤樹が仕えた大洲藩加藤家は学問を好む傾向があったそうで、それが幕末には勤皇の旗幟を鮮明にし、坂本龍馬の海援隊を支援するなどの動きにつながっていったのだろう。街に沈潜するそうした気風が、いまの子供たちをもきちんと育てているように感じる。滞在時間は限られていたけれど、いい街を知った。(2016.10.8)


大洲の市街地を一回りして、感じたのは「心地よさ」である。港町・宇和島からやって来たからだろうか、大漁旗の喧騒はなく、内陸部だから潮の香も遠い街は、爽やかな風が吹き抜けているような静けさがある。人口は44000人ほど。宇和島の6割程度だから、藩政時代の宇和島10万石と大洲6万石がそのまま街の規模となって今も続いているかのようだ。城跡の丘に登ると、肱川が大きな石の河原を形成しながら蛇行して行く。

夏が終わるころになると、大洲市民は毎年、こうした肱川の河原で「いもたき」の宴を開く。特産の里芋で、強い粘りが特色だという「夏芋」を大鍋で煮て、大勢で月を愛でながら楽しむのだ。山形の「芋煮会」と似ている催しだが、こちらは出汁をイリコでとることが特色らしい。伊予のことだから、あちこちの宴席で句会も開かれているかもしれない。静かな街で、季節を味わいながら夜長を過ごす、地方の、羨ましい暮らしがある。

さて与右衛門さん。城跡の丘を登っていくと、一目でそれとわかる坐像を見つけた。大洲には「大洲藤樹会」という組織があるようで、碑文には「大洲は、先生が10歳から27歳まで過ごされた立志・感恩・勉学の地である。大洲の人々は、先生ゆかりの地として、その学徳を追慕し、藤樹先生の心をいつまでも継承しようと、この城山に銅像を建立した」とある。脱藩者でありながら、ここでもこれほど尊崇されている事に驚き、安堵する。

陽明学者・中江藤樹(1608-1648)の教えには、やたらと知、徳、恩といった言葉が頻発し、凡々と生きる私などは辟易とさせられる。ただ人間とは、多くの人々に感銘を与え、聖人と称えられるほどの存在に成り得るのだ、ということを実証した人物として、藤樹の人格は興味深い。母孝行のため脱藩を決行した藤樹は、大洲藩にとっては藩を街を知己を捨てた裏切り者であろう。しかしそれでも追慕されるその人柄は、ただ感動である。

街を見晴らす城山で、最も清々しく感じたのは3本のケヤキだった。復元された天守の広場で、枝を大きく広げて立っている。もともとここに生えていたものか、城山の整備に伴って移植されたものかは分からない。ただこの盆地の真ん中の丘の上で、肱川を渡ってくる川風を柔らかく受け止め、涼やかな葉ずれの音に変えて街に送り出しているような、そんな気持ちにさせられる。城山の一角では、発掘調査の現地説明会が開かれていた。

街を廻ると、かわいい女の子二人が、かわいいヘルメットをかぶって道路左側を1列になり、自転車を走らせて行く。藤樹が仕えた大洲藩加藤家は学問を好む傾向があったそうで、それが幕末には勤皇の旗幟を鮮明にし、坂本龍馬の海援隊を支援するなどの動きにつながっていったのだろう。街に沈潜するそうした気風が、いまの子供たちをもきちんと育てているように感じる。滞在時間は限られていたけれど、いい街を知った。(2016.10.8)











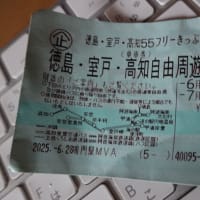



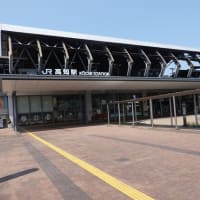










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます