
タイ国政府観光庁から送ってもらったチェンマイの案内書には「北方のバラと呼ばれるタイ第2の都市」だとある。また、世界のどの街とも異なる「弛緩した上品さ」に包まれた独特の雰囲気があると紹介している書もある。しかし1辺が1.6キロほどの正方形の城壁に囲まれた旧市街を歩く私には、思考が、吹き出す汗に弛緩するだけで、バラを連想する雰囲気はどうにもつかみ取ることができない。余りの暑さと埃っぽさに負けたのである。

しかし「壮麗なランナー王朝の歴史と広大な自然が織りなす独自の北部文化は、世界中の観光客を魅了し続けています」と詠う観光庁が大袈裟かというと、そうでもない。街にはアジア系以上に白人観光客が目立ち、はち切れんばかりの肉体を薄着に包んで、汗だくになって寺院を訪ね歩く女子大生らが狭い歩道を闊歩している。私も郊外まで足を延ばせばもっと魅力に触れることができたのだろうが、ホテルの冷房が恋しい日々だった。

タイの歴史は案外に新しい。ユーラシア大陸の東南隅に突き出し、南シナ海とベンガル湾を分かつインドシナ半島に、「王国」らしき存在が生まれ始めたのは2000年ほど前に遡るらしい。インドと中国という、二つの巨大文明に挟まれたこの地は、モンスーンを利用した航海術が進歩すると、巨大文明の交易中継地として夜明けを迎え、点々と初期の国家が誕生した。王権の根拠をインド文化に求めた、半島の「インド化時代」である。

東南アジアの古代史以降、大陸部で最も繁栄したのはクメール人によるアンコール時代である。このころ「タイ人」の先民たちはまだ中国南部の山岳地帯に蟠踞していた。何が契機だったのだろう、彼らは12世紀を経るころ、幾筋もの川を南下、小さなムラを形成し始める。やがて連携してクメール支配を脱し、タイ中部のスコータイに「タイ人」による初の王国を樹立するのが13世紀のことだ。そしてチェンマイがタイ史に登場する。

ランナー王国がタイ北部からその周辺国にまで勢力を広げ、チェンマイに王都の繁栄を確立したのは15世紀半ば。王権の根拠が仏教の守護者にあることから、歴代の王たちは競うように寺院を建立した。だから狭い城塞の内は寺院がひしめいている。そこへの車の乗り入れを禁じる案が出されているそうだが、一般の生活者も暮らしていて難しい問題だと聞いた。歩道を整備し、車を閉め出したら、古都の佇まいはいい方向に向かうだろう。

チェンマイは第2の都会だそうですね、と訊くと、街の人は首を傾げ「5番目くらいかな?」と答えた。工業団地の進出などで、人口を増やす街が続出しているのだろうか。この街に暮らす日本人は、日本人会で把握されているだけで3000人ほど居るという。ビジネスのほかロングステイや冬場の避寒と目的は様々だが、「夫婦の方々は歓迎されますが、男性一人で、というケースは嫌われます」と聞いた。悪習がまだあるのだろう。

書棚に眠っていた『東南アジア紀行』(梅棹忠夫著、中央公論社)を読んだ。1957年に実施された大阪市立大学調査隊の道中記である。チェンマイのことを「なんという明るい、ゆったりとした町だろうか」と書いている。そして「戦時は3万人の日本兵が駐屯していたというが、いまはたった3人だ」とも。日本人が国連職員として漆器技術を教え、チェンマイの工芸は飛躍的に進歩しているという。50年前のことである。(2016.3.23-25)


しかし「壮麗なランナー王朝の歴史と広大な自然が織りなす独自の北部文化は、世界中の観光客を魅了し続けています」と詠う観光庁が大袈裟かというと、そうでもない。街にはアジア系以上に白人観光客が目立ち、はち切れんばかりの肉体を薄着に包んで、汗だくになって寺院を訪ね歩く女子大生らが狭い歩道を闊歩している。私も郊外まで足を延ばせばもっと魅力に触れることができたのだろうが、ホテルの冷房が恋しい日々だった。

タイの歴史は案外に新しい。ユーラシア大陸の東南隅に突き出し、南シナ海とベンガル湾を分かつインドシナ半島に、「王国」らしき存在が生まれ始めたのは2000年ほど前に遡るらしい。インドと中国という、二つの巨大文明に挟まれたこの地は、モンスーンを利用した航海術が進歩すると、巨大文明の交易中継地として夜明けを迎え、点々と初期の国家が誕生した。王権の根拠をインド文化に求めた、半島の「インド化時代」である。

東南アジアの古代史以降、大陸部で最も繁栄したのはクメール人によるアンコール時代である。このころ「タイ人」の先民たちはまだ中国南部の山岳地帯に蟠踞していた。何が契機だったのだろう、彼らは12世紀を経るころ、幾筋もの川を南下、小さなムラを形成し始める。やがて連携してクメール支配を脱し、タイ中部のスコータイに「タイ人」による初の王国を樹立するのが13世紀のことだ。そしてチェンマイがタイ史に登場する。

ランナー王国がタイ北部からその周辺国にまで勢力を広げ、チェンマイに王都の繁栄を確立したのは15世紀半ば。王権の根拠が仏教の守護者にあることから、歴代の王たちは競うように寺院を建立した。だから狭い城塞の内は寺院がひしめいている。そこへの車の乗り入れを禁じる案が出されているそうだが、一般の生活者も暮らしていて難しい問題だと聞いた。歩道を整備し、車を閉め出したら、古都の佇まいはいい方向に向かうだろう。

チェンマイは第2の都会だそうですね、と訊くと、街の人は首を傾げ「5番目くらいかな?」と答えた。工業団地の進出などで、人口を増やす街が続出しているのだろうか。この街に暮らす日本人は、日本人会で把握されているだけで3000人ほど居るという。ビジネスのほかロングステイや冬場の避寒と目的は様々だが、「夫婦の方々は歓迎されますが、男性一人で、というケースは嫌われます」と聞いた。悪習がまだあるのだろう。

書棚に眠っていた『東南アジア紀行』(梅棹忠夫著、中央公論社)を読んだ。1957年に実施された大阪市立大学調査隊の道中記である。チェンマイのことを「なんという明るい、ゆったりとした町だろうか」と書いている。そして「戦時は3万人の日本兵が駐屯していたというが、いまはたった3人だ」とも。日本人が国連職員として漆器技術を教え、チェンマイの工芸は飛躍的に進歩しているという。50年前のことである。(2016.3.23-25)











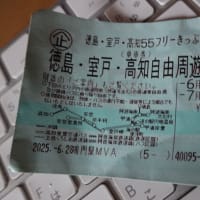



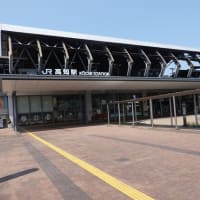










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます