
全国ニュースで取り上げられるほど、中山道・妻籠(つまご)宿が外国人観光客で賑わっていることは承知していた。しかし実際にやって来て、「こんなにも!」と驚いている私である。英独仏に中国語、さらには東南アジアのどこかの言葉やロシア語らしき会話が「山の中」で交錯している。これでは宿泊予約が取れないのも当然かと納得するのだが、それにしても皆さん、何を求めてわざわざここまでやって来るのだろう。不思議な思いで立ち止まる。

そもそも「宿場」とは何か。人の移動は縄文時代から結構活発だったことが確認されているが、江戸時代になって整備された中山道は、官制の国道である。旅人に休息や宿泊の場を提供し、貨物の輸送を繋ぐ場でもある。幕府に任命された問屋が世襲で本陣や脇本陣を構え、防御拠点の役も担っていた。妻籠観光協会の資料によれば、江戸開幕とともに設置された妻籠宿は、標高420メートルほどの河岸段丘上に、30軒余の旅籠が軒を連ねていたという。

同じ木曽路にあっても、奈良井千軒と謳われた奈良井宿などに比べると、妻籠の規模はだいぶ小さい。ただ伊那地域への追分という立地もあって、ずいぶん賑わったらしい。時代が明治になって近代交通ルートから外れると、当然ながら段丘上の宿場は無用となり、他にこれといった産業の無い妻籠は急速に衰退していく。しかし妻籠の衆は踏ん張った。行政や企業を巻き込み、古い家並みを観光資源として復元保存しようと立ち上がったのである。

そして町家を解体修理し、石畳や道標を整備した。電柱などは宿場の裏に隠し、江戸期の風情を出現させた。長い準備と活動の成果として1976年、妻籠宿は国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された。今では全国126地点に及ぶ保存地区の、秋田・角館の武家町などとともに選定第1号だった。文化財保護の思想が景観保全にも広がる先駆けであり、「売らない・貸さない・壊さない」を申し合わせた土地人の思いは、宿場の奥行きを深めている。
 (沖縄・竹富島の重要伝統的建造物群保存地区.2008.4.6)
(沖縄・竹富島の重要伝統的建造物群保存地区.2008.4.6)
15年ほど前、沖縄県竹富島に旅した際、竹富島憲章を目にした。「売らない・汚さない・乱さない・壊さない・生かす」とあった。竹富島の農村集落も妻籠宿の10年後、保存地区に選定されている。住民が自らの意思で、こうした暮らし方を選んでいることを知ると、その土地が好きになる。と、日本人の私ならそんな気分になる集落だが、果たして遠来のお客さんたちは、この黒く古びた家並みを眺めて何を思うだろうか、と、また不思議になる。

だが主に欧米系の観光客の、トレッキングスタイルが多いことに気づいて不思議が解けた。伝統的建造物以上に、彼らは緑したたる自然の中を歩きたいのだ。例えば妻籠から馬籠宿は7.3キロで2時間ほどの行程だ。200メートル余の高低差はむしろ好もしいとする強者たちである。その道がかつての街道であり、そのうえサムライの歴史が堆積していると、上手に紹介するガイドブックがあるのだろう。軟弱な私は、急峻な馬籠峠をバスで越える。

妻籠宿の入口に、レンゲで埋まる広場があった。「僕はレンゲとツクシとフキノトウが好きです。一番好きなのはレンゲです」と小学1年生の作文に書いた私は、45歳の大和路歩きで當麻寺近くのレンゲ畑に迷い込んだ。二上山を背景に恍惚とする大和憧憬病患者(私)の写真を思い出し、レンゲの中に座ってセルフタイマーをセットした。向こうを行く外国人女性が笑顔で私に手を振っている。前夜の妻籠は雨だったのか、尻が濡れた。(2023.4.19)











そもそも「宿場」とは何か。人の移動は縄文時代から結構活発だったことが確認されているが、江戸時代になって整備された中山道は、官制の国道である。旅人に休息や宿泊の場を提供し、貨物の輸送を繋ぐ場でもある。幕府に任命された問屋が世襲で本陣や脇本陣を構え、防御拠点の役も担っていた。妻籠観光協会の資料によれば、江戸開幕とともに設置された妻籠宿は、標高420メートルほどの河岸段丘上に、30軒余の旅籠が軒を連ねていたという。

同じ木曽路にあっても、奈良井千軒と謳われた奈良井宿などに比べると、妻籠の規模はだいぶ小さい。ただ伊那地域への追分という立地もあって、ずいぶん賑わったらしい。時代が明治になって近代交通ルートから外れると、当然ながら段丘上の宿場は無用となり、他にこれといった産業の無い妻籠は急速に衰退していく。しかし妻籠の衆は踏ん張った。行政や企業を巻き込み、古い家並みを観光資源として復元保存しようと立ち上がったのである。

そして町家を解体修理し、石畳や道標を整備した。電柱などは宿場の裏に隠し、江戸期の風情を出現させた。長い準備と活動の成果として1976年、妻籠宿は国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された。今では全国126地点に及ぶ保存地区の、秋田・角館の武家町などとともに選定第1号だった。文化財保護の思想が景観保全にも広がる先駆けであり、「売らない・貸さない・壊さない」を申し合わせた土地人の思いは、宿場の奥行きを深めている。
 (沖縄・竹富島の重要伝統的建造物群保存地区.2008.4.6)
(沖縄・竹富島の重要伝統的建造物群保存地区.2008.4.6)15年ほど前、沖縄県竹富島に旅した際、竹富島憲章を目にした。「売らない・汚さない・乱さない・壊さない・生かす」とあった。竹富島の農村集落も妻籠宿の10年後、保存地区に選定されている。住民が自らの意思で、こうした暮らし方を選んでいることを知ると、その土地が好きになる。と、日本人の私ならそんな気分になる集落だが、果たして遠来のお客さんたちは、この黒く古びた家並みを眺めて何を思うだろうか、と、また不思議になる。

だが主に欧米系の観光客の、トレッキングスタイルが多いことに気づいて不思議が解けた。伝統的建造物以上に、彼らは緑したたる自然の中を歩きたいのだ。例えば妻籠から馬籠宿は7.3キロで2時間ほどの行程だ。200メートル余の高低差はむしろ好もしいとする強者たちである。その道がかつての街道であり、そのうえサムライの歴史が堆積していると、上手に紹介するガイドブックがあるのだろう。軟弱な私は、急峻な馬籠峠をバスで越える。

妻籠宿の入口に、レンゲで埋まる広場があった。「僕はレンゲとツクシとフキノトウが好きです。一番好きなのはレンゲです」と小学1年生の作文に書いた私は、45歳の大和路歩きで當麻寺近くのレンゲ畑に迷い込んだ。二上山を背景に恍惚とする大和憧憬病患者(私)の写真を思い出し、レンゲの中に座ってセルフタイマーをセットした。向こうを行く外国人女性が笑顔で私に手を振っている。前夜の妻籠は雨だったのか、尻が濡れた。(2023.4.19)




















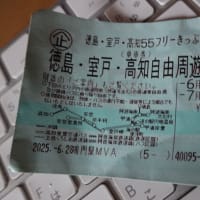



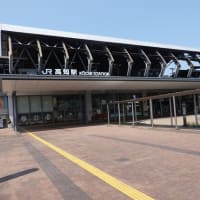










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます