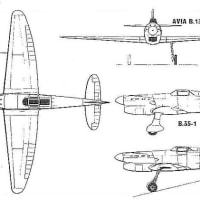西尾氏ほどの知識人がどうしてこんなに誤解をしているかと不可解に思うことが一点だけある。日米戦争や日独戦争を望んでいたのは、ルーズベルト大統領と、政府中枢だけであり、国民はこぞって反戦であったと信じていることである。
以前「ルーズベルトの責任」という本の紹介で、欧州大戦が始まって英国が危なくなると、米国は中立法を改正して、武器貸与や独潜攻撃などの行為をしたことを批評した。これらの事は完全な戦争行為であって、マスコミでも堂々と公表されているが、国民も議会もマスコミもこれに反対した形跡は極めて少ない。国際法学者ですら、米政府の行為が戦争行為だと批判していない。つまり国民も議会もマスコミも政府が次々と打ち出す戦争行為を是認していたと言うことは戦争に反対ではなかったのだ。確かに世論調査をすれば戦争反対の声が強かったのは事実である。これは単に戦争に賛成しますか、と聞かれれば国民は、建前で反対というのである。
本書でも西尾氏はルースベルト政府が次々と援英のために戦争にのめりこむ政策を実行していることを書いている。また日本爆撃の準備をし、実行のためにフライングタイガースという戦闘機部隊を送り込んでいたことも知られている。それでもなぜ国民は戦争反対であったと言う結論が出るのか、聡明な西尾氏にしては不可解なのである。ルーズベルトの戦争政策はマスコミや議会を通じて公表されているのである。武器貸与法などは多数の議員によって支持されている。それならば議員の支持者は戦争反対だと議員を追求しないのだろうと考えればことは簡単である。
この本の主眼は、国際連盟は結局英国の世界覇権の維持のためにあったのであって、そのバックには連盟に入っていもしないのに、英国の世界覇権のあとがまを狙う米国がいたということであろう。それにしても、日本は連盟脱退後もしばらくは分担金を払っていた(P156)というのだから今も昔も日本人の性格は変わらないのだと考えさせられる。
もうひとつの眼目は、米英はヒトラーのドイツ憎し、のためにソ連と手を組んだことは許し難い誤りであった(P310)というのである。日本に対しては合法的平和的仏印進駐にさえ禁輸政策をとったのに、バルト三国併合やフィンランド侵略という阿漕な事をしてもかえってソ連に対して融和的にでているのである。