青春の輝き かあいがもん
先日ヤフーニュースで河相我聞さんのブログを知って、我聞さん懐かしいな~と読み始めたら意外な文才に思わず全部読んでしまった(我聞さんのブログはamebloとはてなブログの2つあります)。
その中にこんな記事がありまして、我聞さんはご自身が出演されたドラマ『未成年』の主題歌だった「青春の輝き」が大好きなのだそうで、それをカバーするためだけになんとピアノとボイストレーニングと英会話のレッスンまでしてしまったそうです 。
。
ドラマ『未成年』。
1995年、私が大学一年生のときのドラマで、我聞さんを始め主役の役者さん達も私と同年代でした。
懐かしいというより、今でも時々現在進行形で思い出す、私にとって特別なドラマです。このブログでも以前ご紹介しました。
主題歌は「I Need To Be In Love(青春の輝き)」、「Top of the World」、「Desperado」など全てカーペンターズの曲。
ていうか「この曲を歌いたい」という気持ちだけでピアノや英会話までやってしまう我聞さん、ナイス。
わたくし、こういう人、好きです。
ご本人曰くこのカバーはまだ発展途上とのことで、確かにちょっとぎこちない感じはあるけど、我聞さんの声、優しくて透明感があっていいね。最後の笑顔もよい (我聞さんはリクエストで「青春の影」カバーや「香水」カバーも歌われていて、とても素敵なので皆さん是非聴いてください。「香水」はどうしてこの曲がそんなに人気があるのか全くわからないわたくしですが、我聞さんのカバーはよい。しかしかっこいいお父さんだなあ。)
(我聞さんはリクエストで「青春の影」カバーや「香水」カバーも歌われていて、とても素敵なので皆さん是非聴いてください。「香水」はどうしてこの曲がそんなに人気があるのか全くわからないわたくしですが、我聞さんのカバーはよい。しかしかっこいいお父さんだなあ。)
こちら↓は、ドラマの主題歌でもあった本家カーペンターズの「I Need To Be In Love」。
Carpenters - I Need To Be In Love
この曲は生前カレンが最も気に入っていた曲だそうです。
切ない曲ですよね。前向きにもとれる歌詞ではあるけれど、カレンの人生を思うと、繰り返される「I know(わかっているの)」がすごく切なく響く。
imperfectなのが人間の世界。
そういう世界に生れ落ちてしまったimperfectな生き物である私達は、この場所で精一杯に生きていく以外にない。愛を求めながら・・・。
そしてコロナ禍の中、ドラマの主役だったいしだ壱成さんがyoutubeにこんな動画↓をあげてくださいました。
「再現か…」と正直、見る前は不安半分だったのですが(私にとって特別すぎるドラマなので)、、、
【神回】未成年のあの名場面を再現しました【いしだ壱成】
壱成さ~ん




懐かしいというより、今の壱成さんが今のご自分の言葉として言っているように聞こえて、沁みる。。。。。
ご自身も朗読後に「思い出すし、なんかこう、回る感じがします」と仰っているけれど、本当にそんな感じがする。
人も人生も、まわっているんだなあ。
そして生きていれば、25年が過ぎて、こういう動画に巡り合えることもあるのだなあ。
壱成さん、これまで色々なことがあったけど、いま、とてもいい表情をされていますね。
ところで最終回のあの屋上シーン、裏話で仰っていましたが、なんと本番ではなくカメラテスト(本番前のカメラの位置や音声を確認するためのテスト)でOKが出たのだそうです。なので脚本の1ページ分くらいがとんでいるんですって。ていうかカメラテストなのにあんな演技をしていた壱成さんに吃驚です。俳優さんってすごい・・・。
ドラマ 未成年 ただそいつらはそうなりたかっただけ
ドラマの別の1シーン。
これも大好きなシーンです。
このドラマの壱成さん、ほんと素晴らしいよね。天性の演技というか、無双だと思う。
野島脚本もこの頃は無双だったし、改めて奇跡のようなドラマだったなあ。
でも”今の壱成さん”の演技も、いつか見られたらいいな。
頑張っては禁句なのかもしれないけど、頑張ってほしいなと心から思ってしまう。応援しています。
私の生活している沿線では毎日人身事故が起きています。
私自身がややもすれば死に惹かれてしまう人間なので強いことは何も言えないけれど、みんな、ずっとなんて考えなくていいから、とりあえず目の前の一日を踏ん張って生きよう。嫌なことは全部投げ出していいから、どんなこともなるようになるから心配しすぎないで、とりあえず、今日は生きていよう。どんなに自分を嫌いになりそうでも、一緒に頑張ろう。
【未成年】当時の撮影秘話【いしだ壱成】
【共演者との想い出】未成年より香取慎吾くん【いしだ壱成】
【歌姫あゆ】共演者との思い出【いしだ壱成】
【初コラボ】中年になった今!ジュンペイと未成年を語り尽くす【北原雅樹】
【北原雅樹】未成年の裏話を喋り尽くす【いしだ壱成】




















 。大変よかった。
。大変よかった。



 ?
?







 。
。
 。気が遠くなるような作業ですよね。私も少しは見習わないとなあ、とそのときは思うのですけれど、なかなか。。。
。気が遠くなるような作業ですよね。私も少しは見習わないとなあ、とそのときは思うのですけれど、なかなか。。。



 。漱石自身も身なりを気にするお洒落な人で、美しいものが好きな人でした。
。漱石自身も身なりを気にするお洒落な人で、美しいものが好きな人でした。 。「
。「
 」を言い渡されたそうで、「5月いっぱいは休む気満々だったのに
」を言い渡されたそうで、「5月いっぱいは休む気満々だったのに (仕事はちゃんとしてますよ)
(仕事はちゃんとしてますよ)



 !蜆川に浮かぶ小舟、水面に映る月影、座敷から漏れる灯り、人々の喧噪・・・
!蜆川に浮かぶ小舟、水面に映る月影、座敷から漏れる灯り、人々の喧噪・・・
 と歌いながら”不孝糖”を売り歩く万吉はん。
と歌いながら”不孝糖”を売り歩く万吉はん。 」「おはちゅ~
」「おはちゅ~

 、とも。
、とも。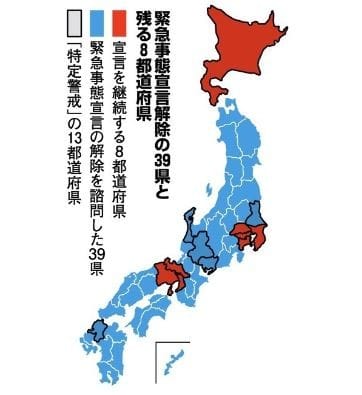
 。
。 」と力強く否定されたことがあります笑。
」と力強く否定されたことがあります笑。 !
!
 (
(



 と見つけて、第1シリーズから第3シリーズまでを全編一気見したのでありました。
と見つけて、第1シリーズから第3シリーズまでを全編一気見したのでありました。


