
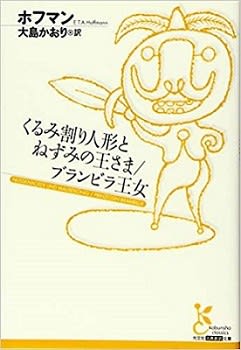
仕事が忙しくて吐きそう。超安月給なのに、納得いかん。しかし転職しても(そもそもできるかという問題もあるが)そう状況はカワラナイのではないかとも思う。うちの会社は超低給であることを除けば、おそらくそこまでブラックではないので。。
100年前に漱石が『草枕』で書いた言葉が沁みる。
住みにくさが高じると、安い所へ引き越したくなる。どこへ越しても住みにくいと悟った時、詩が生れて、画が出来る。
人の世を作ったものは神でもなければ鬼でもない。やはり向う三軒両隣にちらちらするただの人である。ただの人が作った人の世が住みにくいからとて、越す国はあるまい。あれば人でなしの国へ行くばかりだ。人でなしの国は人の世よりもなお住みにくかろう。
越す事のならぬ世が住みにくければ、住みにくい所をどれほどか、寛容(くつろげ)て、束の間の命を、束の間でも住みよくせねばならぬ。ここに詩人という天職が出来て、ここに画家という使命が降(くだ)る。あらゆる芸術の士は人の世を長閑にし、人の心を豊かにするが故に尊とい。
宮崎駿監督は、サン=テグジュペリの『人間の土地』(新潮文庫)に寄せた文章でこう書いた。
「日常だけでは窒息してしまう」。
詩的世界と日常世界。空想世界と現実世界。理想世界と現実世界。人間以外の全ての者達にとって、おそらくそれらの世界の間に境はないのだと思う。人間だけがその二つの世界を意識し、行き来する。そしてそのあわいの場所で、様々な芸術が生まれる。その往来に時に心遊ばせ、時に憩い、時に恐れ、時にその間で引き裂かれた人達が遺してくれたものが、今日も私の日常を慰める。
先月、新国立劇場バレエ団の『コッペリア(ローラン・プティ版)』のネット配信を観たんです。私が観たのは小野絢子さんの日で、小野さんの踊りは初めて観たけれど素晴らしいダンサーだなぁ!と感嘆したり、一方でプティのエスプリ味を表現するのは日本人ダンサーには難しいというSNSの感想を読んで、なるほどとも実感したり。プティの作品って以前も観たことがあるけれど、エスプリ感が本当に重要ですよね。日本人が踊るとただ「可愛い」だけになりがちで、ハードルが高い。。。
しかし私が何より衝撃だったのは、「なんだこの話・・・ 」ということでした。
」ということでした。
『コッペリア』ってこんな話だったのか、と(初めて観たんです)。
こんなストーリーを思い浮かぶ作家の頭の中って一体どうなっているのだろう??と気になり調べたところ、原作はE.T.A.ホフマンの『砂男』とのこと。ホフマンは200年前のドイツの作家で、チャイコフスキーのバレエ『くるみ割り人形』や、オペラ『ホフマン物語』(私は未見)などで有名。シューマンの『クライスレリアーナ』も、ホフマンの同名の小説に触発されて作曲されたそうです。wikipediaでは「後期ロマン派を代表する幻想文学の奇才」と紹介されています。
光文社古典新訳文庫から新訳が出ていたので早速図書館で借り、『砂男』、『クレスペル顧問官』、『大晦日の夜の冒険』、『くるみ割り人形とねずみの王さま』、『ブランビラ王女』の5作を読んでみました。
いやぁ、世の中にこんな奇妙な物語が存在したとは。。。。。
本当に世界は知らないことだらけ。
今回読んだ5作、どれもホフマン独特の感性が溢れていて面白かったけれど、とりわけ『ブランビラ王女』の印象が強烈でした。粗筋の紹介もしようがない、読んでいて頭がおかしくなりそうな、作家がどういう思考の流れで書いたのか想像もつかないような物語なんだけど、その迷宮に迷い込んだまま放られる感じがなんだかクセになるというか、頭から離れなくなる。そういう感じって、シューマンの音楽にもありますよね。シューマンがホフマンに傾倒したのがわかる気がする。
『ブランビラ王女』の主人公は若い青年の役者ですが、「ホフマンと演劇」についてググってみたところ、こんなページ↓が出てきました。
「E.T.A. ホフマン『ある劇場監督の奇妙な悩み』について」(田辺真理)
ホフマンはシェイクスピアの戯曲が好きだったようで、確かにシェイクスピアのあべこべの世界が生み出す混乱や皮肉、にもかかわらず根底に流れる世界の調和、そして失われることのない冷徹な視点はホフマンの作品と通じるところがあるように思う。
この地上における全存在の茶番を認識し、そのような認識を楽しむ、それがフモールなのです。
(『ブランビラ王女』)
ホフマンが描いた幻想世界と現実世界との行き来の物語には、常に根底に「ここ(現実世界)で生きていかねばならない私達」という認識があるように感じる。それは決してネガティブな意味だけではなく、「それが避けられないことであるならば、では私達はこの場所でどう生きるか」と現実世界に対峙する姿勢も垣間見え、それはおそらくホフマンがリアリストの視点を常に失わない人だったからなのでしょう。
『ブランビラ王女』の中で語られる「イロニー」と「フモール」(英語のアイロニーとユーモアですね)という概念が私には馴染みが薄かったので、少し調べてみました。
これ(=フモール)を、イロニー(アイロニー)Ironieと並ぶ基本的な芸術的意識態度として取り上げたのは、ドイツ・ロマン派の詩人ジャン・パウルである。彼はその著『美学入門』(1804)のなかで、これを「ロマン的滑稽(こっけい)」であり、「転倒した崇高」であるとしている。それは通常の揶揄(やゆ)のように個々の愚者や愚行をあげつらうのではなく、理念と対比された人類全体、現実の世界全体の愚かしさを際だたせる。それはまた、単に偉大なものをおとしめるパロディーParodieや、卑小なものから出発して偉大なものへと高まるイロニーとは異なって、これら偉大と卑小のいずれも、無限なものの前ではいっさいが等しく無であるとみる。そしてその限りで、個々の人間の愚かさも、愛すべき滑稽として受け入れる。ここではしたがって、滑稽とまじめ、喜劇的なものと崇高、笑うべきものとそれへの愛惜の感傷とが入り混じっている。
(日本大百科全書「フモール」)
さらに、こんなページ↓も。
ホフマンの『チビ助ツァヘス』と漱石の『吾輩は猫である』を重ね、両作品におけるイロニーとフモールについて書かれています。少し長いですが、イロニーとフモールの概念がわかりやすく、『吾輩〜』についての視点も面白かったので、覚書として引用させていただこうと思います(引用が長すぎて梅内先生に怒られちゃうかな )。
)。
ソクラテスの用いたイロニーの図式を考察してみるとき、次のような手続きが踏まれていることが分かる。まず第一に、話し手は、偽装という手段を用いて、つまり自分を無知なる者と称して低い立場に置き、同時に相手を高い立場に置くことによって、相手の警戒心を解除させ、現実世界の論理から抜けださせる。第二に、話し手は、相手に現実の世界を超えた理想の世界を対峠させ、これを認知させるのである。この図式は、簡略にすれば、テーゼーアンチテーゼージンテーゼという弁証法的発展として捉えられるであろう。
しかし、このイロニーの弁証法的発展経過においては、次の三つの構成要素が看過されてはならない。
一、話し手は、相手よりも高い認識をもっている。
二、相手は、話し手の高い認識を受け入れるだけの認識力をもっている。
三、ジンテーゼは、決して理想 (イデー) そのものとしては実現されない。
•••
イロニーの機能の本質は、テーゼに対して理想的なアンチテーゼを提示することによって、テーゼとアンチテーゼとを融合したジンテーゼを導きだすところにある。このジンテーゼが安定すると、やがてこれは再びテーゼとなり、これに新たなアンチテーゼが対峙させられることになる。このようにして、弁証法的発展が螺旋状に繰り返されるのである。しかしながら、最終的ジンテーゼである理想ないしイデーは、決して到達されることはありえない。従って、イロニーは、実現されることのありえない理想に向かって、永遠にテーゼに対してアンチテーゼを提示してゆく図式から逸脱できないのである。この意味において、時として弱く、はかない地上的存在にとってイロニーは、非情とも、冷酷とも見えかねない。最終的に、理想そのものを地上化することは不可能なのである。ここに至ると、理想的なものを地上化する機能をもつものがフモールであると考えられるのである。
地上的存在である人間が、イロニーの図式によって天上的存在にまで駆り立てられるとき、そこにはやはり、非人間的な状況が生まれると思われる。つまり、地上的存在である人間は、その生命の大前提として空気を、そして水を必要とする。ところが、天上に近づくと、空気は希薄になり、水分も少なくなり、さらに上昇すると、真空の状態になって、人間は生きてゆくことができなくなる。肉体をもつ人間は、イデーの中に生きることはできないのである。そこまでしてイデーを追求することは、生身の人間には求められていない。この極端に進むイロニーの軌道を修正し、天上への方向性を再び地上へと向けて、地上での理想を実現させるものが、フモールに他ならない。この意味において、フモールは、イロニーを前提として生まれるものであると言って差し支えないであろう。
厳しい批評眼からすると、このようなフモールは、一種の妥協という印象を受けるかも知れない。しかし、それは妥協というよりは、むしろ現実と理想の「調和」と呼ぶべきである。あるいは、人類の「智恵」とも呼びうるかも知れない。
そして『吾輩〜』の猫は「勇気をもって、完全に自由な個人主義的立場から、西洋文明を模倣しようとする当時の文化人たちを批判するのである。猫の批判は、超越的なものであって、人間の側からの批判は全く受け付けない。この意味において、猫の批判は、一方通行的なものであって、現実を正反対に映しだす「イロニーの鏡」の機能を果たしている。漱石は、『ガリバー旅行記』に見られるスウィフトの容赦なき諷刺ないしイロニーを高く評価していたと言われる。とはいっても、猫の諷刺ないしイロニーは、スウィフトのそれと比べると、それほど徹底したものではない。つまり、猫のイロニーは、完全に冷たいものではなく、そこには常に一抹の温かみと湿り気、すなわちフモールが潜んでいるのである。
•••
死によって変容するツァヘス、そして溺死によって成仏する猫の姿を観察するとき、その湿り気、すなわちフモールは、いずれの場合にもアンチテーゼとしてのイロニーを超え、一つの調和的なジンテーゼをもたらしている。ツァヘスにしろ猫にしろ、いずれもイロニーの力に駆り立てられ、自分の限りない理想を求めたのであったが、自らの、あるいは地上的存在としての限界に達し、ついには再び地上へと降下し、最終的には溺死する運命にあった。しかし、そこには限界に挑戦したという満足感が生じている。それは、生を享けた者の充実感であり、生の一回性を体験したものすべての喜びでもある。それゆえ、そこには生を無限に肯定する弥勤菩薩か仏陀のごとき「死の微笑」が、必然的に浮かんでくるのである。
漱石にとっての西洋文明と日本文化は単純にテーゼとアンチテーゼとして対峙されうるものではないようにも思うけれど、『吾輩~』の猫が溺死していくときの心情は確かにここに書かれてあるものに近いかもしれない、と感じました。『現代日本の開化』の結論も決して諦念や敗北だけではない何かがそこにはあり、それは梅内先生が書かれている「それは妥協というよりは、むしろ現実と理想の「調和」と呼ぶべきである。あるいは、人類の「智恵」とも呼びうるかも知れない。」と似たものを感じます。絶望だけではない何かを漱石は残してくれている。
話をホフマンに戻します。『大晦日の夜の冒険』や『クライスレリアーナ』が収められているのは『カロ風幻想曲集』というタイトルの作品集で、また『ブランビラ王女』もカロの版画からインスパイアされて書かれた作品です。ジャック・カロは400年前のフランスの版画家で、マーラーの交響曲第1番「巨人」の3楽章もカロの版画がもとになっていました。私はカロについては詳しくないけれど、マーラーの音楽はカロを通してホフマンの世界にも通じているように思う。ホフマンの作品をそのまま音符にしたら、マーラーのような音楽になるはず。グロテスクさ、病的になりかねない混沌、脈絡なく話が跳び、そして回収されない。なのに世界の統一感があって、都会的。wikipediaによると、マーラーの交響曲第一番の3楽章はホフマンの『カロ風幻想曲集』にヒントを得たともいわれているそうです。
エルンスト・テオドール・ホフマンはアマデウス・ホフマン、すなわち「お化けのホフマン」と呼ばれた。いや、自分で好んでアマデウスを名のった男であった。敬愛してやまないモーツァルトに肖(あやか)ったのである。
46歳の短い生涯であったが、その多彩奇才の表現力はなぜか老ゲーテや同時代のヘーゲルに嫌われ、ハイネに褒められ、のちには後期ロマン派の代表作家として、バルザック、ジョルジュ・サンド、リラダン、プーシキン、デュマ、ドストエフスキー、ネルヴァル、モーパッサン、ボードレールに絶賛された。
この通信簿は悪くない。とくにプーシキンとリラダンが兜を脱いだところが上々だ。
(松岡正剛の千夜千冊)
この通信簿は参考になる。ホフマンを絶賛した作家の本を、今度は読んでみたくなる。
と、ここまで書いてきて、謎が謎のまま残っているのに何故か世界の調和を感じさせる妙な説得力があるのって、宮崎監督の映画と似てね?きっと宮崎監督もホフマンお好きな気がする!と思い「宮崎駿 ホフマン」とググってみたら。
三鷹の森ジブリ美術館企画展示
クルミわり人形とネズミの王さま展 ~メルヘンのたからもの~(2014年5月31日~2015年5月17日)
なんですとーーーーー




こんな企画展があったなんて・・・・・・・・


当時はホフマンを読んでいなかったとはいえ、後悔してもしきれん。。。。せめて企画展のパンフレットだけでも手に入らないかと調べてみたら、めっちゃプレミアム化していて手が出ない。。。仕方がないので当時のアエラの特集号を図書館で予約しました。宮崎監督の絵、すごく素敵だなぁ。行きたかったなぁ。。。。。。
宮崎監督とホフマン作品との出会いは『風立ちぬ』の制作中だったそうで、読書家の宮崎監督がそれまでホフマンを読んだことがなかったというのは意外。でも宮崎監督って、本や映画を最後まで読んだり見たりしなくて平気な人なんですよね。途中で想像の翼が羽ばたいて、続きの物語を自分で作ってしまうそうで。高畑監督はそうではないらしいが(ほぼ日新聞)。宮崎監督、『くるみ〜』はちゃんと最後まで読まれたのかしら
内覧会では、東京・三鷹の森ジブリ美術館館長の中島清文氏が今回の“クルミわり人形とネズミの王さま展”が企画された経緯について語ってくれた。
中島氏によると、宮崎駿監督は企画・監修だけでなく、イラストつきのパネル10数枚を描いており、今回の企画展示は、宮崎監督の長編映画製作における引退後の、初仕事とも言ってもよいとのことだ。
なぜ今回の企画が始まったのか、ということだが、これは宮崎監督がロンドン在住のイラストレーター、アリソン・ジェイ氏がイラストを手がけた絵本『くるみわりにんぎょう』に出会ったことがきっかけとのこと。
宮崎監督がこの作品に触れたのは、ちょうど『風立ちぬ』の製作の真っ最中で、ヘトヘトに疲れていたときのこと。何度も何度も、毎晩この絵本を見ているうちに、作品が好きになった宮崎監督は、3人の女の子にこの絵本をプレゼントしたという。
絵本の評判は上々で、それに気をよくした宮崎監督は、さらにネットでドイツ製のくるみ割りを購入して女の子にプレゼント。えこひいきにならないようにするために8体も購入し、「おかげでおこづかいがなくなった」とこぼしていたそうだ。
とはいえ、そこで宮崎監督はおもしろいことがわかったようだ。男の子は、人形の口をがちゃんがちゃんと開けたりしてロボットのように遊ぶのだが、女の子は人形をぎゅっと抱きしめてくれたそうだ。
女の子はたいそうくるみ割り人形を気に入ってくれたそうだが、宮崎監督は「なぜ、女の子はこんなにくるみ割り人形が好きなんだろう」と不思議に思い、E・T・Aホフマンによる原作本『クルミわり人形とネズミの王さま』を読むことにしたのだという。
一読して宮崎監督は困惑したらしい。それは、話が理解できないからだった。「この人形は人間なのか? それとも人形なのか。つじつまがあっていないぞ」と混乱したという。しかし、周りで本を読んだ女性たちは「え? そうでした?」という感じでとくに気にしていなかったそうだ。そこで、「なぜなんだ、なぜこのつじつまがあわない世界を理解できるのだ」と宮崎監督は疑問に思い、さらに作品にのめり込んだらしい。
現在、おもに流通している『クルミわり人形とネズミの王さま』は、19世紀後半にフランスで刊行された改訂版であり、物語のつじつまが合うように整理されているものだそうだ。その後にはバレエ版も作られていたが、E.T.A.ホフマンによる原作本はあまり読まれてはいなかったようだ。
そのような経緯もあり、宮崎監督はいま一度、「ホフマンの世界を読み解こう」、「みんなにも読んでもらおう」と考えたのだという。そもそもなぜ主人公はくるみ割り人形なのか、当時のくるみ割り人形はどんなものだったのか……、と疑問に思って調べたのが、今回の企画展示の出発点となったそうだ。
宮崎監督は、自身の作品には“ここからは現実であり、ここからは異世界である”などという明確な“ルール”を決めているらしい。しかし、E・T・Aホフマンが書いた原作はつじつまが合わず、そのようなルールが見えなかったという。
とはいえ、宮崎監督はE.T.Aホフマンによる原作の特徴を肯定する。なぜなら、子どもとっては、現実も幻想も空想もいっしょくたで、ひとつの物語になっているからだ。それこそメルヘンと呼べるものであり、この本は“メルヘンのたからもの”なのだとー。そこで、「このメルヘンのたからものを、みんなにも読んでもらいたい、みんなにも知ってもらいたい」という想いを持ったという。その想いが、最終的にこの展示へつながったのだそうだ。
(ファミ通.com「宮崎駿監督“引退後”の初仕事 三鷹の森ジブリ美術館“クルミわり人形とネズミの王さま展”をリポート」)
こんなに長く書いてきてすみませんが、ホフマンと宮崎監督について、最後にもう一つだけ書かせてください。
彼(ホフマン)は俗物を徹底的に嫌った。それは彼自身が俗物であったからである。・・・ホフマンが芸術家たるためには、いな芸術家であればあるだけ、市民的練達と事務的な仕事とを愛し、それを必要としたといわねばならない。・・・ホフマンに於ける俗物の世界は日常の世界である。この日常の世界に安住せんとするホフマンを他のホフマンが否定しようとする。それは魔法の世界、即ち不思議の国に住むホフマンである。この二つの世界はホフマンに於ては並立するのではなくして、二つは互に前後上下の関係にある。日常の世界の背後或は底に不思議の世界が隠されて居り、日常凡俗の現実の上により高い現実世界が予感される。ここにホフマンが浪漫派の人であると同時に浪漫派を超えて現実主義の世界に踏み入ろうとしている詩人である根拠がひそんでいる。浪漫派の人々にとって「青い花」は永遠に花として咲き、いたるところに咲いていると共にどこにも咲いていない花であるが、ホフマンにとってはそれは「青い花」として永遠の彼岸に咲き匂う花であると同時に日常の現実に於て咲きまた実を結ぶ花でもある。それはホフマンに於ては日常の世界はそのまま芸術の世界に変えられるからである。そしてここにホフマンの「現実」の秘密がひそんでいる。
(渡辺竜雄「エ・ア・テ・ホフマンと「現実」の問題」)
これを読んで、なんとなく宮崎監督が『風の帰る場所』で宮沢賢治について仰っていたことを思い出しました。宮沢賢治がホフマンと同じというわけではなく、なんとなく思い出したので、覚書として書いておきます。ちなみにインタビュアーはロッキング・オンの渋谷陽一さん。渋谷さんは表現者・宮崎駿を「本当に大好きで、もう死ぬほど好き」なのだそう。
「人を殺した人間だから、殺すことの痛みがわかった人間だから。それで膝を曲げるんじゃなくて、それを背負って歩いてる人間だから、この娘は描くに値するんじゃないかと僕は思ってたんですよ。純潔であるとか、汚れてないことによって、それが価値があるっていうふうな見方というのはね、なんかものすごくくだらないんじゃないかっていう気がするんですね。その泥まみれで汚れてて、それで傷だらけだから。だから、宮沢賢治を僕は好きなんですよ」
――うん。
「宮沢賢治が聖人でね、彼が言ってるとおりの人生を歩んだとは、僕は思えないですよ。やっぱりオナニーもしたんじゃないかと思うんですよね。だからっていって、僕は宮沢賢治をますます好きになるだけでね。そういう葛藤はあるはずですよ、当然です!」
――そうです、うんうん。
「で、非常に愚劣なね、もう少しいい男に生まれたらよかったのにとかね、そういうことを全然思わなかったはずないですよ!」
――ははははは。
「そういう無数の複合体だから、人間って。ただ、生き物っていうのは動態だからね。動いてる。静的な存在じゃないから。だから、同じ人物でもね、ものすごく愚劣な瞬間があったり、それからなんかやたらに高揚してね、あるいは実に思いやりに満ちたり、そういうふうに揺れ動いてるものなんですよ」
※このページ↓の『ブランビラ王女』の解釈、とてもわかりやすいし共感できる。
創作された夢 E.T.A.Hoffmannの『ブランビラ王女』の解読(木野光司)
同じ方の書かれたこの本も、読んでみたいです。
『ロマン主義の自我・幻想・都市像―E.T.A.ホフマンの文学世界』













 にポツンポツンと藁ぶき屋根の家があって、そこから煙が出ている昔の横浜村の長閑な風景が目に浮かぶようで、好きだったなあ
にポツンポツンと藁ぶき屋根の家があって、そこから煙が出ている昔の横浜村の長閑な風景が目に浮かぶようで、好きだったなあ
 と疑いwikiを読んでみると、なんと横浜市歌のみならず横浜商業高等学校(Y校)の校歌まで作詞しているではないですか。
と疑いwikiを読んでみると、なんと横浜市歌のみならず横浜商業高等学校(Y校)の校歌まで作詞しているではないですか。




 です。
です。



 。ウィーンのプログラムは変更後の名古屋と同じですね。もしやウィーンのリハーサルのおつもり…?とか疑っちゃだめよ、だめだめ。
。ウィーンのプログラムは変更後の名古屋と同じですね。もしやウィーンのリハーサルのおつもり…?とか疑っちゃだめよ、だめだめ。 )の翻訳者さんのtweet。
)の翻訳者さんのtweet。












 )、近くて遠い国ロシアを気軽に体験できるのは楽しい。記事で紹介されていたアレクサンドロフのスィロク(チーズをチョコレートでコーティングした冷たいお菓子。写真左上の箱)も、濃厚な味で美味しかったです
)、近くて遠い国ロシアを気軽に体験できるのは楽しい。記事で紹介されていたアレクサンドロフのスィロク(チーズをチョコレートでコーティングした冷たいお菓子。写真左上の箱)も、濃厚な味で美味しかったです





