ワタクシ、原作を途中まで読んでいたんですけどね、まずキャストが決まった時点でそりゃーもう夜神月は藤原竜也くんしかおらんでしょって感じでしたね。(つーか、これ漫画の時点で彼をイメージしてたんじゃないの?って感じなんですけど、そうなんでしょうか?)でも、エルを演じられる人なんているの?って思ってて、松山ケンイチくんって全然知らなかったんだけど、エルの扮装をしているのを見たらこれまたそっくりでビックリしちゃいましたよ。本編を見ると喋り方はちょっとワタクシがイメージしてたのとは違ったけど、それでも全然OK範囲ですね。しかも、それってワタクシだけのイメージやし。喋り方で言うなら藤原竜也くんのほうもちょっと違ったし。そして、月のお父さん役が鹿賀丈史っていうのはちょっとミスキャストって思ってたんやけど、フタを開けてみるとすごく漫画のお父さん像に近くて鹿賀丈史の演技の幅の広さにあらためてすごい人だなぁと。そして、なによりもリューク中村獅童にビックリ。中村獅童の声はまぁまぁってとこ(もうちょっとチャーミングに喋って欲しい)ですが、あの映像すごいな。CGなんだろうけど、あのリアルさってほんとにビックリする。いまどき、CGだったらあれくらいできて当然なんだろうけど、それでもやっぱり感心しちゃいますよね。
原作を読んでいない人からしたらどんな感じなのかなぁ?ちょっと分かりにくい?あと、原作のコアなファンの人だったら、「原作と違うー」ってイヤになるのかも。ワタクシは原作は途中まで読んだし、好きだけど、ファンってとこまででもないから映画も楽しめるのかも。
漫画だから、夜神月が捜査本部に入れてもらうとかFBIが出てくるとかありえんことが起こりますが、それ言い出したらデスノートの存在そのものもありえん!って一刀両断に切り捨てちゃうことになるっちゅうことでそれもいいとしましょう。
前編はシチュエーション説明っていう性格も持っているからその中でのこのデキはかなりOKではないでしょうか。問題は後半ですな。ワタクシは漫画も中途半端にしか読んでいないので結末を知らないのですが、映画のほうもどんな結末を迎えるのか楽しみであります。
それにしても、いくら後半を見に来てもらうためだからってこんなに早くTV上映しちゃって映画館まで見に行った人怒ってないかな?











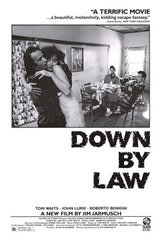

 」という気もしたけど、最後の生徒たちの言動には感動した。
」という気もしたけど、最後の生徒たちの言動には感動した。 特にCoolioの「Gangsta's Paradise」は最高にクールです。
特にCoolioの「Gangsta's Paradise」は最高にクールです。 弟くんが被害者の遺族に会いに行くシーン。弟に背負わせた運命を知り、自分が背負う償いの重さを知った兄は被害者の遺族吹越満に毎月かかさず書いていた手紙を書くのをもうやめるという。その最後の手紙を受け取った遺族は「僕はもうこれで終わりにしようと思う。僕はもうこれでいいと思う。」と言う。加害者の家族の思い、被害者の家族の思い、そして、加害者本人の思い。そのすべてがこのシーンで語られ、そのすべてが昇華へと向かうこのシーン。
弟くんが被害者の遺族に会いに行くシーン。弟に背負わせた運命を知り、自分が背負う償いの重さを知った兄は被害者の遺族吹越満に毎月かかさず書いていた手紙を書くのをもうやめるという。その最後の手紙を受け取った遺族は「僕はもうこれで終わりにしようと思う。僕はもうこれでいいと思う。」と言う。加害者の家族の思い、被害者の家族の思い、そして、加害者本人の思い。そのすべてがこのシーンで語られ、そのすべてが昇華へと向かうこのシーン。 ケーズデンキの会長が「差別のないところを探すのではなくて、君はここで生きていくのだよ」というセリフは現実的にはもっともなアドバイスなんだろうし、あの時の弟くんには必要なアドバイスだったと思う。事実、この社会で生きていくには自分が受ける差別と折り合いをつけて生きていかなければならないし、どんな差別を受けようとも自分自身が誇りを持って生きることが大切だと思う。ただ、このセリフを実際に彼を左遷した側から言われるとそれはこの差別が存在する社会への言い訳にしか聞こえなかった。「差別のないところを探して逃げ回る」のは良くないと言いたかったのは分かるが、「差別のないところを共に作り出そう」という理念を持って彼に接して欲しかった。
ケーズデンキの会長が「差別のないところを探すのではなくて、君はここで生きていくのだよ」というセリフは現実的にはもっともなアドバイスなんだろうし、あの時の弟くんには必要なアドバイスだったと思う。事実、この社会で生きていくには自分が受ける差別と折り合いをつけて生きていかなければならないし、どんな差別を受けようとも自分自身が誇りを持って生きることが大切だと思う。ただ、このセリフを実際に彼を左遷した側から言われるとそれはこの差別が存在する社会への言い訳にしか聞こえなかった。「差別のないところを探して逃げ回る」のは良くないと言いたかったのは分かるが、「差別のないところを共に作り出そう」という理念を持って彼に接して欲しかった。

 してくれちゃうのだ。こればっかりは見てもらわないと、言葉で彼らの面白さを表現することは不可能ですね。彼らの存在がなければ、このお話をこんなに好きにはならなかったかも。でも、これはかなりツボにはまる人と「はぁ
してくれちゃうのだ。こればっかりは見てもらわないと、言葉で彼らの面白さを表現することは不可能ですね。彼らの存在がなければ、このお話をこんなに好きにはならなかったかも。でも、これはかなりツボにはまる人と「はぁ 」ってなる人の差が激しいかも。ワタクシは完全にツボにはまっちゃいました。
」ってなる人の差が激しいかも。ワタクシは完全にツボにはまっちゃいました。
 でした。
でした。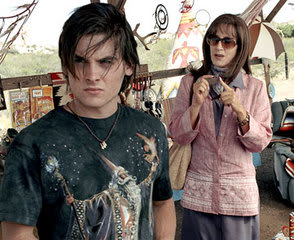


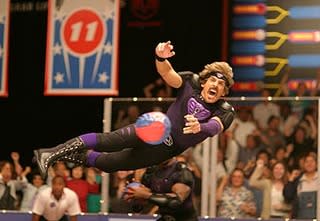


 の中で大声を張り上げて歌いながら帰ったワタクシでした。
の中で大声を張り上げて歌いながら帰ったワタクシでした。

 )って言った人に「それは千昌夫」と突っ込んでいて、“なんのこっちゃ”と頭ん中が「?」だらけになっていたんやけど、
)って言った人に「それは千昌夫」と突っ込んでいて、“なんのこっちゃ”と頭ん中が「?」だらけになっていたんやけど、 “よし、行くぞー”
“よし、行くぞー”

 ってことなんやけど、、、ついつい手を出しちゃったのよねー
ってことなんやけど、、、ついつい手を出しちゃったのよねー )
)