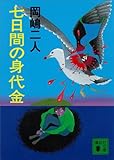|
迷路館の殺人 |
館シリーズの第三弾、今回は各部屋を繋ぐ廊下が迷路状になっている迷路館がその舞台です。
推理小説の大家である老作家の誕生パーティーに招かれた4人の弟子、編集者、批評家、そして我らが名探偵島田潔、しかし訪れてみれば老作家は病を苦に大量の睡眠薬を服用して「この館で、自らが被害者になる小説を書け、一番に優れた者に財産を譲る」とのメッセージを残していました。
戸惑いながらも執筆を始める弟子たち、ところがその作品、ミノスの迷宮、ミノタウロス、イカロスなどギリシャ神話にちなんだ見立てで一人、また一人と殺されていきます。
それなりのボリュームですが立て続けに事件が起きるために間延びした感じはなく、切れ味鋭いタッチで引き込まれていくのはこれまでどおり、それなりには楽しませてもらいました。
ただ、ただ、その切れ味も徐々に鈍りつつあるような気がします。
タネ明かしをされてしまえば水車館と同じく掟破りと言いますか、これは登場人物にも語らせていますので確信犯なところもあるのでしょうが、謎を解き明かす楽しみがありません。
正しくは解き明かす努力が無に帰する、これはある意味で読み手への裏切り行為でしょう。
巧みなレトリックで餌を撒きながらも気がつかせない技法はさすが、しかしそのテクニックに溺れて二重、三重にしたことが逆目に出たような気がします。
エピローグの罠にどれだけの意味があるのか、騙されたよね、と自己満足に浸っているだけではないかとも思います。
そもそもの館シリーズ、中村青司が「奇っ怪な設計をする」だけの存在になってしまっていて、肝心の館も色を出すこともできずに脇役でしかなく、それは名探偵を現場に召還するためのアイテムでしかないのか、ここまでの前振りは何だったのか、これでは掟破りへのこじつけでしかありません。
何らかの意志のようなものが感じられる館に、次こそは巡り会いたいです。
2016年9月7日 読破 ★★★☆☆(3点)