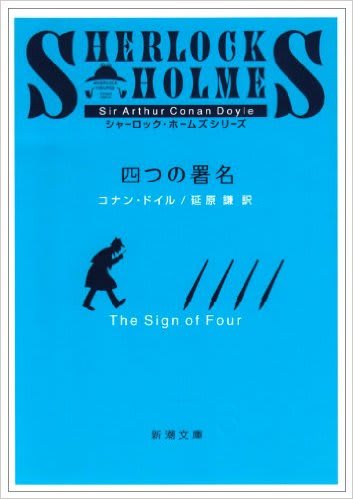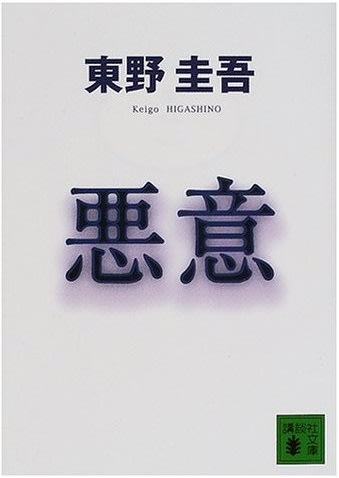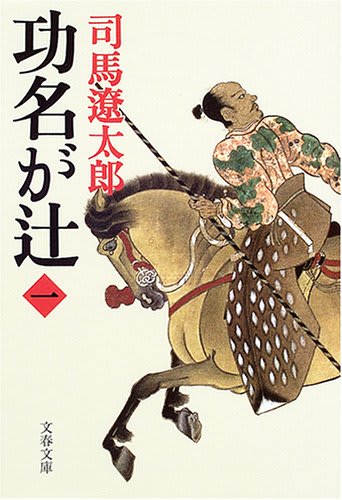
ネット上を漂っていたら大河ドラマ『功名が辻』の全話49回分の動画があって、見入ってしまった。
3~4回は見た。面白いのだ。時代は戦国時代から江戸時代の最初のあたりまで。織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の時代で、この三人に仕えて、戦で敵の首をあげて出世していった男の妻千代の話である。この原作本の事は知っていたが、山内一豊という大名の事は全く知らなかったから、司馬遼太郎作品で面白そうだとは思っていたが、読む事はなかった。
功名が辻というタイトル、ドラマでは山内一豊の家臣の五藤吉兵衛が一豊に、「このいくさで大将くびを上げるかどうかが、功名が辻ですよ」というように言っていた。敵の首を取れるかどうかが、出世を左右しますよ、出世の分かれ道ですよ、というような意味。
このドラマも小説も、実は主人公は妻の千代。信長、秀吉、家康に仕える夫は、歴史上有名な戦や事件が起こっていく。賢い妻が夫を立てつつ、夫にどうすべきかを示唆する。山内伊右衛門一豊には過ぎた女房で、千代自身も信長、お市、濃姫、秀吉、ねね、茶々、堀尾吉晴夫妻、中村一氏夫妻などと交流を持ち、天下がどうなっていくのか、その時にどうすべきか、軍師なみに判断を下す。女大名とも言われる。
山内一豊は信長に仕え始めて、関ケ原の戦いが終わって、土佐二十万石、一国一城のあるじに出世する。地味な凡庸なキャラクターで出世も遅いのだが、歴史に名前を刻んだ有名人になったのである。