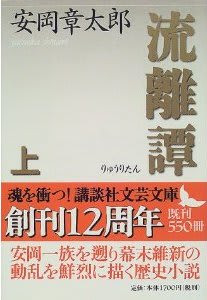坂本龍馬

高杉晋作
今ちびちび読んでいるのがこの本。
司馬遼太郎氏の『竜馬がゆく』を読んだのは大学生の頃だったと思うが、面白くて全八巻を短期間で読んだと思う。もう記憶には無いが。
司馬氏のは“竜馬”だが、俺は竜でも龍でもどっちでも同じだと思っていた。間違いではないと思っていた。しかし、井沢氏によれば、司馬氏は小説として書くために“竜馬”とあえてしたようである。確かに固有名詞だから龍馬を竜馬と書くのは間違いだし失礼な事だ。司馬氏は大筋の史実を踏まえつつも面白おかしく創作するために“竜馬”として一線を画したと言う事だ。
『竜馬がゆく』は長い期間に渡ってかなり売れている本である。ここに書いてある事を史実と考えている人はかなり多いだろう。“司馬史観”という言葉がある。『竜馬がゆく』以外の本も司馬氏の書いた本はかなり売れていて、司馬氏の歴史観や人物観が読者の間に広がってしまっていて、個々の史実や人物のイメージが読者の中で固まってしまっているという事だ。その司馬氏の歴史観の事だ。司馬氏は小説家なのであって歴史書を書いたわけではない。司馬氏が取り上げなかった史実は埋もれていくし、司馬氏が重要視しなかったり、好きでない人物は過小評価されたり時には悪いイメージを読者に持たれているだろう。俺も全く覚えていないものの教科書で大きな扱いではなかったが、坂本龍馬という人が明治維新に非常に大きな役割を果たした魅力的な大人物だったという印象を持っていた。学校の授業でしっかり学んだ記憶も無いから、当時『竜馬がゆく』をまるっきり信じていた。井沢氏は我々が思い込んでいる歴史を、本当にそうだったのか?という視点で書いている。
高杉晋作、久坂玄端などあまりよく知らなかったし、まだわかっていないがそれぞれ27歳、24歳で亡くなっている。龍馬も31歳だ。その若さでも歴史に名を留める人生を送ったというのが凄い事だ。
わくわくどきどきという要素もあるが、すらすらと進む本ではないので読むのに時間が掛るのがたまにきず。















 零戦(靖国神社の遊就館)
零戦(靖国神社の遊就館)
 永遠のゼロ
永遠のゼロ