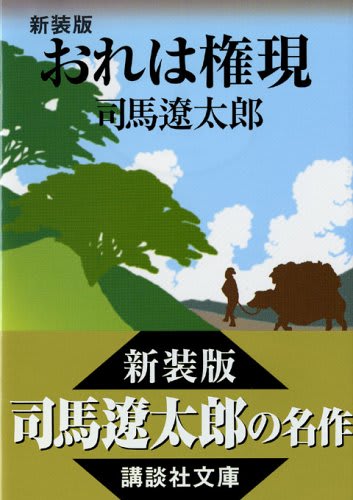ハラスという名の柴犬と生活した日々の記録。

柴犬(イメージ写真)(ハラスではない)。

アメリカ人記者による硫黄島の戦い。日本軍についても書かれている。

アメリカから見た硫黄島の戦い。すり鉢山に立てた星条旗に関わった兵士達の生死、その後の人生がテーマ。
柴犬はかわいい。僕は柴犬がずっと欲しかった。あまり大きくならないのも良い。僕にとって犬といえば柴犬なのだ。それは小さい時の体験が強烈に印象に残っているから。残念ながら犬も猫も飼った経験はない。柴犬は死ぬまでに一度は是非飼いたい。
ここに挙げた本は著者である大学教授が横浜に一戸建ての家を買って移り住み、柴犬を飼った時の体験の記録である。柴犬ハラスが十三年の生涯を閉じ、著者はハラスとともにした生活の喜怒哀楽を記して、ハラスへの思いに決着をつけたかったと記されている。すでに一度は読んだのだが、忘れがたくまた読みだした。
『犬なんてみな同じようなものだと、前は思っていたが、あとになってみればその犬以外の犬ではだめだという、かけ替えのない犬になっているのだから』これは最初のページにある文章である。犬も大事な家族なのだ。読むと楽しくて悲しい。それでも飼ってみたい。
大東亜戦争当時、アメリカは硫黄島を獲得してそこに飛行場・基地を作れば、日本の本土を易々と爆撃出来るようになるから必要としていた(もちろんもっと強い気持ちだったと思う)。グアムから東京までだったら2000kmくらいあるが、硫黄島からは1200km程度だから。
日本側は、硫黄島を守り抜かなければ本土が爆撃を受け、本土にいる次代の日本を担う子供達やそれを育てる女性達が殺されると考えていた。1945年の2月の事で、敗色濃厚な日本軍には職業軍人はあまり残っていない、招集された一般人の兵士がほとんど。物量で劣る日本軍の作戦は、アメリカ兵を水際でくい止めるのではなく、アメリカ軍を上陸させてから、地下に掘った穴の中から攻撃して一人で十人のアメリカ兵を殺すというもの。結局はアメリカ軍に負けて全員が死ぬ事になるだろうが、一日でも本土への攻撃を遅らせる事が出来れば、一日分だけ子供達や女性達が生き延びられる。
アメリカ軍は5日で制圧を計画していたが、日本軍の抵抗はすさまじく36日間持ちこたえた。日本軍は約23000人のうち約18000人が戦死。アメリカ軍は11万人を動員し、約7000人が戦死。
国の為重き努を果し得で 矢弾尽き果て散るぞ悲しき
これは帝国陸軍の栗林忠道中将が3月16日に大本営へ送った訣別電報に記した辞世の歌の一つだ。補給も途絶えていたから、食料も武器も弾も無い。水は硫黄島にはもともと無い。雨水を貯めて飲んでいたのだ。圧倒的な人数と物量で押し寄せてくるアメリカにどんどん追い詰められ、栗林中将は最期の突撃に出てアメリカ軍から銃撃されて玉砕を遂げたとみられている。
亡くなった英霊達は誰一人として、私利私欲のために戦ったのではなく、祖国のために、同胞のために、家族のために自分の命を投げ出したのだ。その精神は気高く、尊い。しかし、日本軍から感じるのは悲壮感、絶望感、貧しさ。日本側の記述や映像もそういう感じになる事が多い。だから僕はアメリカ軍の側からの記録も読んでみたかったのだ。