イワン・イリイチの死 (レフ・トルストイ)望月哲男訳 光文社2006年出版
裁判官となり功なり名を遂げたイリイチは結婚とともに健康を害してしまった、社交界の華であった妻はこうるさい虚栄心の強い女であった、この妻を喜ばせようとして彼はより高い地位に出世したが新しい家を自ら飾り立てていたときに梯子から落下した、
その際身体を痛め大したことでもないと思ったが次第に痛みは増し、それが元で内臓疾患に陥った、それは短期間にたちまち悪化してゆく、遂に彼は死を眼前に意識せざるを得なくなり恐怖の虜となり、そしてまだ45歳という若さで自分が死に逝くことを受け入れることができず、耐えざる痛みと闘いつつ何とかして治癒したいと願う、だが痛みは益々激しくなり見る影もなくなるほどやせ細ってしまうのだ、
イリイチは最期が近づくとき自分はいま何をすべきなのかと自問自答を繰り返す、彼は自分の無力を嘆き、恐ろしい孤独を嘆き、人々の残酷さを嘆き、神の不在を嘆くのだ、何のためにこんなに苦しむのかと嘆いた、
いま何を自分は欲しいのかと問う、今までの生き方が間違っていたのではないかと疑う、だが答えは与えられない、
イリイチは世間が求めているこの世の価値ある立派な生き方が間違っていたのであって、それらは生と死を覆い隠す恐るべき巨大な欺瞞であることを覚るのだった、妻は彼に聖体拝領を勧め彼もそれを受ける、彼は体も気分も楽になった気がした、だが彼は妻を憎み再び苦痛にとらわれる、三日間唸り続けその苦痛のなかで死を前にして自分がすべきことがあるのではないかと言う意識が浮かぶ、
彼は傍で自分をみて泣いたりオロオロしている家族をみて、自分の死が彼らを開放できると気付く、イリイチは「ゆるしてくれ」と自分が言ったように思った、そのとき彼を苦しめていた体の痛みも死の恐れも消えていたのである、その代わりにひとつの光があった、なんと簡単なことか、なんと歓ばしいことか、死は彼にとって最早
存在しなかった
死に面したとき、それの拒絶と受容の過程はキューブラ・ロスの著書「死ぬ瞬間」で否認、怒り、取引き、抑うつ、受容の五段階を経て進むと解説されており、このイワン・イリイチの場合もそのとおりである、誰もが避けて通ることのできない死についてイリイチがどのように苦しみ受容に至ったのか、健康で全てが順調であったときに人生の価値であると思っていたものがすべからく欺瞞であり嘘であったという結論は実に厳しいものだ、
人生が死という終着駅を目指して進んでいるときに為すべきこととは本当に簡単なことであるという、それも大それたことではなく死病で身体も動かせず口も十分に語れなくともできることであるという、これは理屈や勉強で身につくものではなく、キューブラ・ロスの説くような五段階の心の葛藤を自ら経なければ、到達できない次元であろう、だが、到達したときには今までおそるべき恐怖を伴って待ち構えていたら死の姿は消え失せ代わりに大いなる絶対の光しかそこにはないのだという















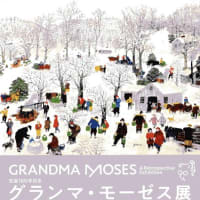




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます