■ 関東大震災で東京は壊滅状態になりました。地域のコミュニティーの場でもある銭湯も壊れました。
「銭湯を豪華に造り直すことで街に活気を取り戻そうと考えた。すっかり沈んでしまった街の人々を元気づけようとした」
NHK教育TVの「美の壺」では東京の銭湯が豪華につくられた理由をこのように説明していました。
亀の湯@北区西ヶ原
先日山手線の駒込駅から旧古河庭園に向かう途中でたまたま見かけた銭湯を路上観察、といってもこの写真を一枚撮っただけですが。
いわゆる宮づくりといわれる銭湯。神社仏閣に見られる唐破風が印象的です。
浴室の壁一面に富士山が描かれているんでしょうか・・・。こんな銭湯でゆったりと一番風呂を楽しむことができたら幸せでしょうね。
残念なことにこのような昔ながらの銭湯が次第に姿を消しています。取り壊してしまうのはもったいないことです。
東京の谷中で銭湯を改修してつくったギャラリー(谷中のギャラリー)を見かけたことがあります。広いスペース、高い天井、高窓から入る自然光、これらの条件は彫刻等の展示スペースに向いています。
でもやはりこのような立派な銭湯には、ず~っと現役でいて欲しいと思います。銭湯の存在は街が健康なことの証のような気がします。
■ 国際文化会館は六本木にある。六本木・・・、東京で生活していたころは全く縁の無いところだった。昨日(0627)初めてこの会館を訪れた。
会館は、前川國男、坂倉準三、吉村順三の共同設計による建築。確か取り壊しも検討されたが、耐震補強や大規模な改修工事が行われて生まれ変わったのが数年前のことだった、と記憶している。
同行の友人によると、本館棟の客室は以前は中廊下型で狭かったが、改修工事によって片廊下型となり、ゆったりとした客室に生まれ変わった、ということだ。
パンフレットには客室の内観写真が載っている。モダンな和の空間は吉村順三主導で設計されたのだろうか。外観のデザインは坂倉準三主導ではないか。薄いスラブや細い手摺、写真には写っていないが本館棟の妻壁は鎌倉の近代美術館に通ずる雰囲気だ。1階の壁に使われている大谷石も近代美術館と同じでは。
増築棟は東京都美術館と同じレンガ調タイル打ち込みの外壁。設計は明らかに前川國男。では、本館棟の前川國男のデザインはどこだろう・・・。
ロビーやティーラウンジはなんとも心地よい上品な空間。「普通の空間」と一体どこがどう違うのか。床や壁、天井、開口部など、空間構成要素を分析的に捉えても分からない。やはり空間の雰囲気は様々な要素が統合されて醸し出されるものだろう。確かなことは「時間」という要素が必須ということだ。
屋外には豊かな緑の庭園が広がっている。静寂な空間は都心に位置するとは思えない。京都の造園家 小川冶兵衛の作とパンフレットにある(旧古川庭園の作庭者も同一人物だが、庭園のパンフレットは小川治兵衛となっている)。
機会があれば再訪したいと思う。
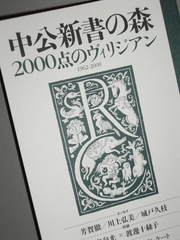
■ 中公新書が通巻2000点を迎えたことを記念して製作された『中公新書の森 2000点のヴィジリアン』。昨日(0627)紀伊国屋新宿南店で入手した(無料)。 やはり東京の大型書店は松本の書店とは違う。
冊子には川上弘美のエッセイ「『宦官』のころ」、渡邊十絲子さんと奥原光さんの対談、「思い出の中公新書」というアンケートの回答(179人分)などが収録されている。
対談には渡邊さんの中公新書ベスト20が載っているが、その中に偶然にも先日ブログに取り上げた『近代絵画史』と『美の幾何学』が入っていた。長谷川尭さんの『建築有情』はサントリー学芸賞を受賞している。
巻末の略年譜によって、透明なビニールカバーから紙カバーに変わったのが1989年ということと、初代編集長が宮脇俊三さんだった、ということを知った。
アンケートの回答を読むと『胎児の世界』三木成夫を複数の人が挙げている。胎児は成長する過程で、生物の進化の過程をトレースするということを紹介している本らしい。この本はたぶん未読、今度書店で探してみよう。

■ しばらく前から読んでいる『のぼうの城』はいよいよ後半、俄然面白くなってきた。が、注文しておいた武澤秀一さんの『空海 塔のコスモロジー』春秋社が届いたので、ちょっと寄り道。こちらを一気に読了した。
同じ著者の『マンダラの謎を解く』講談社現代新書や『法隆寺の謎を解く』ちくま新書と同様、「!」な謎解き。
先日取り上げた中公新書は学術的にオーソライズされた内容のものが多い、と思う。もちろんそれはそれで興味深いのだが、「!」な内容となると物足りなくも無い。その点、「謎を解く」という明快なスタンスで書かれた武澤さんの著書は読み物としても面白い。
武澤さんはローマのパンテオン(内部に空間をはらんでいる)とインドのサーンチーの塔(内部に空間を持たない)を内と外の反転、虚と実の反転とトポロジカルな捉え方をしている。
このあたりの見方や伽藍配置の変遷から塔の意味、位置付けの変化を読み解くあたりはやはり建築家の眼だろう。
図版を豊富に示しながらの実証的な論考、大変興味深く読んだ。
**それにもまして大きな懸念があった。半球体という裸形の幾何学が日本の風景のなかに露出することへの違和感である。中国で拒否された「卵」が日本で受け入れられるとは、とうてい思われない。インドの塔をもってきても日本の風景になじまなければ、そしてそこでつちかわれた感性になじまなければ、結局のところ根づかない。日本人の感性を考えると、大きな「卵」が露わになるのは、中国における以上に違和感をもたれる恐れがある・・・。(中略)
そこで編み出されたのが、すでになじんでいる伝統的な屋根を塔全体にかぶせ、さらには巨大な「卵」に直接取り付けて「卵」は一部だけ見せるという、大胆な折衷的デザインであった。**
インドのサーンチーから大塔(だいとう 表紙の高野山創建大塔復元立面図参照)へのデザインの転換についての考察。これを空海のデザインセンスと指摘する著者。このあたりが「!」なのだ。

いつ頃までかは、分かりませんが、昔の中公新書には透明のカバーがついていました。長谷川 尭さんの『建築有情』も透明のカバー付きです(写真はカバーを外して撮りました)。昭和52年7月に再版された本です。もう30年以上も前に読んだことになります。
今、この本を読んだら、どんな感想を持つだろう・・・。『のぼうの城』を読み終えたら、読んでみようと思います。
このブログの過去ログを見て、何回も中公新書を取り上げていることが分かりました。既に書いたことですが、内容の充実度では他の新書を大きく引き離していると私は思います。でも中公文庫はほとんど取り上げていません。読んでいないんです。
ウイスキーはサントリーなのに、ビールはアサヒかキリン。新書は中公なのに文庫は新潮か文春。何故なのか、理由はよく分かりません。
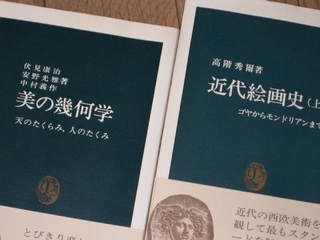
自室の書棚に並ぶ中公新書には、こんなタイトルのものもあります。学生のときに読んだ本です。よく覚えていませんが『美の幾何学 天のたくらみ、人のたくらみ』は繰り返しの美学に通ずる内容だと思います。昔から関心があったようです。
『近代絵画史 ゴヤからモンドリアンまで』この本の帯には**近代の西欧美術を概観して最もスタンダードな“読める”通史**とあります。忘れていましたが、少しは美術史の本を読んでいたようです。
新聞記事によると編集部では通巻2000点を記念して『中公新書の森 2000点のヴィリジアン』という冊子を作成したそうです。
この冊子に川上弘美さんのエッセーが収録されていることを記事で知りました。入手しなくてはなりません。
古い建物のない町は思い出のない人間と同じだ
■「タウン情報」というタブロイド版のローカル新聞があります。週3回発行のこの新聞のコラム担当者の一人に安曇野ちひろ美術館と長野県信濃美術館の館長を兼務している松本猛さんがいます。
先日掲載された「南ドイツの旅」と題するコラムで松本さんは先月(5月)末から今月のはじめにかけての旅行(ドイツ南部に東山魁夷の取材地をトレースすることが目的だったそうです)について書いていました。
およそ40年前、東山魁夷はドイツを旅して数々の名作を描いています。そのうちの何点かを信濃美術館の東山魁夷館で観ることができます(油絵も何点かあって大変興味深いです。全て油絵だったかな?)。
松本さんは、魁夷の取材地の多くを特定することができたそうです。魁夷の絵と符合するポイントが見つかったんですね。
40年前と景観がほとんど変わっていない、いや、魁夷が学生時代に訪れた75年前と変わっていない、ということが文中に書かれています。
第二次世界大戦で破壊された中世の町をドイツの人々が見事に復元したことはよく知られています。
ドイツには「古い建物のない町は思い出のない人間と同じだ」ということわざがあるそうですが(*1)、このような意識を持っているドイツの人々にしてみれば、先のことは当たり前なのかも知れません。日本では考えられないことです。伊勢神宮の式年遷宮、あれは例外的な「儀式」でしょう。
時計の針がありません。ちゃんと保管されているんでしょうか、気になります。
東京駅前の東京中央郵便局の保存問題にについて鳩山前大臣は取り壊すことは「トキを焼き鳥にして食っちゃうようなものだ」と発言しました。「それより剥製にして残すほうがいいだろう」と。
この発言に対してある政治評論家が「あんなものはカラス、剥製にする価値などない」という趣旨の反論をしていました。この建築の魅力が分かりにくいことも確かだとは思いますが。
古い建築を何のためらいもなく次から次へと取り壊してしまう、都市を記憶喪失状態にしてしまう・・・。
悲しいことです。
追記:*1 どうもこれは画家の東山魁夷の言葉のようです。
■ 東京北青山にある複合商業施設「Ao(アオ)」。高さ約90メートルの高層棟は「あたまでっかち」、上層より下層の方が細い。このビルを紹介する日経アーキテクチュアの記事によると、この多面体のフォルムは日影規制から決まったとのことだが本当だろうか・・・。
Ao(アオ) 090329撮影
低層棟はステップガーデンになっていて、屋上緑化されている。誘客効果を考えると前面道路側からその様子がチラッと見えるような計画の方が良かったのでは、などと勝手なことを考えてしまう。
それにしても、あたまでっかち・・・。「モード学園スパイラルタワーズ」に**確かに美しいんです。デザインも素晴らしいんです。しかし…どことなく不安になるんです。**と昴さんからコメントをいただいたが、そのままこの「Ao」にもあてはまる感想ではないか、と思う。
高度な構造解析によって、安全性は充分検証されているのだろうが、やはり「あたまでっかち」は不安定な印象だ。
昔、運動会のかけっこで転ぶと、「あたまでっかちだから(頭が大きいからバランスが悪く、転びやすい)」と言われたものだ。
地階にテナントとして入った紀ノ国屋
この敷地にあった紀ノ国屋のどっしりとした青い店舗がなつかしい。
■ 一昨日(16日)の午後、長野県内は各地で雷雨となり、局地的に雹も降った。直径が1.5cmほどあったというからビー玉くらいの大きさか。
レタスやキャベツなどの野菜に穴があいたり、リンゴやナシなどの小さな実が裂傷するなどの被害が出たそうだ。松本市の南西部でも降雹があって、昔の同級生から届いたメールにも被害が出た、と書いてあった。
自然が相手の農業は天気の急変には対処できない。大変だなぁ、と思う。
■ さて、本題。で、本の話題。
『のぼうの城』和田 竜/小学館を読み始めた。この本も友人から借りていた。かなり話題になった本だと聞いたが、書店で見た記憶がない。まあ、平積みされていたとしても、手にとることもなかっただろう。友人に感謝。
時代小説(歴史小説との違いが分からないが)を読むことはあまりない。最近読んだのは『利休にたずねよ』山本兼一/PHPくらいのもの。
タイトルの「のぼう」とは、
「しかし和尚、御屋形の従兄弟をのぼうのぼうと呼んでもらっては困る」
「でく、をつけんだけありがたいと思え」
という会話があるように「でくのぼう」のことなのだ。
本の帯に**智も仁も勇もない。しかし抜群に人気はある。**とある。主人公は人々からのぼう様と呼ばれ、親しまれている。
さて、こののぼう様、いったいどんなことをして読者を楽しませてくれるのだろう・・・。


090616撮影
■ 名古屋駅前、モード学園スパイラルタワーズ。このランドマークなタワーについては建築雑誌「建築技術」の08年7月号に詳しい。
ドレスをまとったような柔らかな曲面をつくるカーテンウォールの設計、施工。高度な構造解析・・・。
**時代の先端を行き、お互いに切磋琢磨し合う学生達の溢れんばかりのエネルギーが、からみあいながら上昇し、社会に羽ばたいていく様**を表現しているのだそうだ。
技術的にクリアしなくてはならない問題が設計段階から施工段階まで次から次へと出現したことだろう。
日本で最初の超高層、霞が関ビルからおよそ40年、こんなデザインまで出来るようになったのか・・・。
でも技術的に実現可能ということとデザインの必然性とは当然異なる。
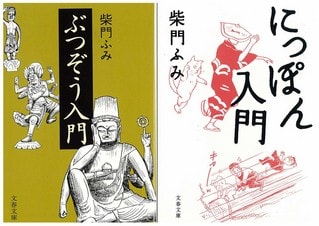
■ 柴門ふみさんの『ぶつぞう入門』文春文庫のカバー折り返しに『サイモン印』と『にっぽん入門』が載っている。
東京からの帰り、松本駅の書店で柴門さんの文庫を探してみた。『にっぽん入門』が1冊だけあった。さっそく買い求めた。で、本日読了。
**仏像よりさらに奥深く、日本文化を探る旅に出るのです。**と担当編集者からメールがあって、旅が始まったそうだ。
『にっぽん入門』には「にっぽん人の心探求」のための全国探訪記が20篇納められている。「諏訪の木落とし坂落とし 御柱に縄文人魂を見たのだ」と「お座敷列車は人情列車 信州カラオケ旅」、長野県も2回旅している。
漫画家になるくらいの人だからやはり観察力がある。人間観察力、仏像観察力、伝統行事観察力・・・ すべてある。ユーモアも当然ある。柴門さんのエッセイがよく読まれているのも頷ける。
「クリスマスの東京湾クルーズ」はクリスマスの夜にイチャつくカップル観察記。銀行の支店長と行きつけのバーのママの不倫カップルか、などと船上観察。で、最後はビシッと、**クリスマスまではイチャつかない。クリスマスに思いきり弾けて、また元に戻る。やはり日本人はハレとケの民族なのだ**と括る。この総括がいい。
「京都「女ひとり」の旅 失恋女はなぜ京都に行くのか」の括り。**京都大原三千院 恋に疲れた女がひとり というフレーズは、日本人の心に強く残り、失恋すると、「そうだ、京都、行こう」と今も多くの日本女性にインプットされている。そういった意味でも「女ひとり」は日本の新しい民謡なのだ。** と歌謡曲論。なるほどね、と納得。
『ぶつぞう入門』同様、『にっぽん入門』にも各章に漫画が載っている。線がなめらかで、丁寧。こちらの方が数段いい。
これはもう、残りの一冊『サイモン印』を読むしかない。
今日も仏像 明日も仏像 これじゃ年がら年中仏像
■ 東京に行くと必ず丸の内オアゾの丸善に立ち寄ります。以前よりも店内が混雑するようになったような気がしますが、まだまだ、ゆったりと本を探して過ごすことができます。
今回は漫画家柴門ふみさんの『ぶつぞう入門』文春文庫を購入。そうです、またまた、まだまだ仏像です。京都や奈良、大阪、そして東北など全国各地に訪ねた仏像について綴るエッセイ。都内を移動する電車内で読了。
**如意輪観音は色っぽく微笑んでいた。あらん、ちょっと酔っぱらっちゃったわぁと頬を染め目を潤ませているぽっちゃり系のお姉ちゃんを、うんと洗練させた感じ。**と、まあこんな感じの仏像評。例の阿修羅についてはやはり夏目雅子に似ているとか、貴乃花だとか、沖田浩之だとか、諸説にぎやかです。
鎌倉の覚園寺の薬師堂、本尊は薬師如来、その両脇は日光、月光両菩薩。月光菩薩は、星飛雄馬のお姉さんに似ているんだそうです。仏像をこのように観察したら楽しいでしょうね。
先日、秋篠寺の伎芸天(ぎげいてん)立像に会いたいと書きましたが、紫門さんに同行していた編集者も「忘れられない。最高じゃないっすかー」と絶賛したそうです。そう、あの柔和な表情、魅せられます。
奈良に行きたい、いや行く!(と、繰り返し書いているときっと実現するでしょう。)
取り上げている仏像について著者のイラストと共に歴史度、技巧度、芸術度、サイモン度という項目を★の数で評価しています。
以下巻末に収録されている瀬戸内寂聴さんとの対談からの引用。
柴門 ハンサムな仏さまもいます。梵天と帝釈天は、帝釈天のほうがハンサムでした。金剛法菩薩も端整なお顔立ちで。
寂聴 仏さまも、美男でなければ拝む気しないですよ。
♪ 飾りじゃないのよ涙は 理屈じゃないのよ仏像は
徹底的に閉じている。
■ JR高円寺駅から中野駅方面に高架に沿って徒歩で5分。「座・高円寺」は外に開く(外の景色を館内に取り込む)ことができるようなロケーションにはない。その意味で伊東さんがサーカスのテント小屋のようなデザインを選択したことは正解だったと思う。
雑誌ではストレートな説明を伊東さんはしてはいないが本音のところは「ここじゃ開けない・・・」ということだったのではないか。
「まつもと市民芸術館」のあわあわなガラスを埋め込んだGRC壁もおそらく同様の理由ではなかったか(プロポーザル段階では、ガラスの大きな開口が構想されていたが、途中で変更されている)と推察する。
所用で東京に出掛けた。用事を済ませてから「座・高円寺」に行ってみた。

エントランスホールや2階のカフェの壁は草間弥生なドットの世界。手摺壁にまでドットを施す徹底振り。
このドットのイメージソースはやはり諏訪湖にあるのだろうか・・・。
テントがつくる曲面そのものの天井。高さ制限という法的な制約をクリアするためだったということだが、上手いなと思う。ただ、階段で2階に上がって、唐突にこの空間になっているのには一瞬戸惑った。まつもと市民芸術館2階のレストラン井(せい)も同様の構成だが、やはり戸惑う。やはり空間的に仕切られていないと落ち着かないのだ。
狭小でロケーションがよくない敷地を上手く生かしてしまう手腕はさすが。
■『マンダラの謎を解く 三次元からのアプローチ』武澤秀一/講談社現代新書読了。マンダラは単に図絵にとどまらず立体的な石窟や飛鳥寺の伽藍配置などにも表現されているとする著者の指摘はなかなか興味深かった。
飛鳥寺は塔を中心としてそのまわりを三つの金堂が取り囲んでいたという。その復元図が載っているが、その伽藍配置をみると確かに立体マンダラだとする著者の見解にも素直に頷くことができる。
その伽藍配置が日本では次第に変容していく。
確かに例えば法隆寺では塔と金堂が横に並び、伽藍の中心性が失われている。薬師寺では東塔と再建された西塔が伽藍の前に配置され、金堂が回廊のほぼ中心に配置されている。塔が本来のストゥーパつまり卒塔婆という意味から変わっている。
塔が伽藍の中心から次第に外れるとともに塔に代わって伽藍の中心に配置された金堂も、横長になっていく・・・。その最たるものが三十三間堂だ(金堂は次第に本堂と呼ばれるようになる)。
著者はこの変化を**立体的幾何学的な、いわば硬直した中心性ではなく、周囲に溶けこむやわらかな叙景性を求めての動きとみることができる。**と指摘している。
そのように変容していったのは一体何故なのか。そのことについて著者は「島国ゆえに」という小見出しからも分かるように、日本の地形の特性、大陸とは異なり細かな地形の変化で、つねに目印となる山並みが目に入ってくる島国であることを挙げている。
塔を中央に据えた中心性の強い伽藍配置不要の地理的特性。これは、和辻哲郎の『風土』にも通ずる指摘だ。
なかなか興味深い論考だった。さて、次はこの本。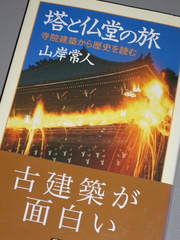
『塔と仏堂の旅 寺院建築から歴史を読む』山岸常人/朝日選書
■ 村上春樹の新作『1Q84』。発売からわずか2週間で発行部数が100万部を越えたそうだ。そういえばいつも立ち寄る書店で平積みされているこの新刊を見て、数日後には一冊もなかった。この異例の売れ行きにはエルサレム賞授賞式でのスピーチも大いに関係があると言われている。改めて全文を読んでみると、やはり上手いスピーチだと思う。村上作品が海外で評価されているということも分かる。
今日の朝刊の文化面に『1Q84』の書評が掲載されている。7日(日)の朝日新聞にもやはり書評が掲載された。これらの書評によって、この小説の輪郭がなんとなく分かってきた。
「1984年」と「1Q84年」、ふたつの世界が層をなす。ふたりの主人公、青豆と天吾、ふたりの物語が交互に展開される。今までの村上春樹の小説世界、その新たな展開。物語が上手く編み上げられているのだろう・・・。
『風の歌を聴け』
『1973年のピンボール』
『羊をめぐる冒険』
『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』
『ノルウェイの森』
『ダンス・ダンス・ダンス』
『国境の南、太陽の西』
『ねじまき鳥クロニクル』
『スプートニクの恋人』
『海辺のカフカ』
『アフターダーク』
一昨年のことだが、数ヶ月かけて村上春樹の長編小説を一通り読んだ。一時「仏像」を休止してでもこの小説を読まなくては、という気持ちになりつつある。夏休みにでも読んでみようか・・・。














