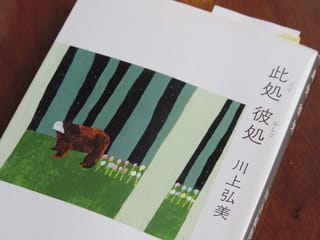
■ **名前は不思議だ。「弘美」という名で育ったことが、自分の性格その他に何か影響を及ぼしているのだろうかと、ときおり考えることがある。もしわたしが「さおり」や「ゆりえ」だったら、もっと明るい性格に育ったかもしれない。**(17頁)
もし、自分が別の名前だったら・・・、なんて考えたことはない。
川上弘美。別の名前だったら作品を読み続けて来たかどうか・・・。
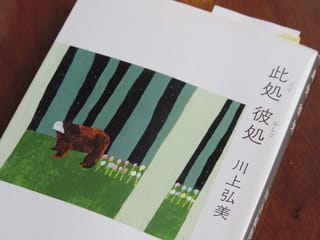
■ **名前は不思議だ。「弘美」という名で育ったことが、自分の性格その他に何か影響を及ぼしているのだろうかと、ときおり考えることがある。もしわたしが「さおり」や「ゆりえ」だったら、もっと明るい性格に育ったかもしれない。**(17頁)
もし、自分が別の名前だったら・・・、なんて考えたことはない。
川上弘美。別の名前だったら作品を読み続けて来たかどうか・・・。
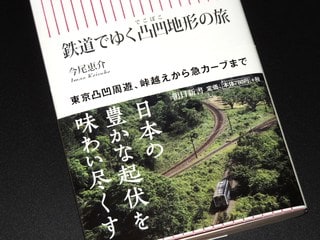
『鉄道でゆく凸凹地形の旅』 今尾恵介/朝日新書
■ 世の中に地図好き、マップラバーは多い。この本の著者の略歴には地図研究家、日本地図学会「地図と地名」専門部会主査とあるから、単なる地図好きではなく地図マニアの域にある人だろう。
地図マニアにもいろんなタイプがある。どうやら著者は「地図上の鉄道」マニヤ、らしい・・・。この本には鉄道曲線や勾配の話がしばしば出てくる。
地図マニアならば、地図を眺めていればその土地の風景が目に浮かび、更に加えて鉄道マニアなら、地図上の鉄道を旅することができるのだろう。本書はそのようなマニアにはたまらない1冊。
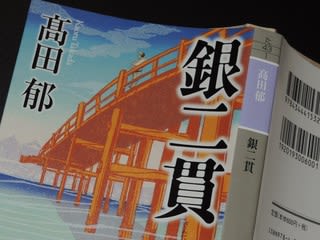
■ 『銀二貫』 高田郁/幻冬舎時代小説文庫 この時代小説を先日読んだ。
**思えば、自分は偶然の出会いによって、今日まで生かされてきた。仇討の場で斬り殺されるところを和助に救われた。同じ丁稚として出会った梅吉は、恐らく生涯を通じての大切な友となるだろう。天神橋の上で巡り逢った真帆、その父親の嘉平、二人に寒天の世界を広げてもらった。半兵衛に出会うことで糸寒天が生まれた。あれほど自分を忌み嫌っていた善次郎が、今は信頼を寄せてくれている。そうしたこと全てが、今は偶然というよりも、天の配剤に思えた。**(268頁)
この引用部分から物語の輪郭がおぼろげながら浮かんでくると思う。(*1)
人情物語、恋物語。そして涙もろい私には心に沁みる涙物語だった。
プレゼントされなければ、読む機会はなかっただろう。Mさんに感謝。
*1 ウィキペディアにあらすじが載っています。

富岡製糸場が世界遺産に決まったことを祝し、過去ログを載せます。
■ 群馬県富岡市にある富岡製糸場の見学に行ってきました(2013年4月13日)。ここには近代日本の幕開けを象徴する建築が建ち並んでいます。
世界最大規模の繭倉庫(東西2棟)と繰糸場という主要な施設を広大な敷地(53,738㎡)にコの字形に配置しています。コの字の中に繭の乾燥場と蒸気釜所、鉄水槽などを配置し、コの字の外側すなわち敷地外周に女工の寄宿舎、工場建設の指導にあたったフランス人ポール・ブリュナの家族の住居(といっても面積は916.8㎡と広い)や病室付きの診療所、フランスから招いた女性技術者(女工に技術指導をした)の宿舎、検査人館などを配置しています。
明治政府が日本の近代化を生糸の生産と輸出に賭けて建設した富岡製糸場。これだけの規模の施設を構想したことと、それを1年数ヶ月で完成させた明治時代の日本の底力に驚きます。140年経過して今なお健全な建築、当時の職人たちの技術の確かさに敬服します。

▲ アプローチ道路正面のアイストップは富岡製糸場の東繭倉庫、1階中央のゲートが印象的。ヨーロッパの古い都市空間を思わせる構成。
東繭倉庫 木骨レンガ造2階建て 和の真壁と洋のレンガ 桁行方向の長さ104.4m 梁間方向12.3m 高さ14.8m 明治5年建設
▲ 東繭倉庫正面(東側)外観 木のフレームと両開き扉の繰り返しの構成が美しい。 繰り返しの美学!
▲ 妙義山から伐り出されたという杉材、現甘楽町につくられた窯で焼き上げたレンガ、下仁田の石灰を主成分とする漆喰、連石山(甘楽町)から伐り出してつくられた礎石、地元地消でつくられた施設
柱脚と礎石の固定方法は?
▲ アーチの中央頂部のキーストーンに彫り込まれた建設年 明治五年
▲ レンガ造アーチの端部と柱の取り合い
▲ 2階床の合わせ梁の小口 雨対策は?
▲ フランス積みのレンガ壁
▲ 裏面(西面)外観 バルコニー式の外廊下
▲ 内観 東繭倉庫1階内部(展示スペース) 木の白い通し柱と2階の床梁
繰糸場 木骨レンガ造平屋建て 桁行方向の長さ140.4m 梁間方向12.3m 高さ12.1m 明治5年建設
▲ 繰糸場北面外観 ガラスはフランスからの輸入品、とガイドさんの説明
▲ 繰糸場の内部 木造トラス これぞ繰り返しの美学!
■ 以下過去ログに追記
日本の世界遺産リスト
文化遺産
1 法隆寺地域の仏教建造物(1993)
2 姫路城(1993)
3 古都京都の文化財(1994)
4 白川郷・五箇山の合掌造り集落(1995)
5 原爆ドーム(1996)
6 厳島神社(1996)
7 古都奈良の文化財(1998)
8 日光の社寺(1999)
9 琉球王国のグスク及び関連遺産群(2000)
10 紀伊山地の霊場と参詣道(2004)
11 石見銀山遺跡とその文化的景観(2007)
12 平泉(2011)
13 富士山(2013)
14 富岡製糸場と絹産業遺産群(2014)
自然遺産
1 白神産地(1993)
2 屋久島(1993)
3 知床(2005)
4 小笠原諸島(2011)

■ カフェバロでミニミニ講座をさせていただくことになりました。アップグレード版となるように努力しています。
お問い合わせはカフェバロまでお願いします。
電話 0263 78 1986
カフェバロのブログはこちらです。
よろしくお願いします。
カクさん チラシを転載させていただきました。



(再・492欠番) 松本市島立大庭
■ 3角形の櫓に円形の屋根と見張り台。屋根の頂部をどのように処理しているかは注目ポイント。この屋根では球状に処理している。これは松本市内の他の火の見櫓でも見たことがある。避雷針に矢羽形の風向計。屋根の下に中心を外して半鐘を吊るしてある。半鐘の表面はツルリンチョ。
見張り台の手すりには縦しげな手すり子、飾りっ気なしのシンプルなつくり。3方向に向けてつけられたスピーカー。見張り台の床直下にアーチ部材と反りのついた方杖。櫓の途中の踊り場は櫓の柱を結ぶ手すりと床で簡素なつくり。
脚部を構成するアーチ部材は柱部材の途中で終わっている。構造的に柱の下半分が単材というのはどうなのか・・・。いつも同じことを書くが、これは意匠的にも好みのタイプではない。
梯子のステップに2本の丸鋼、これは良い。全体的に錆が目立つ、これは残念。

491 アルピコ交通上高地線大庭駅近くの火の見櫓

■ 松本市内の某カフェのYさんと鉄談義。もしかしたらYさんは鉄子さんかもしれない・・・。
先日、塩尻市宗賀で火の見櫓と中央西線を走る列車のツーショットを撮った。シャッターチャンスは一瞬で動く鉄を撮るのは難しいと記事に書いたが、もじもじさんから連写すればいいでしょうとアドバイスしてもらった。なるほど、電車は連写、か・・・。
でも敢えて連写しないで、単写(*1)で撮ることにした。下手な鉄砲、じゃなかった「下手な写真 数撮りゃ 写る」はしないでおこうというわけだ。
ということで、単写したのがこの写真。まあまあの写真じゃないか、などと自分で思ってしまったら、上達しないから、ダメだ、こんなんじゃ  としておく。
としておく。
撮り鉄の人たちは自分に様々な制約を敢えて課すことでディープな世界に入り込んでいく。トンネルから出る瞬間を撮る、鉄橋を渡るドクターイエローを撮る、新幹線を流し撮りする、等々。ならばぼくは動く鉄と動かない鉄のツーショットを自分に課そうと思う。動く鉄と動かない鉄の相性はよさそうだ。
これで楽しみが増えた。
*1 単写ということばをカメラの設定モードで知った。


駅舎側の柱のディテール
■ 小野駅は中央本線(辰野支線)の小さな駅だ。ホームを繋ぐ跨線橋の柱に注目。今なら角型鋼管を使うだけで、味もそっ気もないが、この柱はすごい。
駅の開業が明治39年(1906年)とのことだから、この柱もその時に造られたものかもしれない。 いや、少し時代は下るのかな・・・。ブレースに用いられているターンバックルは火の見櫓でもおなじみのリング式だが、肉厚だ。今なら鋼管をカットしてつくるだろうが、昔は平鋼を曲げてつくっていたようだ。
階段を支える側桁にも注目。今ならH形鋼を用いるのが一般的だろうが、この跨線橋はラチス梁を用いている。
コスト縮減と工期短縮最優先。今は本当に豊かな社会などとはとても言えないのではないか、このような工作物を観察しているとそう思えてならない。


■ 左は辰野町小野に、右は朝日村西洗馬に立っている火の見櫓です。どうでしょう、立ち姿の印象が似ていませんか?辰野の火の見櫓は4角形、朝日の火の見櫓は3角形と平面形は違っていても両者とてもよく似ています。


屋根のてっぺんの飾り、見張り台の手すり、方杖、見張り台床の開口。これらのデザインもよく似ています。


脚部もよく似ています。アーチ部材と横架材を繋ぐプレートの形は瓜二つです。


梯子も似ています。手すりの使用部材、丸鋼を2本並べたステップ。1本の場合の方が多いかもしれませんが、滑りにくさが格段に違うでしょう。1本の場合は靴の裏とは線接触、2本の場合は面的な接触になりますから。
実はこの2基の火の見櫓、同じ鉄工所で造られたことが分かりました。実に誠実な造りだと思います。人柄が出るんですね~。共に昭和30年の8月に完成しています。建設費も分かりました。どのようにして分かったのか、そのことを書く機会が後日あるかもしれません。

490 上田市下之郷
■ 東信地方(*1)によく見られる姿・形の火の見櫓。直線的に広がる細身の櫓、上部の平鋼ブレース、カンガルーポケット、4角形の小さな屋根と4角形の見張り台、そしてがに股。

屋根と見張り台の端正な造り。このようなデザインも好み。



下から見上げる・・・
*1 長野県は地形的、地理的状況から北信、中信、南信、東信の4つのブロックに分けられている。

『眺める禅』 枡野俊明/小学館
■ このところ火の見櫓の記事を続けたので、「また火の見櫓、つまんない」という閲覧者の声が聞こえる・・・。で、今回は本。
4月に東京した際、代官山の蔦屋で買い求めた本。積読状態が続いていたが、先日ようやく読むことができた。著者の枡野氏は曹洞宗の寺の住職にして庭園デザイナー、多摩美大の教授も務めておられる。
本書は枡野氏がデザインした禅の庭、枯山水が心安らぐ文章とともに何例も紹介されている。
以下本書からの引用(51頁)
**
心の在り様が違えば、受けとり方も違うのです
そのときどきの偽りのない心を知る
「禅の庭」はそういうものでもあるのです
**
幕の内弁当のような足し算な暮らしをしていていると、枯山水の引き算の美学に惹かれる。 どこか枯山水の庭を観にいこう、京都か・・・。
■ 南牧村から佐久市に向かって国道141号線を移動中に見かけた火の見櫓のうち、3基を写真に収めた。(487、488、489)

487 小海町豊里 
屋根の頂部、避雷針に付けてある飾りのデザインがユニーク。下端が屋根に固定されておらず「くるりんちょ」な処理をしてある。
見張り台にモーターサイレンとスピーカーが設置してあるのは残念だが仕方無い・・・。

488 小海町豊里



489 小海町豊原


こんなにエレガントな踊り場、観たことない。手すり子の曲線が美しい。手すりのすぐ下の装飾の曲線も優美。見張り台や脚元にいろんなものが付いているが、これらがなければ、「超」をつけてもいいくらい美しい火の見櫓。 櫓のどこにも錆も傷もない。




3基は全体的な印象は似ているが、部分的にはそれぞれ違っている。例えば屋根の装飾、頂華(フィニアル)のデザインが違う。3基とも見張り台は円形だが、手すりのデザインが違う。 脚部のデザインも違う。
火の見櫓 みんなちがって みんないい

486 南佐久郡川上村樋沢
■ 見張り台の大きさに比して屋根が小さい。よく見ないと小さな蕨手には気付かない。屋根を支える柱材が細い!鋼板張りの床。

櫓の外側に設けられた踊り場。小屋根の下に半鐘を吊るしてある。平鋼を踊り場の床を支える方杖に使っている。まさか人の体重(荷重)程度で平鋼が座屈することはないだろうが、取り付け方を上下反転して手すりの付け根のあたりから、引張り材として付けた方が構造的な違和感を感じないですむのかもしれない。
脚元。アーチ材と柱材をガセットプレート(部材接合用鋼板)で接合している。このような脚元を見るのは初めてかもしれない・・・。

485 南佐久郡川上村御所平
■ 県道68号線沿いに立つ火の見櫓。 4角形の櫓と、同じく4角形の屋根(ともに平面形)に円形の見張り台という構成。櫓は直線的に下方に広がっている。東信地方では櫓の上半分のブレースに平鋼を使っているものが多いが、この櫓は全てリング式ターンバックル付きの丸鋼を用いている。平鋼よりスケスケ感がある。

屋根が変形している。頂部の避雷針にはやや大きめの飾り、下り棟の先には小さなくるりんちょ(蕨手)がついている。見張り台の手すりはしもぶくれ。下を広げることに機能的な理由は見い出せない。単なる意味の無いデザインか。蕨手同様細い丸鋼の飾りがついている。床を支える方杖は反っている。

中間のカンガルーポケット踊り場(と勝手に命名した)は東信によくあるタイプ。手すりは見張り台と同じデザイン。ここにも半鐘が吊り下げてある。半鐘の表面はつるりんちょ(平滑)。踊り場側のブレースは2段抜いてある。消防団員の昇降を考えればこれは当然のこと。

脚は短い。やはり末広がりの櫓でないと美脚にはならない。信号表示板が吊るしてある。アーチ部材が基礎まで伸びているのは構造的にも意匠的にも好ましい。

■ 茅野市金沢の道路をまたぐ火の見櫓は新聞にも取り上げられ、また先日はテレビでも紹介されました。 長野県内には他にも道路をまたぐ火の見櫓があります。私が知っている道路またぎ火の見は他に南牧村と飯山市にあります。下は南牧村海尻の生活道路をまたいで立っている火の見櫓です。



反対側から見るとこんな様子です。茅野の火の見櫓と比べてこの火の見櫓はごく自然に道路をまたいでいます。