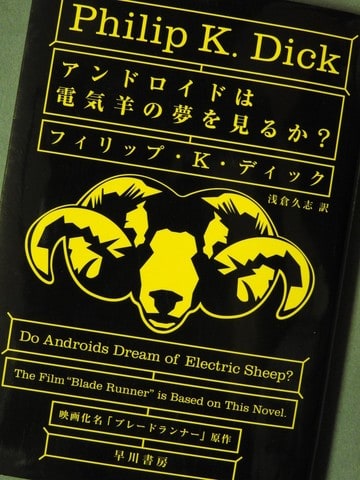■ 毎朝ラジオを聴きながら勤務先に向かう。聴く番組は決まっている。NHKラジオ第一の「マイあさ!」だ。昨日(30日)、番組の中の「マイ!BiZ」というコーナーで、組織の枠を超えて複数の仕事を持つパラレルワーカーの若い女性が語るランチタイム活用法、「年間200時間のランチタイム、どう活用しますか」を聴いた。
その女性は何か新しいことが始まったらいいなという想いからランチタイムに「はじめまして」の人と会うことにしているそうだ。ランチタイムなら1時間、枠が決まっているから気軽に初対面の人と会うことができるという。ここから新たな仕事が始まったりすることもあるそうで、このような行為を「可能性のボタンを押す」と捉えているそうだ。なるほど! 確かに週に5時間、月20時間、年200時間以上にもなるランチタイムを有効に使わない手はない。
私の場合はランチタイムではなく早朝、人ではなく本。しばらく前から朝カフェ読書をしている。週2回、月8回で8時間。ボケーっとしていてもそれまでの早朝、24時間営業している書店で本を探して朝カフェで読み始める。
昨日は朝カフェで『舟を編む』三浦しをん/光文社文庫を読み終えた。本を読み始める朝カフェ、本を読み終える朝カフェ。
新しい辞書の完成目指して日々作業を続ける玄武書房の辞書編集部の人たち。彼らが織りなす人間模様と共にその過程が描かれている。
**一冊の辞書を作るのに、初校から五校まで、校正刷りが五回も編集部と印刷所のあいだを行き来するようだ。校正刷りに修正を入れては印刷所へ戻し、修正が反映されたものが印刷所から送られてきたらまた確認し、といった作業を五回繰り返すということだ**(199頁)そう、私もまったく同じ作業をした。
主人公の馬締(まじめ)と結婚した香具矢(かぐや)は料理人。彼女は編集者のひとりに次のように語る。**「私は十代から板前修業の道に入りましたが、馬締と会ってようやく、言葉の重要性に気づきました。馬締が言うには、記憶とは言葉なのだそうです。香りや味や音をきっかけに、古い記憶が呼び起こされることがありますが、それはすなわち、曖昧なまま眠っていたものを言語化するということです」**(266、7頁)
なるほど!
この作品は映画化されている。観よう!
時間だ。これから東京する。






























 420
420