
078 塩尻市桟敷
■ 桟敷公民館の道祖神のすぐ近くに立っている火の見櫓というのがこれ。
屋根の印象が今まで見てきた火の見櫓と異なるのは、むくっているように見えるからか(「むくる」は「反る」の逆)。理由が分からないが、見張り台に水平ルーバーが付けられている。写真で屋根の下が黒く見えるのはそのため。
銘板により昭和29年の竣工だと分かった。
追記:水平ルーバーは鳥避けかもしれない(160605)

078 塩尻市桟敷
■ 桟敷公民館の道祖神のすぐ近くに立っている火の見櫓というのがこれ。
屋根の印象が今まで見てきた火の見櫓と異なるのは、むくっているように見えるからか(「むくる」は「反る」の逆)。理由が分からないが、見張り台に水平ルーバーが付けられている。写真で屋根の下が黒く見えるのはそのため。
銘板により昭和29年の竣工だと分かった。
追記:水平ルーバーは鳥避けかもしれない(160605)

路上観察 旧島々(しましま)駅舎
■ 大正9(1920)年に建設された島々線の駅舎(島々線は昭和30(1955)年に上高地線に改称された)。
昭和41(1966)年に島々駅の一駅手前の赤松駅(赤松地区の火の見櫓をしばらく前に載せた)が新島々駅と名称が変わった。島々駅は無人駅となり、その後昭和58(1983)年の台風による土砂災害がきっかけで新島々~島々間が廃止された。
旧波田町(松本市波田)が平成2(1990)年にこの駅舎を新島々駅の向かいに移築。現在は農産物などの直売所を兼ねた観光案内所として使われている。
今でも駅舎として現役ならいいのに、いや、解体されずに保存されているだけでも喜ぶべきか・・・。

塩尻市の桟敷公民館脇の双体道祖神
■ 遠くから見えた火の見櫓めざして車で集落の中の狭い道を進んだ。火の見櫓のすぐ近くにこの道祖神が立っていた。両神の表情がよく似ている。女神が随分大きな酒器を手にしているが祝い事には酒が付き物だ。右の男神が手にしている盃には賽銭が置いてあった。
側面の刻字から安政5(1858)年の作と分かった。永い年月人びとの日々の暮らしをそっと見守ってきた道祖神。火の見櫓と共にこれからも・・・。

■ 茅野の火の見櫓たちを紹介します。
①070
②-1 071
②-2 JR中央東線青柳駅近く
①と②の火の見櫓は中央東線の電車からよく見えます(進行方向右側の窓から)。
②は重量鉄骨で組んだ火の見。
③-1 072
③-2 金沢 大沢
④-1 073
踊り場への梯子の掛け方に注目
④-2 金沢小学校前
屯所の2階から直接上ることができるように空中梯子が掛けられています。
⑤ 074 金沢 下町
⑥ 075 宮川 坂室
⑦ 076 宮川 田沢
火の見櫓の後ろに邪魔なモノが・・・

069
■ 火の見櫓が道路をまたいで立っている! 諏訪南で高速を下りて右折、国道20号線に出たらまた右折。そのまま直進。その距離2kmくらいか。中央東線と国道に挟まれた茅野市金沢木舟地区に立つ巨大恐竜のような火の見櫓。

066 東筑摩郡朝日村針尾

■ ホースが何本も掛けられているので、櫓の印象が違って見えるが仕方がない。
避雷針の付け根のところの飾りが、遠目には風見鶏と同様、方位を表すアルファベット4文字に見えたが、近づいてみてそうではないことが分かった。
見張り台の手すり子の下端が外側にふくらんでいるが、これは機能的に特に意味があるとも思えないので「単なるデザイン」だと思う。
床面の開口が大きくて見張り台に立つのは怖そうだ。梯子が床面で終わっており、別に縦手すりが櫓の柱に取り付けられているが、これでもまだ上り下りには不自由ではないかと思う。
年末になるとこの火の見櫓には消防団員の手によってイルミネーションが取り付けられる。そのころまた観察に出かけようと思う。


■ 火の見櫓の必須アイテムの半鐘。上の半鐘のように表面がつんつるりんなものが多いように思う。下は除夜の鐘でおなじみの梵鐘のような半鐘。
戦争中は半鐘も供出の対象になったと聞く。それで半鐘の代わりに板を吊るした火の見櫓もあったらしい。大切な半鐘を地面に埋めて隠し、供出しないということも行われたようだ。
下の半鐘がいつ頃つくられたものかは分からないが、なかなか重厚感があって低い音が遠くまで響いていきそうな気がする。
半鐘も有る無しを確認して終わりではなく、その姿をきちんと観察することも時には必要だ。
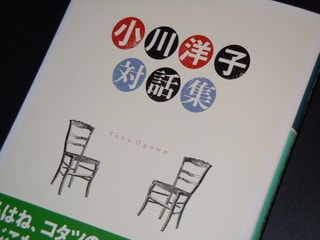
■ 『小川洋子対話集』幻冬舎文庫読了。
小川洋子さんは『博士の愛した数式』を書くにあたって、数学者の藤原正彦さんを取材している。藤原さんは、同小説(新潮文庫)の解説文にその時の小川さんの印象を**清楚な大学院生のような人だった**と書いている。
彼女は取材の時**携えたノートに質問事項がびっちり書いてあり、次々と質問を投げかけてきた。**そうだ。
小川さんの優等生ぶりはこの対話集にも出ている。相手のことを実によく下調べしているのだ。
例えば江夏豊さんとの対話では**(前略)二年目の、奪三振日本記録のエピソードがすごいですね。まずタイ記録を王選手から奪って、さらに新記録も、王選手からとるためにわざと打者を一巡させた。**と発言。小川さんは大の阪神ファン、でもこんなことは調べないとわからないことではないだろうか。
これに江夏さんは**あれは、数え間違えたんです。**と応じ、新記録だと思っていたら、まだタイ記録だとキャッチャーの辻さんに教えられ、下位打者に三振されないように投げ、公言していた通りふたたび王選手から三振を奪って記録を達成したことを明かしている。
**でも確か、0対0の試合でしたよね。打者を一巡させるといっても、打たれるわけにもいかない。**と小川さんはマニアな発言。
また、田辺聖子さんとの対話では**田辺さんのお母様も岡山からお嫁に来られて、大家族のなかで、ご苦労はあったと思います。**とよく調べておかないとできない発言をしている。
では、仮に川上弘美さんとの対話なら一体どんなことが話題になるだろう。ふたりとも芥川賞の選考委員だから、文学についての話題が中心になるだろう。小川さんは川上さんの作品をどう評するだろう・・・。既にどこかに書いているかもしれないな。

063 火の見櫓のある風景 清々しい朝 松本市岡田にて
064 火の見櫓のある風景 実りの秋 松本市波田にて
■ 「花」という対象に対する視点、アプローチの方法はさまざまだ。画家と植物学者とでは全く異なる。画家は自身の美的感性によってひたすら花から「美」を抽出しようとする。一方植物学者は知的好奇心に根ざした分析的な視点で、例えば花の構造を把握しようと仔細観察する。
対象を火の見櫓に変えても同じこと。火の見櫓のある空間の雰囲気、風景を捉えようと観察する人や、ぐっと火の見櫓に近づいてその構成要素、パーツを分析的に観ようとする人もいる。遠景に関心を寄せる人も近景に関心を寄せる人もいる、と言い換えてもいい。
言いたいのはどちらが優れているか、ということではない。対象に対する視点やアプローチの方法は人それぞれでいい、ということだ。
ところで、木を見て森を見ないとか、医者は病気を診て人を観ないというようなことが言われる。この批判めいた指摘は複視的に部分だけでなく全体もみるべき、ということだ。
趣味で火の見櫓を観察しているのだから、このような指摘など気にすることはない。前述したように、人それぞれでいい。でも私は火の見櫓を先に挙げたふたつの視点で観察したい。
時には火の見櫓のある風景の郷愁を、時にはものとしての成り立ち、システムを。

062
■ この火の見櫓、先日取り上げた白馬村の火の見櫓(←過去ログ)と立ち姿が似ていると思った。脚部に付けられていた銘板を見るとやはり同じ鉄工所でつくられたものだった。
プロポーションがなかなか良く、清々しい。屋根と見張り台の大きさのバランスが良いし、飾りのないシンプルな手すりも好ましい。また、屋根の上の避雷針の長さもちょうど良いし、そこに付けられているつる状の飾りもまた、良い。
あえて気になる点を挙げるとすれば、半鐘。ドラ型ではなく寺院にある釣鐘と同型のものが屋根の下に吊るされていれば、私はこの火の見櫓の意匠(立ち姿という評価項目)に五つ星をつける。




060(再)松本市稲倉の火の見櫓 100919
■ 反りのきつい六角形の屋根。頂部の球状の飾りをつくるのは大変だっただろう。避雷針にトンボがとまっている(写真ではよく分からないが)。矢羽根の向きには意味があるのだろうか。
三角形の平面形の櫓は主材(柱材)、水平材(横架材)とも鋼管が使われ、斜材(ブレース)にスリーブジョイントが使われている。スリーブ型のターンバックルを火の見櫓で見たのは初めて(環状のターンバックルが一般的)。建造年は不明だが、これらの使用部材や接合部の様子から比較的新しい火の見櫓と判断される。