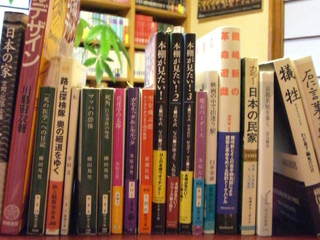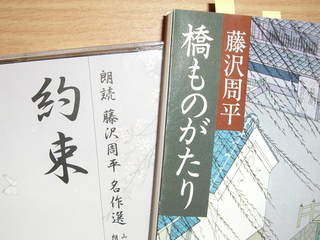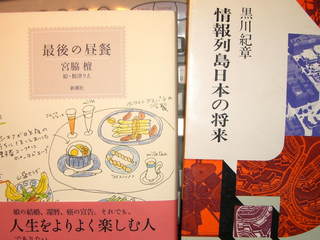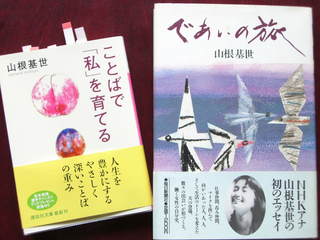「サピア・ウォーフの仮説」という興味深い仮説があることをごく最近知った。あることについて検索していたのだが、その関連でヒットした。都合よくこの仮説を解釈すると、言語が世界の見え方を規定する、別の表現をすれば認識の仕方を規定するという仮説で、言語(言葉)に無いものは知覚されないというもの。
これは、知性と感性とによってものは知覚、認識されると私がこのブログに書いてきたことと同じ内容ではないか・・・。知性と言語は、同義と考えて差し支えない。 但し、感性によって知覚されるということについてはどうなんだろう。言語化されていないことの知覚、このことについてもこの仮説は触れているようだ。
アメリカの二人の研究者によって唱えられた説のようだが、欧米人は日本人のように、例えば虫のなきごえを「いいな!」と感ずるような感性による知覚、認識は難しいようだから、言語、換言すれば知性に偏った説になったのかも知れない。 きちんとこの仮説について調べたわけではないので理解がまだ浅い。テキストを探して勉強してみたい。